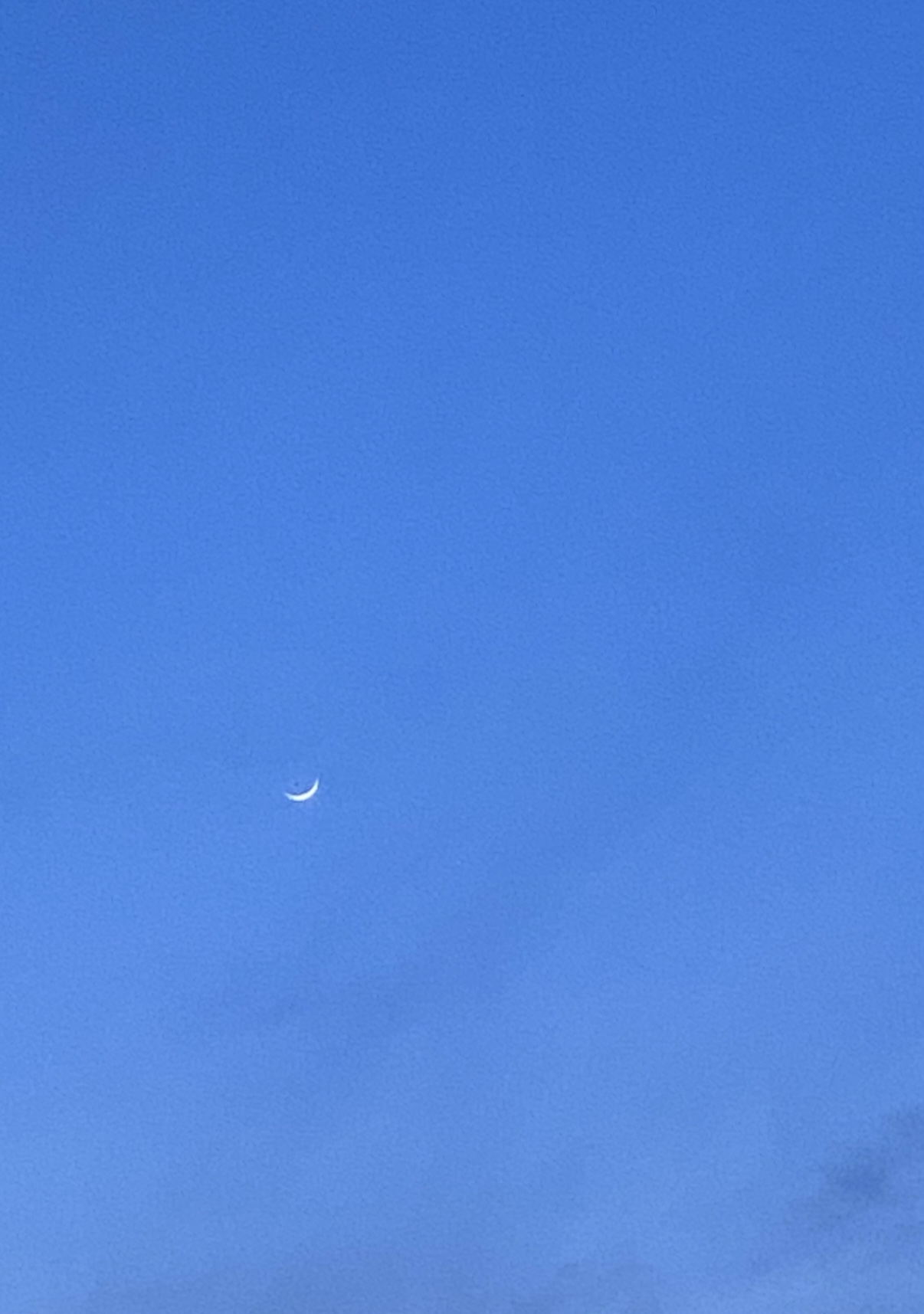前回は気についてまとめたので、今回は血についてまとめる。
血には、水穀の精微から作られる方法と、腎精から作られる方法の2種類がある。
● 水穀の精微より
脾胃の「運化作用」によって、飲食物から作られた水穀の精微は、営気となり、津液と共に脈中を通って肺に到達する。
肺で清気と合わさり、さらに心火によって熱されると赤くなり、血となる。
● 腎精より
腎陽によって温められることで、腎精が血に変わる。
また逆に、血が精に転化することもあり、これを「精血同源」という。
血と関係の深い臓腑
● 心「神」
心には「神」が宿る。
神とは、魂や精神活動を司るもの。
心に血が十分に満たされていないと精神活動が乱れ、不眠・多夢・健忘・狂躁などを引き起こす。
また、心は血を全身に巡らせるポンプの働きも持っている(=推動作用)。
● 肺「百脈を朝す」
「朝す」とは、集めて送り出すという意味。
全身の経脈は肺に集まり、ガス交換によって新たな宗気を得て、再び全身に巡る。これを「百脈を朝す」という。
肺はこの働きを通じて血の循環に関わっている(=宣発作用)。
● 肝「肝血」
肝は血を蓄え、必要に応じて身体各部へ血を送り、調整する。
日中は身体の動きや精神活動のために血が分布し、睡眠や休息のときには肝に戻る。
この分布がうまくいかないと、目・筋肉・月経などに不調が現れる。
→ 肝の「疎泄作用」や「蔵血作用」に関係する。
● 脾「運」び、生「化」する
血や気など、人体に必要な生理物質は水穀の精微から作られる。
脾が健康でなければ、こうした生理物質を作る源がなくなり、正常な活動を維持できない。
また脾には、必要な生理物質を血管の外に漏らさないようにする働き(=統血作用)もある。
この機能が失調すると(脾不統血)、皮下出血・血尿・不正性器出血などの症状が起こる。
まとめ
- 血は「水穀の精微」または「腎精」から作られる。
- 精神・血流・栄養分布など、血はさまざまな臓腑と深く関わっている。
- 脾・肺・心・肝、それぞれの機能がバランスよく働いてこそ、血が正常に生成・循環・調整される
<参考文献>
神戸中医学研究会(1995)『基礎中医学』株式会社燎原
関口善太(1993)『やさしい中医学入門』東洋学術出版
高金亮(2006)『中医学基本用語辞典』東洋学術出版