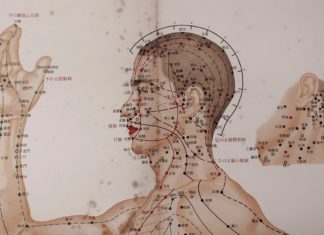『中医内科学 第2版』 冒頭
中国語の本を訳していきます。
正確な訳では必ずしもないところもあると思いますが
もし誤訳などがあれば
その都度修正します。
---------------------------------------------------------------------------------
『中医内科学 第2版』人民衛生出版社
冒頭部分から
---------------------------------------------------------------------------------
宋金以前、中医学には「中医内科」の名は無く、
中医内科は近代になって
少しずつ発展してきた学科名称である。
中医学的伝統概念中に、特別に表記して独立したものを除いた、
つまり外、婦、児、歯、眼、正骨等の科以外の病証のほとんどが
中医内科学的な範疇に隷属する。
中医内科学は、中医学の重要な構成要素であり、
各種内科病証の病因病機、臨床の特徴、弁証論治
および予防保健的な対策などの研究を行う
一つの臨床学科である。
十分に多い系統の考え方を反映している
中医独特理論体系は、
豊富な弁証論治の内容と調和し、
その他の各学科とも分割できない関係を有している。
中医学の整体観念の特色は、
いかなる病証も、全体の有機的な病理変化が局部に反映する、
いわゆる内にあるものは、必ず外に形となる、という考え方による。
このほか、人体における内部の臓腑、外部の苗竅、
および経絡の相互の関連からこれらを一つの整体とし、
かつ、人体と自然界とをまとめて一つの整体とみなし、
合わせて、いずれも中医内科学の弁証論治は
一連のつながりのある関係を備えるのである。
これらの意義によって、中医内科学は、
中医の各臨床学科の一科目の臨床基礎学科となった。
広義の概念を考えると、
中医の理論の核心部分は弁証論治の全過程であると同時に、
当然、内科学の範疇に属さなければならないものである。
学科の分化と発展により、
弁証論治の全過程の中で
弁証部分は診断学科の部分的内容を為し、
論治部分は、その他の各臨床専門学科の外的内容を除去し、
まさしくこれが狭義の中医内科であり、
流行病、雑病の大部分である。
前者(流行病)は傷寒および温病であり、
後者(雑病)は内治法を主とするもので、
各専門学科が包含する病証以外で、
その専門学科の中でも
臓腑と経絡との相関的な病証についてがこれに含まれる。
舞台など
舞台
主役をどこに置くか。
そこが以前からずっと課題として残っている。
受付でもこのシーンはこの人にやってもらった方がいいかな?と考えたりもするが黒子になる意識が薄い。
これはチームで行っている事。
受付時、一緒に働いている方々にやって頂いている事を思い返す。
上手い人達はサラッとして作意がないが、落としたところを助けて頂いている。
そうなる為にまずは太極的に、先の動きも考える。
感じられるところまでいければいいが、まずは考えてみる。
考えた上で考える事が違っていれば考えを捨てる。
自分の場合、内省して答えを出すというより、他からヒントをもらって練度を上げていきたい。
外を見る目を養う為にも意識を変えなきゃいけないな。
やり方は色々試していきます。
舌の考察①
色:淡紅
形:軽く歯痕舌、軽く胖大
その他:斜舌
裏は出すのに苦労している様子も窺える。
正気が無くて出せないというより、緊張して舌を操作出来ていない印象。
口の開け方、舌下静脈は偏る
脾気虚。
口の開け方や斜舌など偏りを感じる。
気の偏りがあるかもしれない。
また、舌下を見せるのに歯が見えるまで出すところに真面目で気逆を起こしやすい要素があると思われる。
舌の考察②
前回よりも舌下静脈付近の細絡が目立つ。
これも瘀血の症候としてみれそうか。
以前として強い歯痕舌が見られ、気虚の程度が強い。
考察③
暗紅色、裏に熱がこもり、瘀血。
自身の体なので他の情報と一致させられるが、舌先右の赤みは右の上焦の停滞と一致させられるかもしれない。
食べることについて①
皆さま、初めまして。
受付をしております、鍼灸学生のイワイです。
ここでは、日々の学習のことやそこで生じた疑問など様々なことについて、学生なりに書いていきます。
どうぞよろしくお願いします。
早速ですが、新年度になりました。
桜が満開で見頃を迎えてますね!
春といえば、「新しいこと」を始めるのに適した季節だというわれています。新しいチャレンジや生活など、楽しみな気持ちと新しいことに取り組む不安もあると思います。
私達の身体は何か取り組むとき必ずエネルギー、気力、体力が必要になります。
そこで、新しいことに向き合うために、日々の生活の中で欠かすことのできない〝食事〟について勉強し、食べることで身体へどういう影響がでるのか、西洋医学と東洋医学での、それぞれの概念について勉強しました。
西洋医学的には、私達が食事した際、口から入った食べ物は 口→食道→胃→小腸→大腸→肛門 という順ではいって、外で便として出て行きます。この過程の中で、体内に栄養素を取り込み、身体に必要な物資に再合成し、吸収されています。
では、東洋医学的にはどういう概念でしょうか?
東洋医学的に考えると、まず人体の構成や生命活動を維持するのに最も基本的な物資のことを〝精〟といいます。
この〝精〟には、父母から受け継いだ〝先天の精〟と飲食物を摂取することにより得られる〝後天の精〟の2つから成り立ちます。先天の精の量は生まれたときから決まっていますが、後天の精は飲食物を摂取することで絶えず補充されています。
次回は、後天の精について勉強したことを書いていきたいと思います。
—————————————————————
【参考文献】
「生理学 第3版 」東洋療法学校協会 編
「新版 東洋医学概論」東洋療法学校協会 編
五行大義(2)
曲直
洪範傳曰、木曰曲直者東方。
易云、地上之木爲觀。
言春時出地之木、無不曲直、花葉可觀。
如人威儀容貌也。
許愼云、地上之可觀者、莫過於木。
故相字目傍木也。
古之王者、登稿輿有鸞和之節、降車有佩玉之度、
田狩有三驅之制、飲餞有獻酢之禮。
無事不巡幸、無奪民時、以春農之始也。
無貧欲姦謀所以順木氣。
木氣順、則如其性、茂盛敷實、以爲民用。
直者中繩、曲者中鉤。
若人君失威儀、酖酒淫縦、重徭厚税、
田獵無度、則木失其性、春不滋長、不爲民用、橋梁不従其繩墨。
故曰木不曲直也。
洪範伝に曰く、木に曲直というは東方。
易にいう、地上の木を観となす。
言うこころは、春時、地に出づるの木は、曲直ならざるなし、花葉観るべし。
人の威儀容貌のごときなり。
許慎いう、地上の観るべき者は、気に過ぐるはなし。
故に相の字は、目、木の傍らにするなりと。
古の王者は、輿に登るに鸞和の節あり、車を降りるに佩玉の度あり、
田狩に三駆の制あり、飲餞に獻酢の礼あり。
事なきときは巡幸せず、民の時を奪ふなし。
春は農の始めなるを以てなり。
貪欲姦謀なきは、木気に順う所以なり。
木気順なれば、則ちその性のごとく、茂盛敷実し、以て民の用をなす。
直なる者は縄に中り、曲なる者は鉤に中る。
若し人君、威儀を失い、酒に酖りて淫縦し、徭を重くし税を厚くし、
田獵度なければ、則ち木は、その性を失い、春滋長せず、民の用をなさず。
橋梁は、その縄墨に従わず。
故に木に曲直せずというなり。
【引用文献】
『五行大義』著者:中村璋八、発行:明德出版社
とある山中にて。
こんにちは、稲垣です。
修行の一環で、とある山中にて作業をさせて頂いております。
感じる事は多々あるのですが、この春に感じた事を記したいと思います。
今年の節分は例年よりも一日早い2月2日でした。
つまり立春は2月3日。
その翌日に山中に入りましたが、都市部の寒さとは違う空気を感じました。
気温は寒いのですが、間違いなく”春”。
ビルよりも、木に囲まれた方が、
季節を正確に教えて頂いているように感じます。
その春ですが、
藤沢周平の作品に出てきそうな
東北武士の気概のような力強さを感じました。
”長い冬に積もった寒さを、苦難を跳ねのけて芽を出す力強さ”的な。
車のギアでいうと1速、2速とかそんなギア比でしょうか。
そんな空気を感じながら作業をしていると。
肝氣の力強さを思い、疏泄機能・条達機能とはこういう事なのかな?と感じたり。
弦脉とはこういう事なのかぁ?と感じたり。
色々な事の辻褄があう感覚を得る事が出来て楽しい時間を過ごせます。
極めて価値ある時間を頂いています。
一人で黙々と作業をする事が、
そんな楽しく思考出来るコツのように思いえますが、どうなのでしょう。
この場所だけに限らず、様々な山を楽しみたいと思います。
施術日記(05)
T.I 先生との治療練習5回目。
舌診での、軸を作りたいと考えて継続しております。
脉や腹診も含めて考察いたします。
舌診の鍛錬
【目的】
① 同經への刺鍼であるが、経穴を変更してみる。
② 舌の理解の為に、脉や腹診との共通項を考える。
問診にて「少々、お疲れ」との事。
この先生がダメージを体に受けている場合には、
舌の右への偏向がみられるようです。
ついでにいえば舌だけに限らず、
立ち居振る舞いにも、ある動きにも特徴が出てきます。
また、脈診においても右腕の脈に特徴を診ました。
舌尖の赤みはあるにせよ、舌辺の赤い斑点はかなり少なくなっています。
ただ、歯痕の凸凹が強く感じられました。
(左)地機:0番鍼にて置鍼(5分)
今回は(04)回までの経穴ではなく、別の経穴を試しました。
切経において、昔の教科書の取穴と現在の教科書の取穴の違いを
議論しながらの刺鍼となりました。
右脚と左脚の経穴を診た感じ、左の地機の方がウブな感じを受けたので、
刺鍼を試します。
舌の出し方が穏やかになり、正中線上に近くなりました。
歯痕も少なくなっております。
今回、特徴的だったのは写真では表現できていないかもしれませんが、
舌に溢れんばかりの潤いが出てきました。
おおよそ、水が引く事のイメージをもっていたので、少し驚いております。
腹診においては前回の治療(04)回と同じように
刺鍼後になってから、脾募へ特徴的な何かを感じました。
ミルフィーユのように階層があるようにも思え、
何かをどかしたら、何かが見えるようになった。のでしょうか。。
今後も経過を見てみたいと思います。
方剤学(02)
ニンニクを多めに食しました。
私自身の二便について変化がありましたので、備忘録として。
疲労回復や滋養強壮などをイメージするニンニクですが、主に作用する臓腑や経絡が『胃』や『大腸』との事で調べてみました。
『中医臨床のための中薬学』においては分類として”駆虫薬”の章に配置されております。
大蒜(蒜頭、葫)
ニンニクは生薬名として、大蒜(たいさん)、蒜頭(さんとう)、葫(こ)等という。
〈性味〉
辛、温。小毒。
〈帰経〉
胃・大腸。
〈効能と応用〉
1:殺虫
鈎虫、蟯虫に対して用いる。
2:止痢
細菌性下痢に、単味を服用
3:止咳
肺結核(肺瘻)の咳嗽、百日咳(頓咳)などに用いる。
4:治瘧
瘧疾に用いる。
5:解毒消腫
皮膚化膿症の初期に用いる。
肺疾患や皮膚疾患にも応用があるところが、興味深く思います。
肺の”水の上源”、胃の”喜湿悪燥”など一定の水分量を共通にするところが気になるところです。
【参考文献】
『中医臨床のための中薬学』東洋学術出版社
『大漢和辭典』大修館書店
(葫:第九巻802頁)
『新版 東洋医学概論』医道の日本社
朗読、会話
朗読
最近人に合わせるって難しいなと痛感しています。
合わせにいったらより合わなくなる感じがします。
正直どうしようかと悩み中なのですが、何かしらやっていかないと変わらないので色々試していっています。
最近試し始めた事が人の朗読しているところの真似です。
心から入れれば一番いいのでしょうけど、できていないのでまずは形から入ろうと思ってYouTubeなどで人が行なっている朗読を真似してみています。
人との会話中に全く同じ事をしていたら違和感が生まれそうですが、相手と同じ事をする必要があるので少しは相手の理解に繋がる気がします。
また、長い文章になると腹から声が出ていないと読みきる事ができないので伝わりやすい声を出さなければいけなかったり、瞬発的に言葉を出す訓練にもなります。
会話
ストレスなく一緒に過ごせる人は波長が合って自然に過ごせる。
家族でも体調不良を起こすと様子が違ってくるので違和感から色々察知しやすいと言った話をよく聞く。
違和感を察知できるのは、同じ空気感をもった人の違和感だと思う。
鍼灸院には若者からお年寄りまで幅広い年齢の方が来るし、色んな個性を持っている。
そういった相手を理解しようと思えば尊重しなければ話は始まらない。
綺麗なものばかりに囲まれているとそう言った人にしか対応できなくなるし、逆もそうなる。
本当に会話上手な人は違和感を感じない。
きっと一致してるんだと思う。
ネガティブなもの
会話の中でネガティブなものが出てくるとそれに同意してはいけない。
もっていかれる。
ただ真っ向から否定するとそれもまた問題なので違和感を感じさせずにかわす必要がある。
告知!第7回 鍼灸学生の為の勉強会
【参加資格】
・鍼灸学生
・本年4月からの新卒鍼灸師
・これからこの業界を目指す方
(※免許を取得し鍼灸師になった方は今回はご遠慮頂いております。)
【日時】
2018/3/18(日) 15時〜17時頃
【内容】
参加者の意向に沿った内容を設定
【場所】
一鍼堂 二階
【費用】
一人3,000円
【募集人数】
一鍼堂内部で患者さんのいない時間に行います。
目のみえる範囲でやりますので、
一定の人数制限を行います。
————————–
今年もやります!
第7回の未来の鍼灸師のための勉強会です。
1・2年生の鍼灸学生さんは
学生生活にも慣れ、
将来自分が進むべき道というのが
少し見えて来たかも知れません。
また新に鍼灸学生さんになる方は
夢を大きく持ってこの業界に進もうと
思っておられると思います。
そして国家試験が終わった
3年生の皆さんはここからが本番であり、
希望とともに不安も多いかと思います。
そんな皆さんの為に、
また勉強会を開催することとなりました。
日々臨床で苦悩、喜びを感じている
鍼灸師に聞きたいことがあれば
どんどん聞いて下さい!
今回も相手の呼吸がきちんと感じられる
少人数での講座とします。
一定数に達した場合は
定員とさせていただきますので、
ご容赦下さいませ。
また皆さんから、
こういうことをやって欲しいという
お題も受け付けますので、
仰って下さい。
エントリーはこちら
↓ ↓ ↓
学生向け討論会フォーム
Facebookでの告知ページはこちら。
コメントを残して頂く事も可能です。
https://www.facebook.com/events/1749825538389987/
一鍼堂
異名同穴④
腧穴(しゅけつ)とは、いわゆる「つぼ」と呼ばれるものの総称である。
腧穴には、十四経脉上(正経十二經脉・督脈・任脈)にある「經穴(正穴)」、経脉に所属せず治療効果から発生し名称と部位が定まっている「奇穴」、奇穴の中でも1901年以降になってから定められた「新穴」、押すと心地がよかったり、圧痛を感じたりするが、名称も部位も定まっていない「阿是穴(天応穴、圧痛点)」などが含まれる。
經穴(正穴) : 十四經脉上にあり名称、部位が定まっている。
奇穴 : 十四經脉上になく名称、部位、主治症が定まっている。
(新穴 : 1901年以降に定められた奇穴)
阿是穴(天応穴、圧痛点): 名称や部位は定められていないが、病態と深く関わって出現したり、治療点となる部位がある。
④4つの異名のあるもの
穴名 異名
陰交穴 : 少関穴、横戸穴、丹田穴、小関穴
陰都穴 : 食呂穴、食宮穴、石宮穴、通関穴
横骨穴 : 下極穴、屈骨穴、曲骨穴、下横穴
客主人穴 : 上関穴、客主人穴、客王穴、太陽穴
曲地穴 : 鬼臣穴、陽沢穴、鬼臣穴、鬼腿穴
頬車穴 : 機関穴、鬼牀穴、曲牙穴、鬼林穴
曲骨穴 : 尿胞穴、屈骨穴、曲骨端穴、回骨穴
三陰交穴 : 承命穴、太陰穴、下三里穴、女三里穴
心兪穴 : 背竅穴、俉焦の間穴、心の兪穴、背兪穴
上脘穴 : 上管穴、上紀穴、胃脘穴、胃管穴
衝陽穴 : 会原穴、趺陽穴、会湧穴、会骨穴
神門穴 : 兌衝穴、中郄穴、鋭中穴、兌骨穴
身柱穴 : 知利気穴、散気穴、塵気穴、知利毛穴
臑会穴 : 顴髎穴、臑交穴、臑輸穴、臑兪穴
太谿穴 : 昌細穴、照海穴、陰蹻穴、大系穴
中府穴 : 膺中兪穴、肺募穴、府中兪穴、膺兪穴
中極穴 : 気原穴、玉泉穴、膀胱募穴、気魚穴
瞳子髎穴 : 太陽穴、前関穴、後曲穴、童子髎穴
命門穴 : 属累穴、竹杖穴、石門穴、精宮穴
腹結結 : 腹屈穴、腸結穴、腸屈穴、陽屈穴
陽関穴 : 関陽穴、寒府穴、陽陵穴、関陵穴
湧泉穴 : 地衢穴、地衝穴、蹶心蹶、涌泉穴
労宮穴 : 五里穴、鬼路穴、掌中穴、鬼窟穴
【参考文献】
『新版 経絡経穴概論』医道の日本社
『鍼灸医学事典』医道の日本社