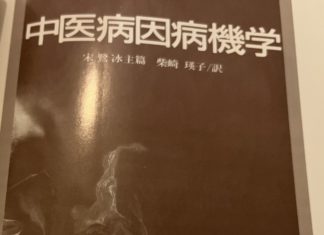素問 陰陽応象大論篇(第5)から
<学生向け 近日開催予定のイベント>
【学生向け勉強会のお知らせ】東洋医学概論をモノにしよう!
→(随時お問い合わせ受付中です!)
【学生向け勉強会】「素問を読もう!」申込み受付中です
→毎週火曜19時〜 または 毎週木曜13時〜(途中からの参加も可能です。)
こんにちは、大原です。
素問の勉強会では、現在
陰陽応象大論篇(第五)の内容を読み解いていっております。
さて、素問 陰陽応象大論篇(第五)の中に、
気(人体を動かす力)、
形(肉体)、
味(飲食物)、
精(生命活動を維持する源泉)
それぞれの相互転化についての記述があります。
その原文と読み下しは以下になります。
【原文と読み下し】
・・・
水為陰、火為陽。(水は陰となし、火は陽となす。)
陽為氣、陰為味。(陽は気となし、陰は味となす。)
味帰形、形帰氣、氣帰精、精帰化。(味は形に帰し、形は気に帰し、気は精に帰し、精は化に帰す。)
精食氣、形食味、化生精、氣生形。(精は気に食(やしな)われ、形は味に食(やしな)われ、化は生を生じ、気は形を生ず。)
味傷形、氣傷精。(味は形を傷り、気は精を傷る。)
精化為氣、氣傷於味。(精は化して気となし、気は味に傷らる。)
・・・
原文三行目から、
体内での転化について述べられていますが、
どのように起こっているのかを原文通り順番に読んでいくと、
一見このようになります。
味帰形、 「味(飲食物)」→「形(肉体)」
形帰氣、 「形(肉体)」→「気(人体を動かす力)」
氣帰精、 「気(人体を動かす力)」→「精(生命活動を維持する源泉)」
精帰化。 「精(生命活動を維持する源泉)」→「化(必要な気血などを他の物質から変化させる作用)」
さらに4行目以降も転化についてですが、
精食氣、 「気」→「精」 (「精」は「気」によって食(養)われる、という意味から)
形食味、 「味」→「形」 (「形」は「味」によって食(養)われる、という意味から)
化生精、 「化」→「精」
氣生形。 「気」→「形」
となります。
矢印は、物質などの生成の向きを示していますが、
「形」は「気」を生成したり(原文3行目)、「気」は「形」を生成したり(原文4行目)、
また「精」は、「化」を生み出し(原文3行目)、反対に「化」から生成される(原文4行目)とあり、
チャート図のように読んでしまうと、
混乱してしまう印象を受けませんでしょうか?
ですが、ここでのポイントは、
これらの相互の関連は
その調和が保たれているということが重要だということだと思います。
「気」→「精」などのようにそれぞれ別個で抜き出すのではなく、
これらをまとめて、
「味」→「形」⇄「気」→「精」⇄「化」
のように表してみると、「気」について、
例えば次のように意訳できると思います。
「飲食物を得た肉体からは「気」が生じ、
その「気」が充実していると生命活動の源泉である「精」も充実してくる。
その「精」が充実してくると、飲食物から体内に必要な気血を化する作用を生みだす。」
このように、単に、肉体から「気」が生じるというのではなく、
飲食物を得て充実した肉体から「気」が生じるという、
一連の流れが重要なのだと思います。
同様に、単に「気」から「精」が生みだされるというのではなく、
飲食物を得て充実した肉体によって気が生みだされ、
(肉体や気が充実するためには飲食物もしっかりしたものが必要だと思いますが)
その「気」が充実してくると「精」が生みだされるということだと思います。
一連の流れが重要だということだと思います。
以下に、参考までに、上の原文の意訳を記します。
【意訳】
水は陰であり、火は陽である。
火である陽は、人体においては気であり、
水である陰は、飲食物(味)である。
飲食物によって肉体(形)は形成され、
飲食物を得た肉体からは気が生じる。
その気が充実していると、生命活動の源泉である精も充実してくる。
その精が充実してくると、体内に必要な気血に化する作用を生みだす。
すなわち、精を作り出すには気を消費し、
肉体は飲食物を得ることで成り立っているのである。
また、化する作用によって精は生まれ、
気によって肉体ができるともいえる。
しかしながら、これらの相互関連は、その調和が保たれている場合にうまくいくのであり、
飲食の不摂生・偏った飲食があると、その飲食によって肉体はかえって損傷され、
肉体が損傷するので気も弱り、気から充実するはずの精も傷られることになる。
まとめると、正しい飲食からは肉体や気が充実し、さらに精をも生み、
精が充実していくると気も充実してくる。
反対に飲食の不摂生や偏った飲食は肉体や気が弱り、
精を作り出すこともできなくなるということである。
すなわち気は精をよりどころとしているので、飲食の不摂生によって障害されるのである。
【用語集】肝腎陰虚
肝腎陰虚
これらを解釈する際、
肝と腎の関係性が重要となる。
腎精の不足や、腎陰が欠損すると、
肝にも波及し、肝陰や肝血の不足へつながる。
その逆もしかりである。
肝血は腎精から化し、腎精は肝血によって補うというように、
相互に助け合っている。
この関係が崩れることで、肝腎の陰虚を呈する。
さらに、
肝腎の陰分が不足する事で肝の陽気を制御出来なくなる
「肝陽上亢」の状態へと発展することもある。
また、
肝腎ともに「相火」を統括するが、
肝腎の陰分が不足すれば、
相火を制御出来ず、火の勢いは強くなり、
熱傾向が顕著となる。
参考文献:
『黄帝内経素問』
『黄帝内経霊枢』
『中医基本用語辞典』 東洋学術出版社
『基礎中医学』 神戸中医学研究会
『中国医学辞典』 たにぐち書店
『臓腑経絡学』 アルテミシア
『鍼灸医学事典』 医道の日本社
施術日記(04)
T.I 先生との治療練習4回目です。
同じ経脈上に刺鍼する事で、軸を作りたいと考えております。
舌診の鍛錬
【目的】
① 同經への刺鍼にて、短期的・中期的・長期的な観察。
② 四診も含め、複合で考察。
舌を出した瞬間に思ったのは『紅くなった?』
いつもより、白っぽさが減って
このシリーズが始まって以来、刺鍼前の舌の表情では目立った違い。
舌の出し方も、リラックスが感じられます。
舌尖・舌辺の感じは前回と同じ様子ではあるが、雰囲気が違う。
陰陵泉(右):0番鍼にて置鍼(5分)
全体的に水分量の調整は出来たと感じ、
所々に赤みが見て取れるも、
一皮剥けて、深層が顔を出しているようにも感じる。
舌の出し方も、締まりを感じる。
これは変な緊張が高まったというよりも、
適正な気力をもって来てるように思える。
舌の中央当たりも、渇きが出てきてる。
もしかしたら、苔を取るのはこの渇きを持たせる事で、
剥離させて行くのでは??と妄想する。
腹診も刺鍼前後に変化は感じられ、
中脘あたりの変化が興味深い。
どこに核?
体のどこで受けるか。
昔何気なく、不意に先生から物を投げてどの様な受け取り方をされるか見られた事がありました。
その時の感覚とリンクするものがある。
そうなんだよな、自分は受け手なんだよなと再認識。
その感覚を掴めたら歩行、しゃがむ動き、足を踏む感覚など日常生活で訓練できる事なんていくらでもあって、その感覚をもったまま色々試す。
掴んだ瞬間はどこまでもいける感覚がある。
これも道なのか?
本当に気の合う人と接していてもある種の似た感覚に陥る事がある。
身体操作に限らない話だと思います。
老子「載營魄一、能無離乎。専氣致柔、能嬰児乎。…」
老子は読んでると色んな事を書いてる。
でも意外と内容は共通していて多くはなく、感覚を掴めるのか、継続できるのかと言ったところに一つの価値があると思う。
楽しんでいこう。
治療と勉強の狭間
◯ 治療の合間に勉強させてもらう
寺子屋で勉強会を開きました。
お互いの主訴から治療まで一連の流れを再現してみました。
「練習相手」と思うから、ダラダラやる。
寺子屋で患者さんの問診から切経を
「5分以内に終わらせるように」
と下野先生に何度指導いただいているのに、
守らず切経を終えて帰ってくる。
やはり『甘え』みたいなものがあったと思います。患者さんも不快に思いますね。
ストップウォッチで測りながらどこに時間がかかっているのか、寺子屋生にも客観的にも見てもらいました。
更に寺子屋生の施術を受けることで
モデル患者さんの治療をしている時の
自分を重ね合わせて、俯瞰して見ることができます。
無意識にやっていることを
改めて意識して修正し、
修正したものをブラッシュアップさせながら、
最終的には無意識でできるようになりたいです。
また、お互いの施術でたまたま選穴が同じだったのですが、気を付けなけれざならないと先生が仰ってた場所だけど、(なぜそうなのかわかっていない)悪い方向に向いた時、体験を共有することができました。
◯“治療の流れ”を意識しすること
私は舌→カルテ→脈→カルテ→お腹…と
診て書いての間に流れが途切れてしまいます。
空間やリズムに何か歪みなようなものが出て違和感が出ます。
それは患者さんも感じていることと思います。
書く、聞く、話すことに気を取られてしまうので、流れを止めないために鍼の袋を捨てる動作ひとつにしても色々と引き算していこうと思います。
舌診(03)
受付のKさんに舌の研究の為にご協力頂きました。
飲食物の影響による舌苔が染まる、
いわゆる”染苔”をさける為に、わざわざ調整していただきました。
表
裏
舌質
舌神:有神
舌色:淡白舌
舌形:嫰・胖大・歯痕・点刺
舌苔
苔色:白苔
苔質:全苔・薄苔
冬休みに入りました!
こんにちは高山です。
冬休みに入りました。
今は東洋医学の病因と病機について勉強しています。
聞いたこともない物質や構造を学び、そこからさらに深掘りしていく、理解するのがむずかしいことが書いてあったり、量も多いです
でも、病気がなぜ起こってしまったか、やその病気の症候などが記されていて、治療する上で、きっと大切になることが、書かれています。ちょうど冬休みですし、じっくり時間をかけて勉強しています。
まだ僕は一年生で、脈診や舌の色、腹診などの仕方や、
感触は全然知りませんが、いずれ学ぶ時が来ると思いますので、今はまだ机上の知識ですが、どんどん吸収していきたいと思います。
患者さんをしっかりと治療できて、喜ばれる日を夢見て日々前に進み続けます。
施術日記(03)
T.I 先生との治療練習3回目です。
週ごとに、同じ経脈上に刺鍼する事で変化をとります。
舌診の鍛錬
【目的】
① 一週間前と同穴にて、鍼の番号を変えて違いを診る。
② このシリーズは今回で3回目。
鍼の ”前後” という短期的にできる変化とは違う、中期的な変化を探す。
舌の中央の苔・裂紋には長い歴史を感じるので、
この変化を狙うのは、
長期的に考えなくてはならないのかもしれません。
舌尖と舌辺の赤みは、ぼんやりといつものようにある。
舌の出し方に、強張った感じはみられない。
陰陵泉(右):0番鍼にて置鍼(5分)
一段と力が抜けたように感じる。
刺鍼後には舌尖と舌辺の赤みは、淡く穏やかになるのはいつもの通り。
舌の水分量の違いが、事前事後で間違いなく変化する。
2週間前は・・
この2週間前に舌診した際、
舌の出し方が右へ傾いていたのが特徴的でした。
舌尖の尖がり具合や舌の周辺の赤みは現在もありますが、
現在は少しマイルドになっているように感じます。
ご自身で治療をされているのもあり、
このシリーズでの正確なエビデンスという訳ではありませんが、
変化は感じられます。
穴の名前、実技での体験など
テスト前で暗記の時期に入りました。
経穴丸暗記は面白くないので、少しですが付随する情報を書いて認識を深めたいと思います。
腎経
①湧泉 (井木穴、子穴だが腎なので瀉法厳禁)、回陽九鍼穴 足背、足屈曲時、足底の最陥凹部
まんが経穴入門P184 由来「足の少陰腎経の木穴に属し、腎経の脈気が湧き出る」
五兪穴では(井・滎・輸・経・穴)があり、陽経には原が加わる。
霊枢:九鍼十二原では気血の巡りを自然界の水の流れで例えた。
井穴は水源。
②然谷 (滎火穴) 足内側、舟状骨粗面の下方、赤白肉際
まんが経穴入門P184 由来「別名、※龍淵 火が深いところで燃え盛り、水の相剋を受け付けない」
※考察 龍の火のイメージが符合しているのか。
③太谿(原穴、兪土穴) 足関節後内側、内果尖とアキレス腱の間の陥凹部
まんが経穴入門P185 由来「内踝の真後ろの深い陥凹部にあるため、湧泉から出て然谷を通った腎水の流れがここで一つにまとまる」
診断でも使える穴な事がよく分かります。
気になること
最近絡穴が気になっています。
豊隆の調べ物をしている時になぜ豊隆は化痰作用があるのか。
それは絡穴で脾と連絡しているからだという内容に触れたので、穴性を学ぶ時もこういう事も意識していきたいと思います。
実技で
実技の授業である穴に置鍼5分くらいされた。
その時恐らく肝がやられて季肋部あたりが痛み始めた。
この時に何で左何だろうと不思議になった。
理論的には
中薬の配合 P 78
「左右者、陰陽之道路也」とあるように、肝気は左から上昇することで、木気は行き渡り(条達)、肺気が右から下降することで、金気は正常に運行(粛降)します。
とありました。
五行でも左に属するのでその辺もあるのでしょうか。
逆に肝気虚と呼ばれる状態にこの治療をしたらどうなるのか。
気になりました。
本では存在している肝気虚も、実際は肝は剛臓なので中々ないとは思いますが…
プライベート
先週から1ヶ月間だけ兵庫県に住むことになりました。
引っ越し中々大変でしたがやっと落ち着いてきました。
テストが終わったら武庫川にでもゆっくり散歩に行こうと思います。
気持ちの面
後期試験が終われば2回生になります。
色々自分に対して思うことがありますが、極力無心でやれることを黙々とやりたいと思います。
参考資料
まんが経穴入門 周春才編著 土屋憲明訳 医道の日本社
中薬の配合 丁光迪編著 小金井信宏訳 東洋学術出版社
脾胃湿熱の「湿熱」について
東洋医学概論の教科書にあった脾胃湿熱でしたが、湿熱とは
食べ過ぎ・飲みすぎが原因で体内に入ったままになっている「水」が
熱の影響で湿気?のようになっているものなのか?
ヒントを探して中医弁証学を読んでみましたが、今日はハテナが多いです。
湿は重濁性と粘滞性をもっていて、湿邪による病は長引きやすく、進行が緩慢
粘滞性があるために長引きやすいような感じがしますが、
病の進行が緩慢というのはいいことなんでしょうか?
それともわかりにくい?ということなのでしょうか。。
気機を阻滞させやすく清陽(?)に影響しやすい。
湿気の多い環境や居住地の場合、湿邪は外から皮毛に入る。
また、脾胃虚弱や水分の取りすぎ、過食などは湿の内生をまねく。
湿の病は内外の湿が合わさって発生することが多い。
私自身が雨の多い土地で生まれましたが、どれくらいの期間その環境で過ごすか、というのも関係があるのでしょうか。
(それによって湿邪に対して耐性ができるみたいなことはあるのか?そもそも邪に対して耐性ってなんだろう…)
(大阪は日本の中でも湿度が高い土地柄から、梅雨の時期になると湿邪による症状が起きやすい、と授業の時に聞いたことがあり、根拠を調べてみましたが思うような答えは出てきませんでした…)