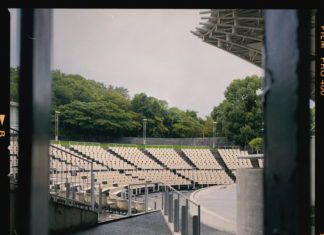先々週の施術で
水分穴の少し右だったように思う。(今も反応あり)
刺入深度は1ミリか2ミリか。
置鍼開始して少しして、
息がうまく吸えていないことに気づく。
吐くことはできている。
入ってこない、がそのことに特に不安はない。
数分して抜鍼の後、それまでの状態をはずみに
誘いこまれるようにからだにもたらされた深い呼吸と何か。
横隔膜の動きが抑制されていたのか。
これも穴性のひとつにあたるのか。
他の方においても似た作用をもたらすのか。
親友と
友人に体を診せて貰った。
ベロ見せてといってベロは出せるけど
裏見せてと言って裏返せない。
こうできる?とやって見せて、
それでもできないみたい。
無意識にか指をベロの下に入れて裏を見せてくれようとしている。
モゾモゾと動くだけで、やはりできない。
人のそんな様子を目の当たりにした。
激しく上気していて、喋り始めるともうとまらない彼に
少しでも落ち着いてもらえるように鍼をさせてもらった。
同情
数週間ぶりに診せてもらって
復調した患者さんの姿に、
前回は浮き沈みする揺れる姿に
一喜一憂していたことに
はっきりと気付かされる。
同情はしないー
以前教わっていたことが指していることが
少し分かった気がした。
目線
目の前の現象に簡単に目が眩むのは、問診で聞きとった患者の言葉に一喜一憂するのと同じで目線に確固たる軸がないためだと知る。患者の先週と異なって冷え切った(そう表現してしまうことも含まれる)腹部に触れて、捉えやすい冷えの情報の向こうに別の情報を察知できずにいる。同じ腹部を診た先輩がまったく別の点で着目、記したカルテを見てまた気づかされる。
鍼治療を受けて⑤
刺激というとき、まず物理的な接触(による操作)を想起する。
力、力量、力の方向を連想する。
学校の授業で取り扱われたのは専らこちらで
刺激量の調節が大事とされた。(自分は学生時代にはそう解釈していました)
もし自分が誰かに腕を掴まれたのなら、
もっと大きな力を出せればそれを振り払うことをする様に
加えられた力には一定の抵抗が生まれるはずで、
痛くないように打鍼する技術は教わりながら
学生時代に感じていた違和感は、
ニュアンスがこれに近いのかも知れない。
でも実際は治療を受けているからだのうえに起こるのは、
ほんの些細な“刺激“でそれまで経験しない、想定していない反応が始まる。
ぜんぶ内側で起こっていて、自分の一番静かなところ
から大胆に動かされる様な感覚。
定期的に治療を受けていても、
今日どんなふうに展開するのか分からない(のでドキドキする)
(疑問も募る。これだけのエネルギーは普段いつどこで発露しているのか)
ツボの存在について、ひとつ新しい気持ちで検討できそうな気がします。
開業いたします。
こんにちは稲垣です。
私が鍼灸学生の時も、国家資格を得てからも
同じ質問を受けた事がありました。
「なぜ一鍼堂なのですか?」
です。
学生向けの勉強会を
一鍼堂で開催する準備をしておりましたので、
その際に、未来の鍼灸師さんたちに向けて話そうと
思っていたのですが、
このご時世で学生さんたちに集まって頂く機会が
なかなか持てませんので、
お伝えしておこうと思います。
(パソコンの画面を通じてのテレビ電話では
臨場感がありませんので、
実際に集まって頂く事を待ち望んでいたのですが、
非常に残念です。)
私は鍼灸学生の一年生の時より
林院長にお世話になりました。
各種勉強会など、様々に参加させて頂き、
大切な価値観を沢山頂戴しました。
学生の頃からの四年間ですから、それはそれは数知れず。
院長の治療を受けさせて頂き、
最初に感じたものは、“テコ”です。
“重い岩”を退けるには支点をおいて、
長い棒のようなもので力点に力を加え
岩という作用点に力を伝える。
そしてゴロンと動かせる。
なるほど!
臓腑へアクセスさせるには、こうするのか!
と鍼治療を体験させて頂きました。
同時に、
このテコよりもっと良い方法はないのか?
支点を岩に近づけたらどうだろう?
力点をより遠くに伸ばしたらどうだろう?
”より良い方法を探し続ける好奇心”を教えられました。
学問に対しての「もっと!もっと!」
というエネルギーを感じ、
同じ場所を掘り続ける魅力を院長より感じました。
私はそんな環境が心地よく思い
一鍼堂に通い続けたのだと思います。
「なぜ一鍼堂なのですか?」
という問いの答えとしては
「探究し続ける楽しさを感じたから。」
となるのでしょうか。
”面白さを教えて頂いた”
これは、私にとっては極めて重要です。
そして、
(話が急に展開して申し訳ありませんが、、)
開業いたします。
その”面白さ”を人生の楽しみにして行きたいと思います。
“修行を完了させて一流のはり師になったから店を持つ”
というのとは全く異なりますが
鍼灸道の修行の為に、
自身の鍼灸院を持つ事といたしました。
ベッドが一つだけの小さな所ですが
臨床の場として、
研究の場として
励んでまいります。
面倒を見て頂いた院長の気持ちを察するに
痛恨を感じるのと、院長が長期的に考えて
準備されていたもろもろを考えると
心苦しいだけではありません。
罵倒の裏にある優しさを感じるだけに
申し訳ない気持ちなど多々あり、
私自身の心中が穏やかではありませんが
怨まぬ為に、
嫌いにならぬ為に、
少し間合いをとることとしました。
身を切り分けて、与え続ける院長のアンパンマン力を感じて
お返しをしなければと、学校を卒業した際に思い続けて
現在まで至っておりますが、必ずお返ししていきたいと思います。
いつになる事やら…
小さな小さな鍼灸院を行っていきますが
温かく見守って頂けるとありがたく思います。
お世話になった皆様に本当に感謝しかありません。
ありがとうございました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
令和3年6月
稲垣 英伸
硬さ 柔らかさ
診察で
各所の情報が、そもそも検討するのに足る量を拾うことができていない 尺度がない
その中で観察した情報をすぐに解釈しようとして、できない(できるはずがない)
切診において相手のからだのいづれか部位に接している時に
触れているその部分だけを見て
情報を取りにいく意識が自分の体も思考も硬くしていることに
先輩のされる様子を見て気付かされる
鍼治療を受ける中で気付かされた
自分が力んでいたことを本当に知るのは体の力が抜けたときだった
能動的に取り組むことと硬さはイコールでないのに
そうさせているものは何か
(覚え書きとして)
治療問診の中で
数年前よりずっと体が重い
と訴えられる方
先週の治療から当日までの調子を尋ねたときに
前回の治療のあと帰りから軽い「けど」まだしんどい。
他の点でも状態は良い「けど」まだ悪い、という矛盾表現が印象的だった
脈診がよく分からない自分にも治療前の左右のバラつきが治療後に
整うのがはっきりと分かる、お腹の全体のおさまりが良くなったと感じられる
数回目の治療で体にそれまでに見えなかった調子が現れていることが感じられる
今週のコンディションは良い状態にあることに違いはないが、
そのことを受け入れる準備が整っていない
それは葛藤の様なものとして映った
治療的にはどんな意味を持つものになるのか
衛気と発汗
専門学校で使った教科書では衛気に関する項で、その作用として「外邪の侵襲を防ぐ他、皮毛を潤沢に保ち、肌肉声 •皮毛 •臓腑などを温め、腠理の開闔(皮膚の収縮と弛緩)により発汗を調整し、体温を一定に保つ働きがある」と説明する。
(そもそも異なる分野の言葉を同じく取り扱うことが間違っているのかも知れないが)生理学の教科書では、発汗に関する基礎として発汗を温熱性発汗と精神性発汗とに大別している。教科書レベルの説明であったとしてもこの括り方に誤りはないはずですが、寝汗や自汗の説明に使えないと考えます。
同じく生理学の蒸発の項で体表面からの蒸発が不感蒸散と発汗によってなされることを教わります。一般的には、呼吸の際に呼気に含まれる水分、皮膚や気道の粘膜から蒸発する水分を合わせたものを指すようですが、衛気が主るところの水分の排出はどちらかというとこの不感蒸散の方を当てはめる方がしっくりくる気がします。はっきり「発汗」と書いている以上、それは学校で習った様に衛気と汗腺の働きを結ぶのが正解なのかも知れませんが、分からない、まま保留としたいと思います。
体表観察で拾う情報に湿り気や冷たさがあるが、それが体に備わる発汗の機構の顕れである場合ととそうでない他の理由による場合とを区別しておく必要がある、体表が冷たいことが体が冷えを表すわけではないことを再認識する機会になりました。
______________________________________________________
【参考文献】
新版 東洋医学概論/医道の日本社
生理学 第3版/医歯薬出版株式会社
鍼治療を受けて④
浮力が働いている様な感じと表現できるかもしれない
いつもの様に
置鍼中に一瞬眠った様な状態になったあと
ふと自分の体の感覚に戻るともうすっかり動いている動き回っている
体は動かしていないけど体が動いている
水のない風呂
今日そう感じたのは足の輪郭がぼわぼわと波たっており暖かく
温かい湯船に浸かっている時と似ているからかも知れない
ゆっくり静かに観じていられる体はベッドのうえで浮力が働いている様にやさしい
こうして完全に身を預ける時間を通して
反対に普段一体どれだけ抵抗を抱えて過ごしているのかについて思わされる
(忘備録として)