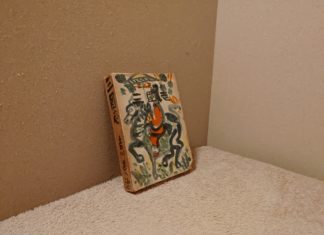おばあちゃん(95歳)と鍼 ②
先日、祖母に会いに行ったことをきっかけに、
拘縮や認知症について知識が乏しいと痛感しました。
学校に行き仲良しの司書さんに相談しました。
「私も介護をしていて、
認知症や介護の本をたくさん揃えたのよ!
でも中々見てくれる人が少ないんよ」
と話してました。
1時間ほど司書さんと本を吟味して
拘縮ケアや認知症の行動心理学の本を
借りました。
拘縮を防ぐタオルの位置や
介護時の声の掛け方など
とても参考になりました。
今日祖母に会いに行ってきました。
午前中、按摩師さんに施術をしてもらっていました。
日によって差がありますが、
顔色も良く、傾眠もほとんどありませんでした。
眉間の皺がないことに一安心。
それでも、腕はきつく抱きしめたて
膝頭が隙間のないくらいひっついていました。
硬い手すりに腕が食い込んでいました。
「もうあきませんわ…」と祖母は弱気でした。
「ほな、鍼しましょうか」と言うと
昔鍼治療によく通っていた祖母は軽く頷きました。
車椅子に乗ったまま4箇所に鍼をしました。
足を2箇所した後、体を前屈できるようになり、
前回できなかった背中にも鍼をすることができました。
1mmも刺していませんが、
動きが予測できないので置鍼は少しヒヤヒヤしますね。
てい鍼があれば安心かもしれません。
背もたれに当たらないようにタオルを挟み
前屈姿勢を介助してもらいながらの置鍼でした。
5分ほどの置鍼した後、脇に隙間ができて
握り締めていた指が徐々に解けてきました。
痛がる場合があるので、
声かけしながら指を動かしていきます。
拘縮した手の中は汗ばみ
菌が繁殖するのでとても臭いです。
爪が食い込み、それだけでも痛いだろなと。
看護師さんに握り締めた指の解き方を教わり、
鷲手のようになった隙に爪切りをしました。
腕を膝上に降ろせるようになったので、
袖をめくって脈を見ようとしました。
拘縮の姿勢でクロスして両腕が当たっていた部分は内出血していて、加わる力の強さに驚きました。
タオルを摘んだり、コップを持ったり
自分の意思で動かせるから祖母はご機嫌そうでした。
祖母は孫のことをわかっているのかな。
私の名前を言うとニコリと笑って頷きました。
私が今日全身真っ白の出立ちだったので、
時たま「先生、ここが痛いんですわ」
話してくれました。
「指があかんようになってあきませんわ」
「お団子が食べたいですわ」
「ありがとうさん」
今日は傾眠することなく、
話はチグハグだけど、ゆっくりゆっくり
色んなことを話してくれました。
「本人が言いたいこと、伝えたいことを話せるようにしてあげたらいいんですよ」
と祖母のことを相談した時に
お爺さんに治療された経験談を交えて
下野先生がお話してくれました。
鍼で延命、なんていうことは考えていません。
残された時間を祖母が穏やかに
過ごせればと思います。
鍼をする前。
腕は拘縮し、体が傾き肘置きに腕が食い込む。
昔よく握手をしていたので、
「握手して」というと手を差し出してくれました。
上腕は動かない。
足の鍼施術後、腕が解けて軽度の前屈が可能に。
背中と肘に空間ができたのでタオルを入れて
姿勢を安定させる。
背中に5分置鍼、腰は鍼が無理なので軽擦。
車椅子のステップから足を降ろしたり、
自分の意思で少し動かせるように。
脇に空間ができて、
肘置きに腕を置けるように。
動かす時は、方向や位置を
知らせた後に動かしています。
タオルを摘んで畳む動作をする。
テレビにおける鍼特集の直近の予定、と個人的な感想。
2018年12月31日 9時~13時 『YOUは何しに日本へ?』の再放送にて、YNSA(山元式新頭鍼療法)の紹介。
https://juku.teppennohari.info/post-7160/
以下、東京大学付属病院に勤務しておられる、粕谷大智先生の公開Facebookページより。
2019年1月4日、NHKあさイチにて、鍼の特集あり。
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128705171477506&id=100030140710901
1月23日および2月13日、NHKためしてガッテンにて、鍼の特集あり。
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122722288742461&id=100030140710901
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128705171477506&id=100030140710901
また、上記文章から、詳細は不明ながらも、2018年にNHKであった「東洋医学 ホントのチカラ」の続編も企画中?らしい?
……
僕、個人的には、正直、怖くなってきました。
2019年以降における、日本の鍼灸および東洋医学の扱われ方、受け止められ方に。
特に、NHKで鍼灸の特集なんて、長年の鍼灸患者からしたら、驚天動地の出来事です。
国が、公共放送を使って、鍼灸をプロパガンダしている……
それは日本医師会も黙認している……
と個人的に受け止めてます。
国の予算が100兆円を越え、医療費が42.2兆円と、常軌を逸した予算配分になっており、
厚生労働省「平成29年度 医療費の動向」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177609.html
また、柔道整復師の保険請求も、去年9月から非常に厳しくなり、整骨院・接骨院のハシゴ受診が非常に煩雑になったり。
(事実上のハシゴ受診不能。)
ほぼ同時期に、はり師きゅう師の広告制限も非常に厳しくなったり。
「これらの動きの背後にある、思想・背景って、なんだろう?」
と、僕なりに推理すれば、乱暴な言い方をすれば、もはや、
「医者で治らない疼痛とか難病とか、もう知らん!!こっちはもう金がないんじゃ!!お前ら自由診療でなんとかせえ!」
という遠回しのメッセージにも感じられます。
当然、ターゲットとなる患者層は、今の若者よりお金を持っている「富裕層の老人たち」…ってところでしょうか。
国が勝手に、鍼灸の宣伝をしてくれるのであれば、なおのこと、今まで以上に、鍼灸で出来ることと出来ないことの線引き・リテラシーなどをしっかり確立しておかないと、患者さんから速攻で不信感を持たれかねませんね。
……
それは恐怖と不安の身震いか。
それとも……鍼灸医術に対する武者震いか……
単に寒いだけで「ふるえ産熱」しているだけか……
……
それより、落としてる科目の単位認定試験、頑張ります。
【学生向け勉強会】「素問を読もう!」終了しました
以下、終了しました。
再会する場合はまたお知らせいたします。
2018年10月
----------------------------------------------------------------------
こんにちは、一鍼堂の大原です。
鍼灸学生の皆さんへお知らせです。
この春から、東洋医学のバイブルである黄帝内経を
週1回ペースで読んでいこうという勉強会を
開催しております。
(素問を最初から読んでいってます。)
いつでも参加可能ですので
気になる方はぜひお問い合わせください!
次のうち、どれかにあてはまる方にオススメです↓↓
「黄帝内経を読んだ方が良いと言われたけれど、どうやって読んだら良いか分からない」
「自分一人では勉強がなかなか続かない」
「将来は、東洋医学の伝統的な考えに基づく鍼灸治療を行っていきたい」
「黄帝内経に書かれている内容を、実際に読んで学んでいきたい」
週1回ペースで素問を読んでいくことで、
半年後には漢文を読めるようになることを
目標にしたいと思います。
興味がありましたらぜひお問い合わせください!
参加希望・お問い合わせはこちらへ↓
学生向け勉強会フォーム
↑「エントリーしたい議題」の欄に
「火曜」か「木曜」のどちらかをご記入ください。
以下、詳細です。
【予定内容】
座学で、黄帝内経(素問)の内容を読み合わせていく。
目標としては「週1回ペースで古典に触れていくことで、
半年後には漢文を読めるようになる」
【参加対象】
鍼灸学生(1年生~3年生)
【日時】
(1)火曜の部
毎週火曜日 19時00分 ~ 20時30分頃
(2)木曜の部
毎週木曜日 13時00分 ~ 14時30分頃
火曜か木曜のどちらか参加しやすい方に
ご参加ください。
※上記(1)と(2)について、
同じ週の火曜と木曜は基本的に同じ内容の予定ですが、
進捗状況が異なってくると
少しずつずれてくるかも知れませんので
できるだけ同じ曜日に出席されるのが良いかと思います。
【参加費】
1回あたり2,500円
【会場】
一鍼堂 大阪本院 内(緑地公園駅から徒歩2〜3分)
気になる方は
ぜひお問い合わせください!
エントリーされる方はこちらへ↓
学生向け勉強会フォーム
↑「エントリーしたい議題」の欄に
「火曜」か「木曜」のどちらかをご記入ください。
-------------------------------------------------------------------------
【最後に】
鍼灸の学生さんは、学校や勉強会、仕事等で
色々な技術を習得していく中で、
将来自分が進むべき道というのが
少しずつ見えて来たかも知れません。
また、夢を持ってこの業界に進まれた学生さんも
いらっしゃるると思います。
ですが、伝統的な鍼灸をやってみたいが
古典を学ぶ場所が無いという声を聞きます。
そんな学生さんの為に、
継続して学習していく勉強会を開催しております。
参加者の方と一緒に
自分も勉強させていただく気持ちを忘れず、
共に学んでいけたらと思います。
一定数に達した場合は
定員とさせていただきますので、
ご容赦下さいませ。
(人数が集まらない場合は中止とさせて頂きますので
ご了承くださいますようお願いします。)
【講師】一鍼堂 大原
エントリーはこちら
↓ ↓ ↓
学生向け勉強会フォーム
↑「エントリーしたい議題」の欄に
「火曜」か「木曜」のどちらかをご記入ください。
一鍼堂
祖母の脈を診る。
祖母。94歳。要介護4。今年2月に脳梗塞。
30年前ぐらいに大腸癌→人工肛門。
発声はあれど会話は覚束ない。
食欲旺盛。
六部定位脈診……の真似事をしてみる。
……
肝心脾肺腎のうち、腎が沈なのは予想通りだったか、脾がやたら強いのには腰を抜かした。
次いで、肺も強い。
肝心はかなり弱かった。
うーん、もっと色んな人の脈を診ないと比較ができん。
穴の名前、実技での体験など
テスト前で暗記の時期に入りました。
経穴丸暗記は面白くないので、少しですが付随する情報を書いて認識を深めたいと思います。
腎経
①湧泉 (井木穴、子穴だが腎なので瀉法厳禁)、回陽九鍼穴 足背、足屈曲時、足底の最陥凹部
まんが経穴入門P184 由来「足の少陰腎経の木穴に属し、腎経の脈気が湧き出る」
五兪穴では(井・滎・輸・経・穴)があり、陽経には原が加わる。
霊枢:九鍼十二原では気血の巡りを自然界の水の流れで例えた。
井穴は水源。
②然谷 (滎火穴) 足内側、舟状骨粗面の下方、赤白肉際
まんが経穴入門P184 由来「別名、※龍淵 火が深いところで燃え盛り、水の相剋を受け付けない」
※考察 龍の火のイメージが符合しているのか。
③太谿(原穴、兪土穴) 足関節後内側、内果尖とアキレス腱の間の陥凹部
まんが経穴入門P185 由来「内踝の真後ろの深い陥凹部にあるため、湧泉から出て然谷を通った腎水の流れがここで一つにまとまる」
診断でも使える穴な事がよく分かります。
気になること
最近絡穴が気になっています。
豊隆の調べ物をしている時になぜ豊隆は化痰作用があるのか。
それは絡穴で脾と連絡しているからだという内容に触れたので、穴性を学ぶ時もこういう事も意識していきたいと思います。
実技で
実技の授業である穴に置鍼5分くらいされた。
その時恐らく肝がやられて季肋部あたりが痛み始めた。
この時に何で左何だろうと不思議になった。
理論的には
中薬の配合 P 78
「左右者、陰陽之道路也」とあるように、肝気は左から上昇することで、木気は行き渡り(条達)、肺気が右から下降することで、金気は正常に運行(粛降)します。
とありました。
五行でも左に属するのでその辺もあるのでしょうか。
逆に肝気虚と呼ばれる状態にこの治療をしたらどうなるのか。
気になりました。
本では存在している肝気虚も、実際は肝は剛臓なので中々ないとは思いますが…
プライベート
先週から1ヶ月間だけ兵庫県に住むことになりました。
引っ越し中々大変でしたがやっと落ち着いてきました。
テストが終わったら武庫川にでもゆっくり散歩に行こうと思います。
気持ちの面
後期試験が終われば2回生になります。
色々自分に対して思うことがありますが、極力無心でやれることを黙々とやりたいと思います。
参考資料
まんが経穴入門 周春才編著 土屋憲明訳 医道の日本社
中薬の配合 丁光迪編著 小金井信宏訳 東洋学術出版社
視点
学校の帰りに人と喋りながら帰る。
難しい話ではなく、その人が今何を見ているものを教えてくれた。
自分とは違う視点。
そこに照準を合わせると今まで見えていなかった別のものが目に入る。
新しい発見があった。
何に合わせるか。
改めてとても大切な事だと思いました。
一緒に帰って良かった。
行動は大切!
三国志(01)
少年の頃にはマンガの『三国志』(著:横山光輝)を
数年に一回はマイブームが起きて夢中に読んでおりました。
私と同様に三国志ファンの友人が中国に観光に行った時の話ですが、
長江の武漢で色々と観て歩いて、今度は赤壁を見に行こうと観光船に乗ったとの事。
遊覧を楽しみ、そろそろ赤壁に到着かと思っていたら、
急に引き返して帰ってしまった!と嘆いていたのを思い出しました。
まだ中国といえば、”自転車と人民服”をイメージする時代の話ですが、
観光がビジネス化されていなかった時代では、
現地の人たちにとって自分たちの歴史であって、観光資源という概念が遠かったのかもしれません。
三国志の軌跡を観光したいと思い続けて数年が過ぎましたが、
観てみたい場所は様々あります。
”赤壁”もそうですが、”五丈原”も訪れたい場所の一つです。
孔明最期の地であり、「死せる孔明生ける仲達を走らす」の場所。
それでは
「桃園の誓い」より物語を楽しみたいと思います。
【参考文献】
『三國志』(株)六興出版社
六經病機(01)
太陽病病機
【01】営衛不調
【02】表寒裏飲
【03】邪入經輸
【04】邪陥胸中
【05】実邪結胸
【06】邪陥心中
【07】邪熱下痢
【08】經邪入腑
【09】臓腑陽傷
【10】臓腑陰傷
【01】営衛不調
営は陰で、衛は陽である。衛営は拮抗する事によって、衛外を守り固め開闔を主るという生理機能をもつ。
外的要因により膚表の営または衛の力量に変化が生じ、陰陽昇降のバランスが崩れる。
成無己(金代)は「風は衛にあつまる。・・寒は営にあつまる。」(『注解傷寒論』)とする。
外邪(風)を感受すれば、衛の昇散活動が優位に立ち、衛強営弱病機を発生させる。
外邪(寒)を感受すれば、営の沈降し静かであるという性質が優位に立ち、営強衛弱病機を生み出す。
太陽表虚証。
衛の昇散性が優位となり、外表部に浮揚し、発熱する。
弱くなった営の沈降凝集し静かであるという特性が弱まり、内部を守れず自汗し脉が浮緩となる。
自汗がでれば、衛が散漫となり皮膚の温煦作用が失われ、悪風(風に当たると寒気)する。
太陽中風、陽浮而陰弱、陽浮者、熱自發。
陰弱者、汗自出。
嗇嗇悪寒、淅淅悪風、翕翕發熱、鼻鳴乾嘔者、桂枝湯主之。
方一。
太陽表実証。
営の沈降凝集し静かであるという性質が強くなり、衛が肌表の内側に抑鬱されて、膚表を温めることができなくなり、悪寒が現れる。
陽気が発散されず発熱する。
営の沈降凝集し静かであるという性質が、無汗・脉の浮緊となる。
血を滞らせれるので、頭痛や関節の痛みが現れる。
太陽病、頭痛、發熱、身疼、腰痛、骨節疼痛、惡風無汗而喘者、麻黄湯主之。
方五。
表寒裏熱証。
風寒両方を感受すれば、寒邪は営に入り、風は衛に入る。
営の沈降凝集し静かな性質が強くなり、悪寒ひどくなり無汗。
衛の昇散活動性が強くなるが、汗が出ないので熱を排出できず内部に鬱滞する。
その為に高熱して煩躁し、表裏とも実証となる。
太陽中風、脉浮緊、發熱、惡寒、身疼痛、不汗出而煩躁者、大青龍湯主之。
若脉微弱、汗出惡風者、不可服之。
服之則厥逆、筋惕肉瞤、此為逆也。
大青龍湯方。
八。
【参考文献】
『中医病因病機学』東洋学術出版社
『中医臨床のための 方剤学』医歯薬出版株式会社
『傷寒雑病論』東洋学術出版社
先週の患者さん
先週の患者さん
以前見たことのある空気感だった。
脾虚がベースにあり気遣いをされる方。
ストレスを受けていてもどこか他に気を使われている。
ストレスを受けたとしても体質や本人の処理の仕方で傷つく臓腑は違う。
また、自身がここが気になると先生に報告した穴で治療するとどうなるか。
以前別の患者さんで聞いた話を思い出した。
匙加減を間違うときっと暴発してしまう。
直接的、表裏と二つの側面から難しいのかと想像。
フットサル
鍼灸とは全く別の話です。
フットサル選手の感覚を知りたくて、
「ガチガチの個サルより緩い個サルの方がドリブルが難しくないか?」と聞いてみた。
帰ってきた答えがブレースピードが早すぎると相手によっては反応できないから、そういう時は自身のプレースピードも下げてプレーするらしい。
ガチガチならガチガチ、小学生なら小学生とそこに応じたスピードでプレーすると上手くいく。
とは言ってもやはり自身に近い方が楽で、小学生相手が一番難しいらしいです。
色々役立てそうな感覚だと感じました。
手
手で覚える。
この事を明日はより強く意識いこうと思います。
その為にもきちんと集中します。
周辺
どんな状況でも周りへの意識を忘れずに。
そこが抜けた瞬間治療どころでは無くなる。
気遣い
受付をしていて、診察券を返すときに予約時にメールアドレスを伝える。
その時に自身が不親切な案内だった。
その事実が自身の課題を表していると思った。
改めるべき点。
優しくないといけない。
ホッカイロ
冷え性の方でお腹や腰にホッカイロを一日中貼りっぱなしで行動をしている方がいらっしゃいますが、貼りっぱなしは要注意です。
寒いところに出る時だけ貼るのであれば良いのですが、貼りっぱなしにしていると余分な熱が邪となり体に入り込み臓腑の弱いところに症状がでる場合があります。
例えばもともと脾虚の症候がある場合、余分な熱が脾を傷つけ運化の働きが弱くなり飲食物をうまく処理できず滞りができてしまい時間が経つと瘀血になってしまいます。
瘀血ができると通り道が狭くなるので気血の流れがより悪くなり熱が生み出されていきます。
熱は陽の性質なので、上へ上へ登っていき、眩暈や頭痛、嘔吐といった上部の症状がでてきます。
その上、脾は湿の調整を行なっています。
湿をうまく処理できずに浮腫んだり、皮膚に湿が残ったままになり冷えの症状がでたりします。
体の内側は熱により傷ついているのに、表面は冷えを感じる。冷えを感じるからホッカイロを貼る。ホッカイロによってまた余分な熱を体に与えては弱っていく。とゆう悪循環が生じます。