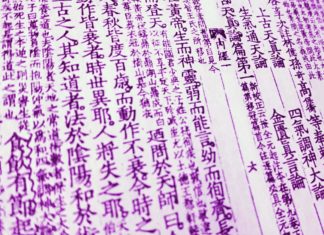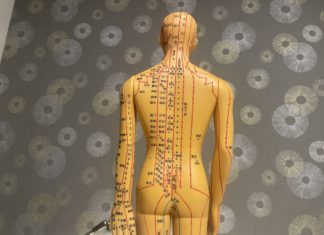医古文の学習(1)
一鍼堂(大阪本院)で行われる「素問を読もう!」(木曜日)に参加しています。
【黄帝内経素問】
《上古天眞論篇第一》
昔在黄帝.生而神靈.弱而能言.幼而徇齊.長而敦敏.成而登天.
廼問於天師曰.余聞上古之人.春秋皆度百歳.而動作不衰.今時之人.年半百.而動作皆衰者.時世異耶.人將失之耶.
岐伯對曰.
上古之人.其知道者.法於陰陽.和於術數.食飮有節.起居有常.不妄作勞.故能形與神倶.而盡終其天年.度百歳乃去.
今時之人不然也.以酒爲漿.以妄爲常.醉以入房.以欲竭其精.以耗散其眞.不知持滿.不時御神.務快其心.逆於生樂.起居無節.故半百而衰也.
(読み下しや翻訳に関しては、沢山の先生方が訳した書物がありますので割愛させて頂きます。)
黄帝を表して
生 弱 幼 長 成
神靈 能言 徇齊 敦敏 登天
五進法から始まってます。「このリズムでいきますよ。」と感じます。
当時の発音も解れば、より以上感ずることも多いのかと、、残念な思いと探究心が交錯しますが。
法 和 節 常 不作
陰陽 術數 食飮 起居 妄勞
「昔の人は偉かった」との話の中に一つのモデルケースが示されています。
ここの”陰陽”をとってみても、具体的に話しているようで総論的な意味合いも含んでいるように思えます。
素問全体を通して理解が進む事を期待しつつ進んでまいります。
漿 常 入房 竭精 耗散 不知 御 快 逆 無節
酒 妄 醉 欲 眞 滿 神 心 生樂 起居
今度は”今時の人”のダメ出しパターン。
倍の10件も記されています。説教が長い・・・タイプのようです。
エジプトのピラミッドを作った労働者の落書きに「最近の若者はダメだ」とあったように聞いたことあります。
大古の昔より、「変わらぬものは変わらない」と感じた記憶があります。
医古文もまた共通の不変性を示しているように思います。
年を重ねて分かるからこそ、伝えるべき”無駄”を伝えようとしているように感じるのですが、
どうなのでしょうか?
参考文献
「現代語訳 黄帝内経素問 上」東洋学術出版社
「重廣補注 黄帝内経素問」天宇出版社
稲垣英伸
背中
ありがたい事に最近人の背中を触らせて頂く機会が増えてきました。
しかし現状として捉えることが出来ていない。
正直な感想としてはどうしたものか。
手が重いと仰って頂く事が多い。
ベターって感じで触ってしまっているのかな。
そんな感じなので何とか手を軽くする様に訓練しないといけないなと思っています。
前に脈診の際に教えて頂いた体勢も意識してみよう。
患者側が体験出来たことも勉強になりました。
なかなか人に背中を触られる経験ってしないので、触られたら嫌な部分ってあるんだと知れました。
また背候診と繋がるかは分かりませんが、自分の身体で食事を変えたら何か変化あるのかなと思って一回の食事量と肉をだいぶ減らして変化を追ってみています。
感覚の部分はあまり感じれていませんが、肉食の人の肌のキメが荒いということと筋肉が硬くなるという事は体感する事が出来ました。
なんの役に立つか分かりませんがせっかくやってみたので書いて残させていただきます。
逆子
テーマ「逆子」
逆子を治したいとご相談に来られたら。
西洋医学的に知っておくべきこと
医学用語「骨盤位」
・骨盤位の分類(大きく分けて三種)
・骨盤位の誘因(母体側、胎児側)
・そのまま経膣分娩するリスク
・帝王切開によるリスク
・いつまでに自然回転しておいた方が良いのか
・回転しない時の対処法
など
踏まえた上で確認すること
・現在何周目
・お医者さんの見解
など
自身の課題
帝王切開について調べ不足。
妊婦さんの不安も知っておく。
その他妊婦さんへの気遣い。
お腹が膨れたり、つわり、精神的な不安など状況に応じてその人が不安に思わない様に心がける。
医療人としての意識と知識と態度。
相手に対しての共感。
安心して頂ける様に。
相手に対する優しさが足りない。
調べてわかった事と考察
子宮筋腫も逆子の原因となる。
それが原因で回りづらい事も。
一般に至陰・三陰交の灸は逆子に良いとされる。
実際に治った例も沢山あるので体質に合う人には良いものなのだと感じる。
しかし合わない場合。
例えば三陰交(大陰)は書物によれば病がない場合は禁灸穴にも指定されている。
金匱要略解説 P575 婦人妊娠病脈治
「懐妊後、最も怖いのは湿熱が胎気を損傷することである。胎が湿熱を受けると、胎は不安定になる。」
中医鍼灸臨床経穴学 P 78
「妊娠期間の母体には、「血を以て用と為す」という特徴がある。臓腑経絡の血は、衝任に注ぎ胎児を滋養している。そのため、妊婦の全身には血分が不足し、気分が偏盛となっている。」
以上から場合によれば熱入血室も起こりえる。
すると衝任脈を通して他経に移り、他臓腑を傷つける可能性もある。
そうなった場合、直接的に湿熱になるケース、欝熱になり気の停滞を起こし血の巡りも悪くなって養胎しづらくなるケースなども考えられる。
そもそも逆子が血室で起こることなら直接的でなくとも間接的でもそこにアプローチをかければ治るのかもしれない。
ただし、動きやすいタイミングなどもあるのでそこは注意が必要。
参考資料
中医鍼灸臨床経穴学 東洋学術出版社 李時珍著
金匱要略解説 東洋学術出版社 何任著
補瀉
補寫に関して気になったので調べていきます。
《現代語訳 黄帝内経霊枢上巻》P 14 九鍼十二原篇
「針の技術の要は、刺鍼の部位が適当であることと徐疾の手法の正確な運用にあります。」
「気の働きの虚実変化を理解すれば、補瀉の手法を正確に運用でき、毛筋ほどの間違いも起きる様なことがありません。」
「気の往来の時期を理解してはじめて刺鍼の正確な時間を理解できるのです。」
「気が去るとき経脈が空疎になるのを『逆』、気が来るとき経脈が充実するのを『順』といいます。」
《現代語訳 黄帝内経霊枢上巻》P 18、19 九鍼十二原篇
「瀉法を用いるときは、かならず鍼を素早く刺入して気を得たのちゆっくり抜き去り、大いに鍼孔を揺らして、表用を開けば、邪気を外に洩らすことが出来ます」
「補法を用いるときは、経脈の巡行方向にしたがって鍼を向け、ゆっくりと散漫な様子でそっと刺します。鍼をめぐらして気を導き、経穴を按じて鍼を刺すとき、あたかも蚊が皮膚の上を刺しているようなあるかなきかの感覚があります。鍼を抜き去るのは速く、矢が弦から放たれたかのように、右手で鍼を抜き、急ぎ左手で鍼穴を按ずれば、経気は留まり、外は発散せず、中は充実し、留血の弊害もありません。」
「鍼を刺すときは経気の到来を候わなくてはなりません。」
《現代語訳 黄帝内経素問》P272 鍼解篇
「虚証を鍼治療する際には、鍼下に熱感がなくてはなりません。なぜなら正気が充実すると熱感が生まれるからです。
実証を治療するときには、鍼下に涼感を感じなくてはなりません。なぜなら邪気が衰えてはじめて涼感が起こるからです。」
→補寫どちらにおいても気が至ったり去ったり、熱感・涼感を感じる感覚が重要。
手技としては、どういった速度で刺し抜きするか・どの様な角度で刺すか・揺らすか・案じるか。
《鍼灸臨床能力 北辰会方式 理論篇》P344
「臨床的には、かつては太い鍼をゆっくり入れて気を温め集めて、スッと抜いていた。抜くときにゆっくり抜くと、鍼穴が余計に広がって、気が漏れやすく散りやすくなるためである。現在の鍼は細くなっているのでその必要がない。ゆっくり入れてゆっくり抜けば良いのである。」
→古代と現代の違いを感じました。昔と全く同じ条件ではないので、形ではなくそれが何を意味するのかきちんと理解していないとこれからズレた認識が生まれてきそうです。
また、ここから補瀉の際にどんな鍼を選ぶかなどのヒントにもなっていそうな気がします。
読んでいて、昔の人はどんな方法で鍼を作って保管していたのか。
現在は鍼をどの様にして作っているのか。
現在の鍼になった分岐点などはいつなのか。
なども気になってきました。
参考資料
《現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻》 東洋学術出版社 南京中医学院編著
《現代語訳 黄帝内経素問 中巻》 東洋学術出版社 南京中医学院編著
《鍼灸臨床能力 北辰会方式 理論篇》 緑書房 一般社団法人 北辰会学術部編著
保護中: 知り合いのおばちゃんとの会話
以前、僕は知的障害者授産施設で、生活支援員として、1年限定の約束で働いていた。
その時、その施設でボランティアで来ておられたおばちゃんと、先日、某所にて久々に会った。
ひさしぶり、からの挨拶で、その施設の現在のよもやま話に花が咲き、
「福祉なんてね、真面目な人間がやるもんじゃないよー」などと、ぶっちゃけトーク。
……
僕が鍼灸師の専門学校に通っていることを話すと、
「アンタまだモラトリアムかいね~」
と、呆れられながら、苦笑された。
しかしその後、別れ際、おばちゃんから言われたことに対して、背中に稲妻が走った。
「
鍼灸師なんてね、本来は目の見えない、視覚障害者のための職業だったのよ!
アンタは【晴眼者】なんだから、しっかり勉強せな、アカンよ!!
」
確かにはっきり、【晴眼者】という単語を飛び出してきたことに対して、僕は瞬時に、おばちゃんの博識さと、己自身の甘さを痛感させられた。
そうだった。
学校に入る前、かなり入念に、自分なりに、業界のリサーチをしていたつもりだった。
そこで異口同音に言われたことは、
「鍼灸学校なんてどこに行ってもおんなじ。国家試験なんて簡単だし。免許をとってからの勉強のほうが遥かに大事だよ。」
と。
しかし、ある意味、自分が視覚障害者の職業を、奪っているのではないか、という認識や自覚はなかった。
もう少し、ヒリヒリした感覚を持って、学業に臨もう。
そう思わされた。
オバちゃんには感謝してる。
鍼治療をうけて②
2021/04/07
週に1回の治療
すっかり不眠の症状が表に出て来なくなった。
今週は体調が良く、下半身が軽いと感じていた。
歩く体が軽い
すいすいと動く
軽いのに力が入る
そういえば...と思い出した。先週は腹の調子が悪かった
今回の治療中に、体調について聞かれて、
腹の調子が悪いと自分が訴えていたことを思い出した。
先週 水曜日あたりに普段の量より多く食べる機会があって、それからのことだった。
とにかくガスの量が著しくて、便の出方はでたらめ、排便の周期もばらばら。
食事は食べれるし、出せるけどずっと(下痢や便秘はなく)軟便気味。
脾胃の気に一定の損傷が起きていることは明らかと感じられた。
パンクしたタイヤを交換せずそのままに走っているから、
車内でガタガタと揺れがひどい、まるでそんな有り様だった。
それも今、整えられている
今回の治療中には、何度も深い呼吸が起こった。
からだが積極的に欠伸を、深呼吸をしにいっているみたいに起こった。
ただ普段でる欠伸に似ているけど違う。
勢いよく吸って吐いてとやっているけど、自分が意図的にやる時の深呼吸とも違う。
(この前記録に残した、なにか栓が外れて空気が抜ける様な、あのときのとも違う)
結局、治療を終えて体を起こして動き出すまでその深い呼吸が続いた
気の巡り方は、体表を動くというよりじんわりと中にという感覚
腹部には湧いてくる様な動き
(気が満ちるというのはこういうこを指すのか)
欠伸の時の様に涙が出た。じわりと出る、それが何度も続くので
流れ出たあとが温かく
お腹が温かく
手と足が充実している
体の各所に温もりがあって、一瞬
のぼせの症状が出る体調の時の五心煩熱が想起されたが
手と足と、胸 じゃなくて腹。
それから温かさの種類が違う、対極とさえ感じる
(こちらの状態を指す言葉はあるのだろうか?)
________________________
これまで鍼を受けたことがないという人から
鍼はどんなだと興味を持って聞かれることがあり、
こうした感覚を載せて伝えられないものか考えた
自然治癒力という言葉で表すのでは全然足りない
からだそのものの力を持って癒える
体調が戻ったあとこそ自然を知る
紙飛行機がふわりと着地する光景が似合う
日々の発見
○ 格言
パニックを起こす私にも
ポンっと思い出せる先生の言葉があって、
その言葉は大抵10文字以内ぐらいです。
カルテに書き留めた走り書きやメモを読み直たり、
先生とお話しして突き刺さるシンプルな言葉。
今の支えとなり、課題であり、目標となっています。
◯ 波長が合う
ガードが堅い患者さんだ、とそれとなく聞いていました。
「先入観は置いときましょう」
と下野先生から言葉をいただき、どんなもんかなぁと
患者さんの世界感にお邪魔してきました。
中々言葉では表現できませんが、
自然と問診、切経ができる不思議な経験をしました。
これを波長が合うという事だそうです。
風寒邪の咳嗽から穴性を学ぶ①
初めまして。
2月より寺子屋でお世話になり始めました日下と申します。
先生方の様な治療家になれるよう様々な事を学んで成長したいと思います。
よろしくお願い致します。
最近穴性学を学び始めたので勉強した内容をアウトプットさせて頂きます。
中医鍼灸 臨床経穴学 P25
「風寒外束、肺失宣降(風寒の邪による宣降失調)
症状:喉が痒い、咳嗽、痰は稀薄である。鼻閉、鼻水。声が重い。または発熱、悪寒、頭痛。無汗。舌苔薄白、脈浮など。
処方:中府、風門、大椎(瀉)…疏風散寒、宣肺止咳。」
この意味を考えていきたいと思います。
まずは穴性を調べる前に、風寒邪がなぜこの様な状況を引き起こすか考えていきます。
記載には2パターンありますが、処方が同じなので異病同治だと思います。
先にパターン①について考察していきます。
①喉が痒い
霊枢経脈篇に肺経の流れが書かれていますが、その中に「従肺系横出腋下」とあります。
この肺系は喉嚨をさし、肺経の流れが悪くなれば経絡上にある喉にも影響すると考えられます。
また、痒みを感じるのは魄によるものだと思いました。
肺は魄を蔵すと言われますが、魄は魂と比べて、「本能的な、比較的低級な精神活動・神経活動のこと。」と言われ、
ここには痒いといった感覚も含まれます。
風寒邪によって肺経の流れが悪くなった結果、肺の蔵す魄にも影響が及んだのではないでしょうか。
②咳嗽
肺失宣降とある様に、正常な状態では肺は宣散粛降という働きをしますが、その機能が弱ると気が上逆して咳が現れます。
③痰は稀薄である。
肺が宣降失調を起こし、通調水道機能に影響を及ぼしたためかと思います。
中医病因病機学P448
「寒痰寒飲は肺に潜伏し、肺の宣降機能が失われる。症状は、咳嗽・喘息・澄んだ痰が出る・大量の白い痰が出る、などである。」
④鼻閉
素問 金匱真言論篇に「入通於肺。開竅於鼻。」
肺の機能失調が鼻に影響しているのだと思います。
⑤鼻水
③と同じ理由かと思います。
⑥声が重い
風寒喉瘖と言われるものです。
中医基本用語辞典
P209「風寒が外から襲い、肺気の宣発・粛降運動が失われ、風寒の邪気が喉部に停留し、声帯の開閉が不順になって本病証を生じる。」
穴性を学ぶにはその人に何が起こっているのかをまず知る必要があるかと思ったので調べてみました。
経絡の走行経路なども意識できるので勉強になります。
その他記載のない参考文献:
「臓腑経絡学」 アルテミシア 藤本蓮風監修 P39、42、44
「中医学って何だろう」東洋学術出版社 P194、196、211
舌の考察など
六経弁証
何故か日本では太陽病→少陽病→陽明病→太陰病→少陰病→厥陰病 と教わる。
藤平健先生の論文も読んだが、腸チフスを元に話を展開されていて良くわからない。
熱論を崩すほどのものなのか。
元々傷寒論だと①太陽→陽明 ②太陽→少陽のパターンどちらも明示されてあるからそこに意味はないと思うのだけど、教科書では順序逆転。
先生に聞いてみてもあまり納得出来なかった。
色んな意見があっていいと思いますが、自身の中では邪気の進展を機械的に覚えないでおく事にしました。
恐る恐る
まだ全然自身の人をきちんとした条件で刺すといった経験は足りていませんが、散々強く刺される経験なら学校でしてきた。
人の治療がどうこうという事はどうでもいいのですが、自分の中に落とし込もうとして考えた時は
こうしてみたらどうだろう?と疑問が生まれる。
その中で「怖いもの知らずな鍼」は自分の目指すところではない。
では逆説的に「怖いものを知る鍼」ならどうなるのか。
刺す経験はないけど、先生方・寺子屋・受付で話した事や起こった事、そこで感じた事を鍼に落とし込めると近付くのかな。
刺す前に刺すイメージをしてみる。
実際刺すとどうなるのかな。
でもその前に相手の体が答えてくれる様にしよう。
猫
うちの猫が高齢(18歳)で最近は寿命も近いかなといった状態になってきた。
呼吸が深く吸えず荒くなる、腰の落ち、水を飲むとすぐに吐く、恐らく原穴であろう位置のスカスカ感、いつも寝転んでいる、嬉しくなると喉をならすゴロゴロの回数低下、聴力はずいぶん前から低下傾向 など腎を思わせる症状が出ている。
何とか残りを楽に過ごしてほしいので少しだけ手を加える様にしていると少し状態は落ち着く。
最後まで楽に、良い猫生であったなと感じてほしいものです。
舌の考察①
舌質・舌形
胖大傾向。
歯痕がみられ、ハリがない。
舌苔
表面的に潤っていて滑苔傾向。
舌色
表裏ともに色が薄く、裏が弱っている。
舌先に少し赤みが見られる。
その他
舌の出し方がデロンといった感じ。
舌診ではないが、口周りに白い吹き出物あり。
脈
中〜沈、押し切ると消える、尺部の落ちがあった。
緩と少し滑だった印象。
考察
舌の色や力のない出し方から臓腑の弱りが起こり、正気が建っていないと想定。
そのため気も上がり、舌先に色が偏る。
臓腑の弱りもあるために水を捌く力もないため停滞して過度な潤いが生まれる。
全体的な色調は気がいかないため出ていない。
脈と合わせて中焦、下焦を強めて正気を建たせる。
舌の考察②
舌質・舌形
胖大傾向。
舌色
こちらも舌先に少し赤みが目立つ。
表面に比べ裏が赤い。
少し色褪せが気になる。
舌先か辺縁部に黒い色調のものが見える。
舌苔
奥の方に膩苔が見られる。
黄色みがあるが恐らく飲み物(茶)の影響。
その他
舌の出し方としてある程度の力はある。
考察
膩苔から飲食物の停滞が見られる。
裏に熱を抱え込み、表面的な色褪せが見られる事から裏熱が陰分を傷つけている可能性がある。
辺縁部分の色調からも上焦〜中焦の境目に邪気の停滞が見られる。
抱え込んだ裏熱を取りつつ本質的な中焦を建てて舌を引き締め、膩苔も取れる様にする。
境目の邪気も直接的・間接的な方法はあるにしろ動かして取っていく。
振り返って
○ 3/29
合格発表も終わり、
同じ県同士のクラスメイトとピクニック。
空と土と風と樹々の中で
なんと爽快なことか。
どんな鍼灸師になりたいか
進路のことも語り合った。
○ 3月下旬 繰返し基礎
国試では西洋医学ばかり勉強していたので
東洋医学をもう一度復習した。
各疾患を勉強をしたら、
臓腑の解剖学や生理作用や流注に戻る。
ほうほう、
基礎 ⇄ 応用の繰返しの必要性を改めて痛感。
○ 4/2 直感
一鍼堂でお腹や背候診をすると
気色が浮き上がって見えます。
触れずとも「ここだ!」という時がある。
探そうと念じるのではなく、
とても冷静で素直な心持ち。
寧ろ、「ここだよー」って
自然と患者さんが教えてくれる
という例えが近いかもしれない。
○ 4/3 ① 脈診(寺子屋にて)
生まれつき脾が弱い人の
施術前と後の変化を診せてもらいました。
健康人の脈とは…
「胃の気の旺盛な脈」
しなやか、潤いがある、生々として力みがない
“名状を以てするに難しき脈象のこと”
(言葉にすること表現し難い脈)
施術前に寸・関を重按しても
僅かに触れるような脈でしたが、
施術後、脈形が細くても脈力が戻ってきた。
相対的に正気が上がり、これも善しとする。
「そもそもの体質を考慮すべきだ」
という先生の言葉を
心に留め、これから意識していきたい。
○ 4/3 ②尺膚診 (寺子屋にて)
鍼治療を続けると
身体の変化に敏感になる。
あまり治療をしていない方の体は
言葉にし難い何か鈍い感覚があった。
尺膚診で足裏がジットリと濡れた感触、
陥凹すべき所が隆起している感触から
邪の性質を知ることで、
治療方針を立てていく。
一見肝鬱のように聞こえるが、
そもそもの本質は何か。
生体の中でどのような駆引きを展開させるか
先生の治療を聞くとワクワクした。
○ 4/3 ③ 問診
初めて患者さんに問診させてもらいました。
「5分で問診から切経まで診てきて下さい」
と先生からお達しがあったが、10分オーバー…
その後先生の問診を扉越しに聞く。
「花粉症はありますか?」
ではなく、
「花粉症は目、鼻、喉、頭痛などどこに出ますか?」
具体的な例を挙げると
その後の弁証に役立つなと
教えていただけました。
○ 4/5 色々あった日
新年度、新しい環境。
もう学生じゃないんやなと
急に襲う例えようのない不安。
勝手に緊張してピリピリ。
具合も悪くなって
集中できなくてまたピリピリ。
でも指摘されるまで気付かなかった。
「好きなものってなんですか?」
と受付さんに聞かれてハッとした。
Pinterestで密かに貯めている
好きなものコレクションが頭に浮かんだ。
自然と気持ちがアガる。
鍼灸の世界にいるから
鍼灸のことだけ考えなくちゃと
雁字搦めになって
肝心な時に気が散漫になり
集中できず空回りしていた。
「焦らんとやっていこう」
「楽しんで」
院長の言葉がありがたい。
自分のやり方で気持ちを切り替える方法を
模索していこう。
帰宅後、ノートの走り書きを目にする。
「和敬静寂」
静かな荘厳さの中に
何か穏やかな
人間の気が交流できるような雰囲気
脈診の心得の時に書き留めたものだが、
夜な夜な心に沁み渡る言葉でした。