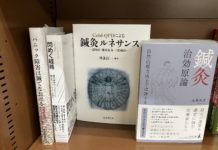短気
11月は鍼灸学校の定期試験があったため、ブログをお休みしていました。
無事試験が終わり、クリスマスや年末で浮かれた気分になり勉強がおろそかになりそうのですが、
あと1年ちょっとで国試も控えているかとおもうと、気を引き締めないといけないなぁと感じる今日このごろです。
最近は年のせいか1年があっという間に感じます。
先日、学校の東洋医学の授業だったか本で読んだかで、「短気」という言葉が出てきて、
気が短く怒りっぽいという意味で捉えていたので、なんか意味が合わないなと思い調べてみたら
短気は“呼吸が浅く、深い呼吸ができない状態”(中国医学辞典 基礎編 陳 有昭 編著 p477より引用)
中医学では短気は息切れという意味なんですね。
怒りっぽくなっているときは呼吸も浅くなっているだろうし、短気はどちらの意味にしろ体によろしくないですね。
「短気は損気」を肝に命じて、イライラしないよう気をつけます。
気になった文章、歴史
気になった文章
「小腹控睾。引腰脊。上衝心。邪在小腸者。連睾系。屬于脊。貫肝肺。絡心系。
氣盛則厥逆。上衝腸胃。燻肝。散于盲。結于臍。故取之盲原以散之…」
霊枢 四時気第十九
大変勉強になりました。
天台烏薬散が使われるシーンに近い気がします。
また、これも更に探っていくと別の原因にも繋がってくるので、治療方法は変えていかないといけないとも思いました。
歴史
歴史を追うと、太素が幕末の偉い人達に与えた影響は大きそうで、これを踏まえて色々見ていっています。
色々繋がってくるので面白いです。
全く別物の認識がゴロゴロ出てきて勉強になります。
怒るエネルギー
肝火上炎
肝気鬱結や他の熱(火)邪などにより、肝の火が燃え上がったもの。めまい、耳鳴り、頭痛、顔面紅潮、焦燥易怒感、動悸、不眠などの上部熱症状や口苦、季肋部、出血、過多月経、黄色小便などを呈する。虚実錯雑証の肝陽上亢とは異なり、実熱証であり腰部下肢脱力などの虚熱症状は呈さない。
実践漢薬学 三浦於菟 p379
日頃から好きでよく韓国ドラマを観るのですが、何せストーリーの展開が劇的で劇中に俳優さんが怒りに震えて眩暈を起こして倒れたり、急に心臓が苦しくなって病院に運ばれたりするシーンがよくあります。日本だとそこまで怒りに任せて爆発するようなことはしないのだと思いますが、お国柄もあるのでしょうが、反応がストレートでわかりやすい。なので第三者としてテレビの前で観ているいち視聴者としてはある種爽快なのでしょう。
怒りを爆発させるのにも相当なエネルギーが必要だと思います。私は元々がエネルギー不足なので怒るのが面倒くさいです。面倒くさくて怒りの沸点まで上昇させることができません。なので、ある意味怒りを爆発、発散できる人を羨ましく思います。いつか体質を改善してエネルギーが満たされた人間なったら爆発させてみたいです(笑)
お国柄とありますが、日本は世界的にみても穏やかな民族であることは間違いないと思います。怒りの原動力はエネルギーだと思いますので、そのエネルギーは陰気ではなくて陽気になるでしょう。日本食は鮮度を生かして生の食材が多かったり、本来の食材の味を生かして薄味にしたりと、どちらかというと精進料理的な食事が多いと思います。陽気は少なそうです。
それに比べて中華や韓国料理は肉食も多く辛い香辛料もふんだんに使った料理が多く、みるからにエネルギーに満ちた食事に見えます。そういった食事を常にしているのもお国柄を作る要因の一つではないかと思います。
しかし現代はその和食文化も相当変わってきているので、このまま何十年何百年と進んでいくうちに、日本人の気質も変化していくのだと思います。
梅核気
肝気鬱結を勉強している際に気になる言葉が出てきたので調べてみました。
肝気鬱結の症状には、イライラする、憂鬱、有声のため息がよく出る、
胸腹部の脹痛、月経不順などがあるが、その中に「梅核気」というものがありました。
「梅核気」は現代病名だと神経性咽喉部狭窄症(ヒステリー球)というそうです。
のどに梅干しの種があるような違和感があり、飲み込もうとしても
吐き出そうとしてもなくならないが、飲食は普通にとれる。
気の滞りによって咽喉部に痰が生じていることによって異物感があるようです。
ストレスが原因の病は現代に多いような感じがしますが、金匱要略にも
「婦人、咽中に炙臠(あぶった肉の切り身)有るが如きは、半夏厚朴湯之を主る」
とあり、婦人・・・と書かれているが、男性にも起こる。
他の臓器の影響(脾胃が多い?)、過度の情志、情志の抑制などによって肝の
疏泄作用が失調することによって発生した気滞が肺に昇って起こる。
理気去痰解うつ作用のある半夏厚朴湯を用いて治療するとあるように、薬物による治療が行われることが多い。
梅の種は肉のかたまり、というより大きいしもっと固いように思いますが
実際に梅核気があるような方に尋ねると名前の由来となっている梅の種が
つまっているような、ということはわからないけど息苦しい感じがあり、不快であるとのこと。
臨床医学総論でもヒステリー症を勉強した際に、ヒステリーはギリシャ語で「子宮」を
意味することから昔は子宮が原因で引き起こされる女性の病気とされていた、と習いました。
西洋でも東洋でも同じように病を分類していることもあるのかと思うと興味深く感じました。
先々週の施術で
水分穴の少し右だったように思う。(今も反応あり)
刺入深度は1ミリか2ミリか。
置鍼開始して少しして、
息がうまく吸えていないことに気づく。
吐くことはできている。
入ってこない、がそのことに特に不安はない。
数分して抜鍼の後、それまでの状態をはずみに
誘いこまれるようにからだにもたらされた深い呼吸と何か。
横隔膜の動きが抑制されていたのか。
これも穴性のひとつにあたるのか。
他の方においても似た作用をもたらすのか。
衝脈
少し前から奇経八脈について書籍にて学ぶようになりました。
先日、研究生同士でモデルになり治療する機会があったのですが、その時の主訴がL2当たりに腰痛があるというものでした。
舌診や腹診、脈診、切経などを一通り行なった結果、左の地機と太渓に鍼をおいたのですが、その際、被験者によると腹部深部の嫌な感覚と足のそれぞれの鍼のおいた穴が繋がった感覚ががあったようで、置鍼とともに段々和らいで行ったようです。
それと呼応したのか背中の痛みも薄まったと言われていました。
身体の深部という言葉に、奇経八脈の「衝脈」を思い浮かべました。
私なりに奇経を交えて考察したいと思います。
衝脈は五臓六腑十二経脈の海で、五臓六腑は皆、衝脈によって血を受けていると言います。
また天人地三才理論によれば、督脈は天脈、任脈は地脈、衝脈は人脈になります。つまり督脈と任脈を繋ぎ、陰陽のバランスをとっているとも言えます。
衝脈の流注自体は複雑でいろんな説がありますが、今回関係がありそうなところを抜粋すると、〜臨床に役立つ 奇経八脈の使い方〜 著:高野 耕造
・李時珍は、衝脈の腹部における走行について「素問」骨空論と「難経」の折衷案を採用した。つまり、足の少陰腎経と足の陽明胃経を走行するとしている。
・胸部の衝脈は、浅層を走行するルート(経穴があるルート)と深層を走行するルートの2本のモデルを設定する方がよい。
・衝脈の下肢の流注は、大腿部内側面を下降し、足の太陰脾経と足の少陰腎経の間を通過する。そして、膝窩の陰谷に到達している。
・衝脈の下腿部の流注は、陰谷から2脈に分かれる。一つは、陰谷から足の少陰腎経に沿い、内果の後方から足底部の湧泉に向かう。もう一つは、斜め前方の足の太陰脾経を下降し、三陰交と交わり、足の太陰脾経とともに内果をめぐり、公孫から隠白に向かう。
・衝脈の足の太陰脾経を通る分枝は、足背面に出て拇趾と示趾の間を下って太衝に至る。
・衝脈の流注は、背裏(脊椎の臓面)を上行し大杼まで達している。
・衝脈は足の太陽膀胱経の一行線の脊柱前面を上向し、督脈を背裏から支えている。
取穴したツボは下腿部の脾経と腎経でした。衝脈の流注とも関係しているかと思います。また反応があった腹部の位置ですが、正確には確認してなかったですが、左側の胃経と腎経の辺りだったかと思います。
ちょうどその裏面の左背部(三焦兪から腎兪辺り)に膨隆がみられました。施術後、膨隆は幾分柔らかくなり、平になろうとしているように思えました。
またこの著者は左右の腎から供給される精気は帯脈を通じて左右の衝脈に流れるとしてます。
おそらく日頃の疲れがベースにあるところ、前日の睡眠不足で更に腎気虚損となり、腰痛が強く現れたと思われます。
一般的に奇経は臓腑とは直接連携はせず、正経の気血の調整を果たしていると言われます。
しかし衝脈は十二経の海と言われているため、経絡の異常や五臓六腑の不調による影響が色濃く現れやすいはずです。
今回は衝脈(人)を充実させるためにも、先天の精(天)に関わる腎経と後天の精(地)に関わる脾経に施術している事になります。
恥ずかしいほどの浅学ですが、少しずつ学びを深められたらと思います。
夙川にて
図書館、公民館など、外で勉強する事が殆どです。
好きな場所で、夙川沿いの静かなところに”西宮市立中央図書館”があります。
休憩に川沿いで新鮮な空気を吸うのですが、ふと思い出した事がありましたので。
以前に、六甲山からの鉄砲水で犠牲者が出たことがありました。
その時に『山上が曇れば大蛇が通る』という伝承を知ります。
古人が鉄砲水を大蛇に例えて後世に伝えやすくしたのだと思います。
それをきっかけとして、スサノオノミコトがヤマタノオロチ退治を
”治水対策の比喩”であるとの仮説にも出会う事になりました。
クラスメイトが話の中で「東洋医学=スピリチュアル」との認識に違和感を覚えたのを覚えています。
東洋医学を学ぶという事は災害の地に建つ石碑のように、
古人が未来へ向けた思いに耳を傾ける事のように思います。
とか、思い出しながら国家試験に向けての勉強の年末です。
気づかない
自宅にて。
大きな雷が鳴った。
何か考えている時、ここにきちんと注意を向けれていただろうか。
換気扇の音、記事を書くときのパソコンの冷たさ、椅子の座り心地、耳鳴り。
見落としていたものばかりです。
湧く泉
最近、母親に鍼をしています。
体表観察の練習に観させてもらってるうちに、ちょっと打っておこうかなと選んだツボが湧泉でした。足裏にあるので普通は他人に打つのには躊躇しがちなツボかと思いますが、そこは家族なので変な遠慮もありませんでした。本人も痛くないとも言っているので、実家に寄った時にはお決まりのように打っています。
何年も前から、母親から足の異常は聞いていて、足の裏から指先にかけて痺れた感じがあり、本人にとってかなり気持ちが悪く気になっているみたいでした。病院で診てもらったことがありましたが、特に異常はないと言われて治療はされなかったようです。ひどい時には指先が赤く腫れた感じになったり見た目の変化も現れるとも言っていました。
私としては、老化が原因で足の屈筋支帯のような神経の通るトンネルがダメになって神経を圧迫して痺れてるのかな?と漠然と想像していました。だからもう治らないのでは?と。
そしたら一回打ったあと、また打って欲しいとお願いしてきました。
本人曰く、鍼を一回打った翌日に何だか足の裏の感覚がいつもと違ったようで、歩いていても足裏の感覚が良くなってる感じがしたそうです。それは回を重ねるごとに改善していると今は喜んでいます。足の甲の氷を載せたような冷えも取れたとも言っています。
湧泉
本穴は足心に位置する腎経の井穴であり、脈気が湧き出す処であるため、湧泉と命名された。
~鍼灸学 東洋学術出版社~
湧泉にそんな力があるんでしょうか。