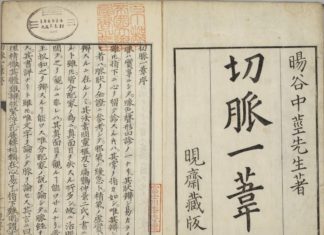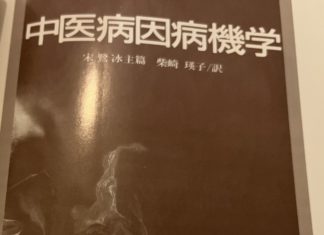『舌鑑弁正 訳釈』より”紅にて震える舌”から学ぶ。
こんにちは稲垣です。
顫動する紅舌を『舌鑑弁正 訳釈』より学びます。
第一百十三、紅戦舌。
鸇掉不安、蠕蠕微動也。
深紅、赤紅而戦者、宜三黄石膏等湯。
紫紅、瘀紅而戦舌、宜三黄白虎大承気。
淡紅而戦者、宜十全大補湯。
鮮紅、灼紅而戦舌者、宜六味地黄湯、
此舌虚火、実火皆有之(均裏証、無表証)、誤治即壊。
旧説指為汗多亡陽或漏風所致、
且不詳弁而概用温補、謬也。
(引用:『舌鑑弁正 訳釈』P244~245)
第113 紅戦舌
舌の震えが止まらずクネクネする。
深紅・赤紅で震えるものは、三黄石膏湯がよい。
紫紅・瘀紅で震えるものは、三黄白虎大承気湯がよい。
淡紅で震えるものは、十全大補湯がよい。
鮮紅・灼紅震えるものは、六味地黄湯がよく、
この舌は虚火・実火ともにあり(ひとしく裏証で、表証はない)、誤治は壊証になる。
旧説は汗多くて亡陽であったり、漏風によるというが、
詳しく調べずに概して温補を用いるのは、間違っている。
※十全大補湯については《和剤局方》を出典とする
『中医臨床のための 方剤学』と『舌鑑弁正 訳釈』の生薬について
成分が一部異なっており、精査していきたいと思います。
梁玉瑜は旧説の主治の方として紅戦舌に対して温補剤を一概に用いる事に注意を促し、
戦舌でも、紅舌の様々について湯液を選定されています。
《戦舌》
深紅・赤紅 → 解表清裏剤 「三黄石膏湯」
紫紅・瘀紅 → 寒下剤 「三黄白虎大承気湯」
淡紅 → 氣血双補剤 「十全大補湯」
鮮紅・灼紅 → 補陰剤 「六味地黄湯」
舌体がふるえ動いたり、舌筋がぴくぴくと動き、自分では制御できないことである。
「顫動舌」「顫抖舌」「舌顫」「舌戦」などと呼ふ。
虚損あるいは動風によって生じ、筋脈が陽気の温養と陰液の濡潤をえられないために
安寧を欠いて顫動したり、肝風内動にともなって振戦が引き起こされる。
(引用:『中医臨床のための 舌診と脈診』P30)
内熱の強そうな患者さんの、手足に動きがあるのが気になっており、
戦舌の特徴を調べることにより、熱と体の動きとの共通点を見つける事ができたらと考えました。
現時点では明確な発見には至っておりませんが、今後につなげたいと思います。
【参考文献】
『舌鑑弁正 訳釈』たにぐち書店
『中医臨床のための 方剤学』医歯薬出版
『中医臨床のための 舌診と脈診』医歯薬出版
五行大義(05)
【更】
01:かえる、あらためる
02:かわる、あらたまる
03:こもごも、かわるがわる
04:さきもり、交代して役に服する義
05:夜閒の時限の稱呼(称呼:よび名)
06:つぐ、つづく
07:つぐなう
08:経る
09:ふける、すぎる
10:よい
11:としより
12:姓
從革
金曰從革。從革者、革更也。從範而更。
形革成器也。西方物旣成、殺氣之盛。
故秋氣起、而鷹隼撃、春氣動、而鷹隼化。此殺生之二端。
是以白露爲露。露者殺伐之表。
王者敎兵、兵集戎事、以誅不義、禁暴亂、以安百姓。
古之人君、安不忘危、以戒不虞。
故曰、天下雖安、忘戰者危、國邑雖强、好戰必亡。
殺伐必應義。應義則金氣順。
金氣順、則如其性。如其性者、工治鑄作、革形成器。
如人君樂侵凌、好攻戰、貧色賂、輕百姓之命、
人民騒動、則金失其性、治鑄不化、凝滯渠堅、不成者衆。
秋時萬物皆熟、百穀已熟。
若逆金氣、則萬物不成。故曰金不從革。
金は従革という。従革なるもの、革は更なり。範にしたがい更となす。
形あらたまりて器を成すなり。西方の物、既になりて殺氣盛んなり。
故に秋氣が起こりて鷹隼を撃ち、春氣動きて鷹隼を化す。これ殺生の二端なり。
これをもって白露は露となす。露なるもの殺伐の表なり。
王なるもの兵に教え、兵を戎事の為にで集め、以って不義をうち、暴乱を禁じ、もって百姓を安ず。
古の人君、安ずれど危うきを忘れず、もって不具をいましめる。
故にいわく、天下が安といえども、戦いを忘れたものは危うき、国邑が強といえども、戦いを好めば必ず亡ぶ。
殺伐は必ず義に応ず。義は則ち金氣の順に応ず。
金氣の順、その性のごとく。その性の如くは、工治・鋳作し、形をあらため器をなす。
もし人君が侵凌を楽しみ、攻戦を好み、色賂をむさぼり、百姓の命を軽んじ、
人民の騒動、則ち金がその性を失い、治鋳は化せずに、凝滞し渠堅する、ならないもの衆し。
秋は万物みな熟し、百穀はすでに熟す。
若し金氣に逆らえば、則ち万物ならず。故に金は従革せずという。
【参考文献】
『五行大義』明德出版社
『大漢和辞典(第5巻、962頁)』大修館書店
切脈一葦 上巻3 (総論の最後まで)
こんにちは、大原です。
前回の続きです。
(前回:切脈一葦 上巻2)
今回も、原文に書かれている文意を汲み取りながら、
その読み方や
著者の言いたいことは何かを考えていきます。
今回は総論の最後までいきます。
---------------------------------------------------------------------------------
画像は京都大学デジタルアーカイブ『切脈一葦』より、
12ページ目の最後から引用。
(本ブログ記事で参照した箇所を掲載)
<読み>
たとえよくこの三部九候を、詳に診し得ると
いえども、脈色声形の四診を参考にするの時に臨みて、
何の益あらんや。
これ脈の一診をもって、
万病を診し分からんと欲する者のなすところにして紙上の空論なり。
→前回の記事でもありましたが
ここでもばっさりと「これは机上の空論であるぞ」
と言ってます。
「脈診だけで全部分かろうとしなくても良いではないか、
何かメリットがあるのか?」と。
晋の王叔和(おうしゅくか)、
『難経』に依(よ)りて、
左右を分かち臓腑を配して、もって脈学を唱う。
これをもって同調の人、称して脈学の大成となす。
しかれども脈は血気の流行にして、一条脈の道路のみ、
何ぞ三部各その脈状を異にするの理あらんや。
また、浮中沈は、病人の脈の浮中沈にして、
医の指を浮中沈するの義にあらず。
なんぞ医の指の浮沈をもって、五臓をうかがうの理あらんや。
たとえ明達の人といえども、
その実なくして、その理を究むる理あることなし。
これ王叔和以来、一人も脈学の極めを知る人なきゆえんなり。
後世の脈を学ぶ者、分配家のために、欺かれるを知らず。
徒に精神を費やして、
その道を明むることあたわずといえども、
なおいまだ空言にして、その実なきことを知らず。
ただ、己が見解の及ばざる所となす。
これをもって分配家の脈法を出づることあたわず。
→「いくら聡明で物事の道理によく通じている人でも
中身の無いことに対しては、
その理を追求することはできない。」
と書かれています。
説得力のある言い回しで、手厳しいですね。
ついに一寸九分の地をもって三部となし、
あるいは
掌後の高骨をもって関となし、
あるいは
臂の長短に従いて三部を定め、
あるいは
まず関を按じて、次に寸尺を按ずといい、
あるいは
浮かべて腑を診し、沈めて臓を診し、中をもって胃気を診すといい、
あるいは
浮かべて心肺を診し、沈めて肝腎を診し、中もって胃を診すといい、
あるいは
左を人迎となし、右を気口となし、
あるいは
左の寸関尺に心、小腸、肝、胆、腎、膀胱を配し、
右の寸関尺に、肺、大腸、脾、胃、命門、三焦を配して、
もって診脈の定法と為す。
これ皆三部各その候を異にするの理なきことを知らざるの誤りなり。
→「以上に述べた脈診の考え方は、
理が無いことを知らないためにできた、
誤った理論である。」
と書かれています。
読んでみると分かりますが、
この脈診の考え方は専門学校の授業などで習うものですね・・・。
もし三部各その候を異にすべきときは、反関の脈の如きは、
何の処をもって三部と為(な)さんや。
思わざるの甚だしきなり。
およそ医を業となる者は、皆脈を診するをもって、
先務としながら、もし
この決断することあたわざる脈法をもって、
闇然として、人の病を診して、疑いを隠して、その証を弁ぜんとす。
その危うきこと薄氷を踏むがごとし。
これ何の心なるや。
これを何と言わんや。恐るべし。
歎(たん)すべし。
医を学ぶ者、深く心を用うべし。
あるいは言う、
寸関尺を分かっては、分配家の説なりといえども、
寸部の脈進みて、魚際へ上がる者を、頭中の病とし、
関部の脈に力ある者を、腹中の病とし、
尺部の脈に滞りある者を、腰脚の病とし、
左右は左右を分けて、
心を用いるときは、病人に患る所を問わずといえども、
大概知れる者なり。
しかればすなわち、
寸関尺の部位全く無しと言えからざるなり。
謙(著者の名前)曰く、
これは人相家相等を占する者と、同断にして、
医門に不用のことなり。
いかんとなれば、頭中に病あり、
あるいは腹中に病あり、
あるいは腰脚に病ありて、医に治を求むる者なれば、
脈をもって頭中の病、腹中の病、腰脚の病を占するに及ばず。
病邪の辞にて、知れたることなり。
何ぞ脈をもって占することを竢(ま)たんや。
→ざっくりと
「寸部を頭中の病、
関部を腹中の病、
尺部を腰脚の病とするような脈診は、
これは占いと同じであり
医学には不用である。」
と書かれています。
脈診を「占い」と比喩してますが、これは
脈の寸関尺だけで
病の場所を特定してしまうことに対する
懸念を表したのだと思います。
それ脈の用は、
頭中の病、腹中の病、腰・脚の病ある人の脈を診して、
色声形の三診に合して、
その病の陰陽・表裏・寒熱・虚実を決断するの診法なり。
病毒頭中にあり、腹中にあり、腰・脚に在るの類は、
みな瀉形の与(あずか)る所にして、
切脈の与(あずか)る所にあらざるなり。
これ病証有りて、脈を診すると、
脈を診して、病証を占するとの辞なり。
また脈をもって病毒の所を占すると、
脈をもって病証の陰陽・表裏・寒熱・虚実を決断するの弁なり。
→「脈診の目的は、
患者さんの身体の色や声、形態と合わせて、
それらを総合して、
病の陰陽・表裏・寒熱・虚実を決めるものである。
病が頭にあるのか、腹中にあるのか、腰・脚にあるのかを
脈の寸関尺で分かるとうたっているが、
病がどこにあるのかは「瀉形」によって判断するものであり、
脈診で判断するものではない。
ある病があるからそれに合った脈が現れるのであって、
その脈だからそれに合った病が現れるということではない。
さらに言い換えると、
その脈だから、病の陰陽・表裏・寒熱・虚実が決まるということではない。」
と書かれています。
つまり、脈診だけで全部は分からないぞ!ということが
ずっと書かれていますね。
また、病がどこにあるのかは「瀉形」によって判断するもの
とありますが、
この「瀉形」とは、
切脈、望色、聴声、写形(望診)といった
四診合算のことをいうようです。
その中の脈診だけで病を判断してしまうのは
いかがなものか、
ということを一貫して言っているのだと思います。
引用:
京都大学デジタルアーカイブ『切脈一葦』より
病因について(3)
自身に降りかかった病について~
以前に目の病気を患いました。
正に、お先真っ暗・・の感がありました。
当時の健康状態では、肝臓が極めて悪い状態。
(現在は問題なく完治しております。)
【五行】
・五蔵 肝、心、脾、肺、腎
・五官 目、舌、口、鼻、耳
東洋医学の道に入り”肝”と”目”の繋がりを学ぶにつれ、感嘆します。
肝を傷る原因とは・・
【内因】
〇七情
・怒 気機を上昇させる 肝
・喜 気機を緩ませる 心
・思 気機を鬱結させる 脾
・憂 気機を鬱滞させる 肺
・悲 気機を消耗させる 肺
・恐 気機を下降させる 腎
・驚 気機の乱れを起こす 腎
当時の年月を思い出せば、”怒”というのが日常であったように思います。
肝の持ってる昇発という特性が過度となり、蔵を損傷させていたのでしょうか。
鶏が先か?卵が先か?
肝を損傷したので、易怒となるのか・・
易怒となったので、肝を損傷するのか・・
デフレスパイラルの様に悪循環に陥った先に”病”があるように思います。
〈肝火上炎〉
肝気鬱が火に変化し、気と火が上逆したために起きる事多い。
...
休み
普段一生懸命働いて休む。
この休みの時の過ごし方はとても大切だと思う。
上手く休めると、しっかり息を抜く事で今あるものに気づくことができる。
普段から過呼吸な訳ではないけども、ちゃんと呼吸できている感覚になる。
ここまで落とせると、色んな事が整理できて、それを次に活かせるし、思考以外の感覚が使え、今あるものを感じる事ができる。
ここがスタート時点で、そこで感じたものをどう解釈するか。
今も、ふと、唐揚げの臭いがした。
そういえば、この前嗅覚障害の患者さんがきたよな。
でも、自分でも匂いが感じにくくなっていた。この状態になって匂いをしっかり感じている。
きっかけが、ご本人の仰っていた通りなんだろうか。
患者さんも色々お伝えくださるが、それを鵜呑みにせずに別の視点で見ることで、座学としての弁証の視点から別の見え方ができる。
自身で作る脳の束縛の様なものから解けて、気づくものがある。
仕事で懸命にやる事もいいというか、やるべきなんですけど、休みは休みの過ごし方がある。
勉強しなきゃ、ではなくやりたいからやる。
自由にできていないと、外界との現象と壁ができる。
幅を狭める。
午前中ゆっくり過ごして感じた事なので、この感覚をもったまま午後の休日を過ごしたらどうなるかやってみよう。
冬休みに入りました!
こんにちは高山です。
冬休みに入りました。
今は東洋医学の病因と病機について勉強しています。
聞いたこともない物質や構造を学び、そこからさらに深掘りしていく、理解するのがむずかしいことが書いてあったり、量も多いです
でも、病気がなぜ起こってしまったか、やその病気の症候などが記されていて、治療する上で、きっと大切になることが、書かれています。ちょうど冬休みですし、じっくり時間をかけて勉強しています。
まだ僕は一年生で、脈診や舌の色、腹診などの仕方や、
感触は全然知りませんが、いずれ学ぶ時が来ると思いますので、今はまだ机上の知識ですが、どんどん吸収していきたいと思います。
患者さんをしっかりと治療できて、喜ばれる日を夢見て日々前に進み続けます。
【用語集】肝鬱気滞
肝鬱は
肝気鬱もしくは、肝気鬱結の略称であり、
肝気が滞ることをあらわす。
気滞は、その名の通り、
常に循環しているはずの「気」の流れが「滞」っている状態をあらわす。
肝気の特徴として、
樹木がなんの制約も受けず、
ただのびのびと枝を伸ばしていく様を「条達」。
縦横無尽に全身を動き回ることを「疏泄」と表現する。
精神的な負担などがかかることで
肝気が伸びやかに巡らなくなり、
肝気が鬱屈した状態、すなわち「肝鬱」となる。
参考文献:
『黄帝内経素問』
『黄帝内経霊枢』
『中医基本用語辞典』 東洋学術出版社
『基礎中医学』 神戸中医学研究会
『中国医学辞典』 たにぐち書店
『臓腑経絡学』 アルテミシア
『鍼灸医学事典』 医道の日本社
ホッカイロ
冷え性の方でお腹や腰にホッカイロを一日中貼りっぱなしで行動をしている方がいらっしゃいますが、貼りっぱなしは要注意です。
寒いところに出る時だけ貼るのであれば良いのですが、貼りっぱなしにしていると余分な熱が邪となり体に入り込み臓腑の弱いところに症状がでる場合があります。
例えばもともと脾虚の症候がある場合、余分な熱が脾を傷つけ運化の働きが弱くなり飲食物をうまく処理できず滞りができてしまい時間が経つと瘀血になってしまいます。
瘀血ができると通り道が狭くなるので気血の流れがより悪くなり熱が生み出されていきます。
熱は陽の性質なので、上へ上へ登っていき、眩暈や頭痛、嘔吐といった上部の症状がでてきます。
その上、脾は湿の調整を行なっています。
湿をうまく処理できずに浮腫んだり、皮膚に湿が残ったままになり冷えの症状がでたりします。
体の内側は熱により傷ついているのに、表面は冷えを感じる。冷えを感じるからホッカイロを貼る。ホッカイロによってまた余分な熱を体に与えては弱っていく。とゆう悪循環が生じます。
「10/7(日) 学生向け勉強会」の感想
講師は、盧先生より学びました。
私は現在、鍼灸学校の2年生です。
日々、書物を目にしたり妄想を繰り返したりする日々を過ごしておりますが、
「自分なら、○○なのかな~」とシュミレーションをしたりもします。
それが1年生とは違うところと感じています。
書物などを読み進める上で再確認できたのが、”帰納”と”演繹”。
【帰納】
個々の事例の観察より、これを含む一般命題を確立する事。
一つの症例より他の患者の症例も、このケースであろうとする。
【演繹】
1つまたはそれ以上の命題より、論理法則に基づいて結論を導出する思考の手続。
学術論議を症例を元に構築していき、結論を推定する。
本日学んだ事の一つで重要な事だと感じています。
歴代医家たちのカルテの集積が、症例集であって絶対的な答えではないのだろうと思えます。
学術的に議論の構築を進めることも重要に思いますし、
現実の臨床を繰り返すことと、歴代医家たちのカルテの集積とを見比べることも
精度を高める為に必要な事なのかと思います。
今年のノーベル賞受賞者の本庶佑博士は、記者の質問に
「・・・教科書に書いてあること、文字になっていることを信じない、疑いを持つこと」
と答え、有名な論文雑誌も疑う対象の例外ではないと強調されています。
「自分の目で物を見る、そして納得する。そこまで諦めない」
とも答えらています。
考えていた事と学んだ事がリンクする機会が多かったように自分では思いました。
座学をし、二礼二拍手の効果を実感し、病床にて臨床実技をし、、、
時間のある限り、幅のある講義を試そうされていた様に思います。
お疲れ様でした。次回も楽しみにしています。
最後になりましたが、機会を頂いた院長にお礼申し上げます。
平成30年 秋
稲垣 英伸
血分病機
こんにちは、稲垣です。
血分病機についてまとめます。
【血分病機】
血は営より深層にあり、血分病変は営分病変よりもさらに重くいとされ、
心・肝・腎などに重大な障害の可能性があるとされる。
・熱深動血
熱邪が血分まで深く入りこんで火に変わり、火毒が燃えあがり、血絡を損傷し、血流を混乱させる。
血熱が心を傷れば、主神の蔵ゆえに意識障害・譫語・狂躁が現われる。
・血瘀血畜
血熱が気を損傷し、気滞をつくり血瘀に発展させる。
邪熱が血とぶつかる、陰液を熱邪が損傷させて営血を消耗させた場合、など瘀血となる。
さらに発展し、邪熱と瘀血がぶつかりあえば「血結胸」「下焦畜血」などとなる。
・血熱動風
血熱が盛んになり、厥陰まで入り込み、肝を犯して筋脈を焼く。
陰血を消耗させ、火より風を生じさせる。痙攣などが発生する。
少火は壮火となり、風を起こして、さらに火を煽る。
意識の混迷や厥証を発生させる。
・耗血動血
熱の血分侵入では、耗血・血竭・亡血・動血を起こす。
血の不足により筋を潤すことが出来ず、また陰が陽を抑えられずに
血虚生風、虚風内動を起こす。
【参考文献】
『中医病因病機学』東洋学術出版社