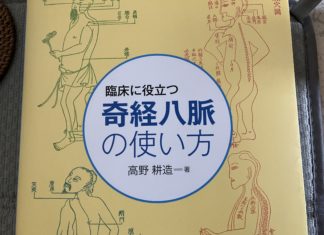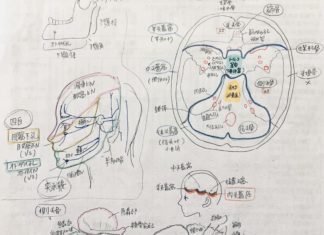奇経八脈
「臨床に役立つ 奇経八脈の使い方」高野耕造ー著
メインで奇経八脈について書かれた本を読んだのは初めてでしたが、私にとっては知らないことが多く、とても興味深くためになりました。
所属経穴や循行順序などは、鍼灸甲乙経 難経 十四経発揮 奇経八脈考などの書籍によって違いがあることも知ることができました。
小ムズカしい古典から読むよりも、私にとっては良かったと思います。
その上で著者が考える奇経八脈がその後展開されていくのですが、その説明にも抵抗なく感心を持って読むことができましたし、その理論に基づいた著者オリジナルの臨床への応用も、私のようなレベルの者でも納得できました。
いつかその一部でも活用できる日が来たらいいなと思います。
振り返って
○ 3/29
合格発表も終わり、
同じ県同士のクラスメイトとピクニック。
空と土と風と樹々の中で
なんと爽快なことか。
どんな鍼灸師になりたいか
進路のことも語り合った。
○ 3月下旬 繰返し基礎
国試では西洋医学ばかり勉強していたので
東洋医学をもう一度復習した。
各疾患を勉強をしたら、
臓腑の解剖学や生理作用や流注に戻る。
ほうほう、
基礎 ⇄ 応用の繰返しの必要性を改めて痛感。
○ 4/2 直感
一鍼堂でお腹や背候診をすると
気色が浮き上がって見えます。
触れずとも「ここだ!」という時がある。
探そうと念じるのではなく、
とても冷静で素直な心持ち。
寧ろ、「ここだよー」って
自然と患者さんが教えてくれる
という例えが近いかもしれない。
○ 4/3 ① 脈診(寺子屋にて)
生まれつき脾が弱い人の
施術前と後の変化を診せてもらいました。
健康人の脈とは…
「胃の気の旺盛な脈」
しなやか、潤いがある、生々として力みがない
“名状を以てするに難しき脈象のこと”
(言葉にすること表現し難い脈)
施術前に寸・関を重按しても
僅かに触れるような脈でしたが、
施術後、脈形が細くても脈力が戻ってきた。
相対的に正気が上がり、これも善しとする。
「そもそもの体質を考慮すべきだ」
という先生の言葉を
心に留め、これから意識していきたい。
○ 4/3 ②尺膚診 (寺子屋にて)
鍼治療を続けると
身体の変化に敏感になる。
あまり治療をしていない方の体は
言葉にし難い何か鈍い感覚があった。
尺膚診で足裏がジットリと濡れた感触、
陥凹すべき所が隆起している感触から
邪の性質を知ることで、
治療方針を立てていく。
一見肝鬱のように聞こえるが、
そもそもの本質は何か。
生体の中でどのような駆引きを展開させるか
先生の治療を聞くとワクワクした。
○ 4/3 ③ 問診
初めて患者さんに問診させてもらいました。
「5分で問診から切経まで診てきて下さい」
と先生からお達しがあったが、10分オーバー…
その後先生の問診を扉越しに聞く。
「花粉症はありますか?」
ではなく、
「花粉症は目、鼻、喉、頭痛などどこに出ますか?」
具体的な例を挙げると
その後の弁証に役立つなと
教えていただけました。
○ 4/5 色々あった日
新年度、新しい環境。
もう学生じゃないんやなと
急に襲う例えようのない不安。
勝手に緊張してピリピリ。
具合も悪くなって
集中できなくてまたピリピリ。
でも指摘されるまで気付かなかった。
「好きなものってなんですか?」
と受付さんに聞かれてハッとした。
Pinterestで密かに貯めている
好きなものコレクションが頭に浮かんだ。
自然と気持ちがアガる。
鍼灸の世界にいるから
鍼灸のことだけ考えなくちゃと
雁字搦めになって
肝心な時に気が散漫になり
集中できず空回りしていた。
「焦らんとやっていこう」
「楽しんで」
院長の言葉がありがたい。
自分のやり方で気持ちを切り替える方法を
模索していこう。
帰宅後、ノートの走り書きを目にする。
「和敬静寂」
静かな荘厳さの中に
何か穏やかな
人間の気が交流できるような雰囲気
脈診の心得の時に書き留めたものだが、
夜な夜な心に沁み渡る言葉でした。
実験、公孫など
珈琲
私はコーヒーが合いません。
香りや苦味が好きなんですが、身体に合わない。
自分の感覚として体感しているのは肝の暴走。
散々書籍にあることなので発見でも何でもないのですが、体感としても感じます。
じゃあ、それを思いっきり飲んだらどうなるか。
ボトルコーヒーを一本一気飲みしてみた。
自分の体の反応と術者としての感覚を飲む前、飲んだ後と比較してみました。
術者として
普段から鋭くない感覚が更に鈍くなる。
全く相手を感じる事ができない。
身体を触らせて頂く時に頭に言葉が多くなる。
体感として
自意識が強くなる。
ナポレオンはコーヒーを勇気の出る飲み物として愛用していたらしいのですが、鈍感になっただけじゃないのか。と思った。
また、時間差があるので直後には出ない。
ただ影響がマックスになった時、酒で酔った感覚になる。
調べるとコーヒー酔いというものもあるらしいです。
気逆を起こすと気が大きくなる?
脈の寸には影響があった気がします。
頭には色んな言葉が浮かぶ様に。
エゴが強くなった感覚?
いつも以上に自分の世界だけで全てを完結させている気がしました。
家に帰って自分の肝経の経穴に鍼をしてある程度は和らぎましたが、躁鬱状態ってこんな感じなのかなと思いました。
手に受ける感覚
何か違和感を感じたとして、それぞれ種類が違ってくる。
細分化して言語化できればいいなと思いました。
体感として一つ重い感覚はあったので、まずはそれについて考えていく。
切経
術者と患者が合った時、そこに囚われ過ぎるのは良くないと思いました。
ベタベタ触ると段々反応も薄れ、よく分からなくなってくる。
即時即決、一回でどれだけ情報を頂けるか。
患者とどの様な意識で向き合うか、模索します。
深さも意識したい。
公孫
この穴の認識を深めたい。
奇経八脈考、症例から学ぶ中医婦人科などを中心に調べているのですが、まだイメージが掴めていません。
引き続き調べて行きます。
楽しむこと
表面的なものではなくて、この本質って何なんだろう。
考える事で遠のいていっているかもしれないけど、一旦はこの工程を踏みたいと思います。
歯が痛い日々
歯が痛い。
歯痛ってこんなに辛いものんなんですね。
昔に虫歯で治療した歯が疼くので、被せを外して再度削ってもらったのですが、その歯が痛すぎる(泣)
仮歯状態なんですが、麻酔が切れた後から痛みが始まってずっと痛いんですけど。歯が気になって集中できず、何事もやる気が起きなくなっています。もちろん勉強も・・・
再度かかってる歯医者さんに相談したら、恐らく歯髄炎でしょうと言われました。通常は一週間くらいで痛みは治るそうです。
歯の神経を抜くのは嫌なので、この痛みに耐えるためにロキソニンを毎日飲んでいます。
それでも痛くて気になってしまうので、何かいい方法はないかと思いついたのが針麻酔でした。昔行った勉強会でそんな実技もしたはずだと、資料を引っ張り出し、電気パルスをつなげて取り敢えずやってみようかと。
患部は下の歯なので、三叉神経の第3枝の大迎と下関。あと合谷と曲池。
パルスを行っている時は何となく痛みが薄らいでいるような感じがするものの、鍼を抜くとやっぱり歯の痛みは消えてなかったです(泣)
やり方がマズかったのでしょうか。
痛みが去るまで、我慢するしかなさそうです。
赤い宝石
先日、奈良でいちご狩りを堪能してきました。
私は奈良のブランドいちごの「あすかルビー」の大ファンです。
2年前から春になりオンシーズンになると、あるルートから毎週注文して「あすかルビー」を堪能していましたが、今年からは手に入れるルートがなくなってしまい残念に思っていました。
ところが今年は運良く現地に行く機会に恵まれて、思いっきり堪能できたのです。
もう何個食べたかわかりません(笑)
真っ赤な大きく膨らんだ苺は見るだけでテンションが上がって最高ですね。
赤い宝石と言われますが、全くその通りです。
そうそう、最後に勉強にも繋げないと。
薬膳 いちご
体に必要な水分を補充し、体の組織や器官を潤す働きがあります。食薬として滋陰類に分類されます。(※肝経・胃経・肺経の経絡に強く作用)
潤肺生津
肺に潤いを与え、体に不足した水分を増やす。
滋陰補血
体に必要な潤い(水分)や血液を養う。
清熱解毒
体にこもった熱を冷まして取り除くと同時に、毒素を体外に排出する。
利尿
体に滞った余分な水分を、尿として排泄する。
健脾和胃
脾を強くし、胃の調子を整える。
SATOYAMA 食薬図鑑
https://www.satoyama.bio/databook/fruits/strawberry/
確かにお腹いっぱいいちごを食べた後、身体が冷えて、しばらくしたら利尿効果が半端なくトイレばっかり行っていました。
今回は食べ放題だったので、必要以上に食べてしまったのが悪かったんだと思います。でも2時間ほどしたら、あんなにたくさん食べたのにかかわらず、お腹がペコペコになって胃がスッキリしていました。
ちなみに、ちょうどその日はWBCの日本vsメキシコの日で、隣のビニールハウスから「やったー!、日本逆転や! 勝った!!勝った!!」と1人のおじさんが叫ぶと、ビニールハウス中が一気に歓喜に包まれました。みんな苺を摘みながらも、日本の勝敗が気になって仕方なかったんですね。とってもよい思い出になりました。
痰
今日は痰について書いていこうと思います。
痰は津液が濃密になり、粘ることにより形成されるものだそうです。
ネバネバ、ドロドロしたイメージです。
津液はサラサラした水のイメージです。
ではなぜサラサラしたものがドロドロに変わってしまうのでしょうか?
津液というのは飲食物が水穀の精に変化してそれが津液に変わる
また、気が津液の元という考えもあります。
つまり、津液を作る過程でなんらかの異常があり、痰ができてしまうのでしょうか?
あるいは、津液がなにか不純物が混ざってドロドロになってしまうのか。
あるいは、熱で津液が焼かれてドロドロになってしまうのか。
何が原因で痰が形成されてしまうのかが疑問です。
津液を形成するのは基本的には脾の役割で、つまり脾の失調によって痰が形成されてしまう。
そして、痰は気に従ってあらゆるところへ留まるとあるので、痰による症状は様々です。
肺に行けば痰や咳嗽が出る
脾に行けば胸焼け
経絡上に留まればあらゆる部位の疼痛、など症状は多岐に渡ります。
そして、気の流れを止めれば、気鬱、気滞が起こり、万病の元です。
脂肪は痰という考えにも至るのでしょうか?
つまり、太り過ぎの方は脾の働きが悪く、
正常に運化が出来なくて、食べてもお腹が減り、
水穀が正常に気化されず痰になって、脂肪として体の周りに痰がついているという考えも一つあるかも知れません。
痰がどのようなことが原因で形成されてしまうことについてよく考えたいと思います。
食について
過食や、少食は万病の元だと考えます。
生き物は気、血、津液から構成されています。
この気、血、津液は食べ物から構成されています。
だから、食べ物は生き物が正常に生きていくには、正常に食べ物を摂取していかなくてはならないと考えます。
そして、食べ物を化成しているのは主に脾の役割です。
なので、脾の失調は万病の始まりとも言えるのではないでしょうか?
少食になると、脾で食べ物を水穀の精に変えることが出来なくて、気血津液を化成することが出来なくなり
臓腑機能の失調や、気虚、血虚など、虚症が顕著になるのではないでしょうか。
たしかにお腹が減っている時は頭がボーってしたり、体に力が入らない時が多々あります。
しかし、少食は食べたいけど食べ物がないから食べない時と
食べ物を食べてないけど、お腹が減らないという2種類があると思います。
前者よりも後者が問題だと考えます。
食べてないのにお腹が減らないということは生理的な現象に反します。
これにはどのような原因があるのでしょうか?
やはり、一つに脾の機能失調があるのではないでしょうか?
逆に過食になると、脾胃が食べ物を精に化成できる容量を超え、食べ物が脾胃に溜まってしまう。
そうすると脾胃を傷つけててしまったり、食滞、食積が溜まって、痰に変化して、あらゆる場所に病を起こしてしまう。
これも食べても食べてもお腹が減ってしまうのは生理的に異常があると考えます。
食べても運化されずそのまま流されてしまったり、
身体に気、血が十分に行き渡らずにずーっと運化してしまって食欲が抑えられないなど、多々原因はあると思います。
食べ過ぎて太っている方や、少食で痩せすぎな方も、
意志が弱くてそうなってしまっていると考える方が多くいますが、
東洋医学的に考えると根性論ではなく、病の一つとして考えることもできます。
ただいま、寺子屋
国試と卒業式を終え
半年ぶりに寺子屋に帰って来ました。
そして本日国試の合格発表があり無事合格しました。
今日は国試でお休みしていた間のことを
書こうと思います。
寺子屋はお休みしましたが、
体調管理のため一鍼堂に通っていました。
秋の卒業試験前は胸痛、息切れ、動悸。
締め付ける服や下着が着れなくなりました。
コロナに罹患して以来、
のぼせと耳鳴りがひどく、
疲れるとすぐ喉が痛くなり
ここで放置してしまうと
発熱して咳が止まらなくなります。
卒試直前は
「間食を避けるように」
と院長が仰っていました。
脾の負担を減らし、脳に気血が行くようにということかな?
お世話になっていた漢方の先生が以前
「甘いもん食べたらアホになるし心が病む」
と言っていました。
しかし、この頃学校では脳に栄養が行くと
ブドウ糖ラムネが大流行。
とにかく何事もほどほどにですね。
卒試が終わり、油断してファーストフードを食べた後、
コロナは陰性でしたが38度の熱が出て咳が止まらなくなりました。
下野先生が以前話していたことを思い出しました。
「クリスマス、正月明けは温病チックな人が多い」
去年高熱を出した時に、内科の先生が
「熱が出るのは胃腸を大切にせえへんからや」と
脂質カットメニュー表をくれました。
肝鬱で脾がコテンパに弱っているし
脂っこい食事、夜中のおやつ、
クリームと名のつくもの(アイス、ケーキ、チョコ)を避け
徹底的に和食生活することにしました。
冬になり、学校の暖房が暑くて逆上せが酷くなり
眠ることができなくなりました。
冬場寒冷となるべき時に反って温暖であったり、
厚着し過ぎたりしても精気を外洩れせしめ「陰虚」の体質を作ってしまう。
同気相求むですね。
香辛料を控えるように、
カイロ、ストーブ、入浴
直接熱に当たる事を避け
重ね着して暖をとる。
毎晩22時には寝る!
院長から生活指導もしていただきました。
「精を蔵さずして発生する所の温病」
精を蔵さず陰虚となり「陰虚伏熱」
国試が近づくにつれ
精神的に追い詰められ疲れがピークの中、
今年は立春と卒試が重なりました。
立春になると毎年決まって発熱する私は、
インフルもコロナの大流行もあり
異常に気が立っていて
この頃から右の太白と公孫の間が痙攣し始めました。
脾が悲鳴を挙げてるのかなぁ・・・
国試が終わるとピタッと止みました。
冬から春にかけての季節の変わり目
「木の芽時」に国試や入試がある日本は酷…
治療を通して面白いなぁ〜と思ったのが、
体の変化と治療後のリズムがわかってきたことでした。
そして鍼だけで乗り切れるか、
鍼の効果を妨げないように
秋頃からサプリも漢方もやめました。
治療の翌日は、力が抜けて木偶の棒になります。
「頑張れない日」ができました。
初めは勉強できへんやんか…と
嘆いたてましたが、
ちゃんと植物が育つように大地を整えて
上にばかり行こうとせんと
大地にも根を張れるように
敢えてそうしてくれてはるんやと思うようになりました。
翌々日からちゃんとヤル気スイッチが入りました。
コロナと切っては切れない3年間、
学校でマスクを外したのは卒業式が初めてでした。
コロナ世代やと悲観したこともありましたが、
後遺症に鍼が効くことも学べました。
師との出会い
鍼師を生業としたいと夢を抱く同志
応援してくれた家族や友人
満足いく学生生活が送れました。
これからやりたかった勉強をして
早く臨床に立てるようになります。
参考文献:「温病の研究」 楊 日超著
気鬱
こんにちは高山です。
気鬱について書こうと思います。
生き物は全身に気が流れていて、いろいろな活動に使われていますが、
この気がスムーズに流れなくなってしまう状態を気鬱といいます。
イメージ的には、ホースに水が流れていて、そのホースに何かが詰まって上手に水が流れない感じ。
そして、気鬱になると、気がいくべき場所に行かない状態になるのですから、あらゆる症状が出てくるのではないかと思います。
心に気が渡らなければ、精神に異常が出たり。
脾に気が渡らなければ、代謝異常を起こしたり。
頭に気が昇らないと、頭がボーっとしたり。
あらゆる器官が気をエネルギー元に活動を行なっているので、当然たくさんの病的症状が顕著になってくると考えます。
ではなぜ、気鬱になってしまうのでしょうか、これもたくさん理由があると思います。
一つ目が肝鬱気滞。
これはよく聞きます。
肝は気の流れのバランスを整える役割がありますが、この肝が虚してしまうと、この機能が失われます。
そうすると、気の流れに異常をきたし、よくあるのが、
胸脇部の痛み、太息、など
そこから、衝任脈へ波及し、月経痛が現れる。
二つ目が、感情による気鬱。
思い悩んだり、考えすぎたりしても気の流れが悪くなるようです。
自分はよく思い悩むことが多々あるのですが、
その時は、確かに頭がボーってしたり、体が普段よりだるくなります。
そして、三つ目が痰です。
痰というのは、どろどろねばねばした塊で、この痰が気の流れを滞らせるようです。
これだけでなく他にも気を滞らせる原因があると思います。
でも、一つ目、二つ目と三つ目の気鬱の形態の違いが見られます。
肝の疎泄と、感情の異常はホースと水で例えると、
ホースに流れている水の勢いが弱ってしまっているイメージが思い浮かびます。
痰の形成による気鬱は、ホースに石が詰まってしまって、水の出が悪くなっているイメージがあります。
この考え方であるならば治療のアプローチも変わってくる気がします。
そして、気鬱の病理の変移に気鬱が火に変わるとあるのですが、これもすごく興味深いなと思います。
これは五行的に考えて、肝が心になんらかの影響を与えて、火を生み出したのかなと考えました。
気鬱になった人が全員火に変化するという事もないと思いますので、それは体質からくるのものなのかなと思いました。
自分はよく、火が昇ったように上半身が熱くなるので、この体質に当てはまるのかなと思いました。
そう考えると自分はもしかしたら気鬱傾向が強いのかもしれません。
気鬱を、解消できる方法も考えていきたいと思います。
美しさ。
東洋医学で言うと、
一般的にブラックボックス化されているイメージでした。
しかし、
林先生の治療をみて、それが改めて覆されました。
先生の治療はブラックボックス化させるのではなく、外部で症状として出ているものを、内部の原理や構造を理解し、それをわかりやすく伝える。
そしてそれに合った配穴する。
その治療に感動し、そして、美しさを感じました。
これが自分の目指す治療だなと。
生意気ですが、将来、自分にも治療ができるという根拠のない自信が湧いてきます。
想像すると、鳥肌が立つように心躍ります。
好きな人ができたような感覚で笑
好奇心と情熱を持って東洋医学に向き合いたいと思います。