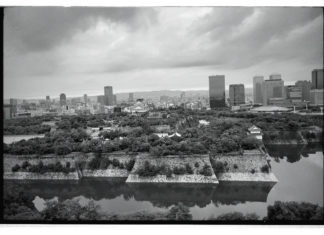フットサル・イチロー・歩き方
フットサル
週末あたりに時間を見てフットサルをする事が多いです。
その時に勉強になる事が体の確認と駆け引き。
知らず知らず走るフォームが崩れていると非常に疲れやすくなる。
どういった動き方がいいのか確認出来ます。
疲れにくい時の走り方の感覚としては、物凄い重いものを力を使わずに持っている感覚です。
そういった時は地面と一体感がある。
これを普段の歩き方にも反映させよう。
不動明王みたいなドッシリさが欲しいところです。
もう一点、駆け引きの部分。
初心者が相手DFの時は全く通じないのですが、ある程度の経験者が相手になると出方を伺う読み合いになってくる。
読み合っている中、相手に一番通じるフェイントが空気感を出すこと。
行くぞ!といった空気感を出すフェイントと動作だけのフェイントは引っ掛かり方が全く違う。
鍼を打つとき、これがいい感覚なのかむしろ邪魔になるものなのか。
試してみない事には分かりませんが、こういった事を鍼にも落とし込んでみたいと思います。
イチロー262のメッセージを読んで
とても勉強になる本でした。
イチローさんの遊び心も見えて楽しかったです。
考え方だけでなく体の使い方でも参考になる部分は多く
P207
「腕の振りは、前後だよ。
体が伝わる、体の中で振る。
中心線の中で力が伝わるよう、
そこから、外れてはならない。」
といった内容も勉強になりました。
包む感覚
人の体を触らせていただくときに大切になる感覚じゃないのかと感じています。
こう触った方が相手が答えてくれている気がします。
仙骨
ナンバ歩きとモデルのウォーキングの映像を見ました。
どちらにも共通する事は腰の落とし方と上半身の連動。
ただ感覚として掴めないのでお尻歩きで訓練中してみます。
ベッドに座る姿勢に繋げる、体幹の強化、上半身と下半身の動きの連動、体の左右のズレの矯正が狙いです。
新鮮な感覚
起きたてに自分に鍼を刺してみた。
いつもと違った感覚で新鮮で、手が運ばれた気がする。
参考書籍
自己を変革するイチロー262のメッセージ
「自己を変革するイチロー262のメッセージ」編集委員会 ぴあ株式会社
気になった文章、歴史
気になった文章
「小腹控睾。引腰脊。上衝心。邪在小腸者。連睾系。屬于脊。貫肝肺。絡心系。
氣盛則厥逆。上衝腸胃。燻肝。散于盲。結于臍。故取之盲原以散之…」
霊枢 四時気第十九
大変勉強になりました。
天台烏薬散が使われるシーンに近い気がします。
また、これも更に探っていくと別の原因にも繋がってくるので、治療方法は変えていかないといけないとも思いました。
歴史
歴史を追うと、太素が幕末の偉い人達に与えた影響は大きそうで、これを踏まえて色々見ていっています。
色々繋がってくるので面白いです。
全く別物の認識がゴロゴロ出てきて勉強になります。
生活癖
甘いものがやめられない。
それにジャンキーなものも・・・。
食べると確実に体調が悪くなるだろうと分かっているのに食べてしまう。
いったい何何でしょうか?
分かっているのにやめられない。
世の中にもそう言う人は多いのではないでしょうか。お酒やタバコもその代表かと思います。
私の場合はそう言う気分になるのは決まって夜です。
朝や昼間はそういうものを見ても何とも思わないのですが、夜になると無性に食べたくなってきます。そしてそんな時は必ず食べすぎてしまいます。
今、色々分析してみると、朝は睡眠から目覚め、身も心もリフレッシュしていて一番健全な状態なように思います。そんな時は気分も落ち着いていて穏やかで心に余裕があります。
昼間の活動時間になると、仕事モードに入り、自分の外のことに終始注意を払って集中している状態です。きっとこの時にかなりのエネルギー(気)を変に(正しくない方法で)消耗しているんだと思います。
そして夜になると何か昼間に失ったものを解消、穴埋めしたい気分になっているように思います。それが反動となって強刺激な甘いものやジャンキーな食べ物の欲に転化しているのではとの分析です。
東洋医学的に考えてみると
人の体は均衡を保とうとします。
昼間に陽気が旺盛になって、夜に陰分が充実する。
気は陰から転化してできる。
私の場合は、本能的に昼間に失った陽気を取り戻そうと夜に過食して(間違った方法)陰分を増やそうとしているのでしょうか? もともと陽気不足なもので。。
睡眠が陰分を増やす行為なら、過食するより早く寝た方が賢明ですね。
そしたら翌朝になって充電され、また心穏やかな朝に戻れるはず。
素問 陰陽応象大論篇(第5)から その3
<学生向け 近日開催予定のイベント>
【学生向け勉強会のお知らせ】東洋医学概論をモノにしよう!
→(随時お問い合わせ受付中です!)
【学生向け勉強会】「素問を読もう!」申込み受付中です
→毎週火曜19時〜 または 毎週木曜13時〜(途中からの参加も可能です。)
こんにちは、大原です。
前回の続きです。
(前回の記事→素問 陰陽応象大論篇(第5)から)
(前回の記事→素問 陰陽応象大論篇(第5)から その2)
前回は、「陰為味」すなわち
飲食物は陰(地)の気によって生じるという記述から
考察していきました。
続いて、今回は「味」と「気」が
身体にどのように作用するかについてを
陰陽で考察していく内容になります。
【原文と読み下し】
・・・
陰味出下竅、陽氣出上竅。(陰味は下竅に出て、陽気は上竅に出(い)ず。)
味厚者為陰、薄為陰之陽。(味厚き者は陰と為し、薄きは陰の陽と為す。)
氣厚者為陽、薄為陽之陰。(気厚き者は陽と為し、薄きは陽の陰と為す。)
味厚則泄、薄則通。(味厚ければすなわち泄し、薄ければすなわち通ず。)
氣薄則発泄、厚則発熱。(気薄ければすなわち泄を発し、厚ければすなわち熱を発す。)
壮火之氣衰、少火之氣壮。(壮火の気は衰え、少火の気は壮んなり。)
壮火食氣、氣食少火、壮火散氣、少火生氣。(壮火は気を食らい、気は少火に食らい、壮火は気を散じ、少火は気を生ず。)
氣味辛甘発散為陽、酸苦涌泄為陰。(気味の辛甘は発散して陽と為し、酸苦は涌泄して陰と為す。)
1行目ですが、
味(身体を作る飲食物)と気(身体を動かすための力)は、
味は有形なので身体の下竅(=尿道・肛門)へおもむき、
気は無形なので身体の上竅(=目・耳・鼻・口)へおもむく、とあります。
この関係からすると、味と気を陰陽で分けると、
味は陰で気は陽となります。
そして2〜3行目、
厚い味は陰で、薄い味は陽、
厚い気は陽で、薄い気は陰であると続きます。
すなわち、味は陰に属するので、
厚い味は陰中の陰、薄い味は陰中の陽であり、
気は陽に属するので、
厚い気は陽中の陽、薄い気は陽中の陰である、とあります。
これは
陰が厚くなればさらに陰に傾き(=陰中の陰)、
陽が厚くなればさらに陽に傾く(=陽中の陽)ということです。
気や味について陰陽の分類がなされていますが、
これらをよりイメージしやすくするために
次のように具体的な食材を考えてみました。
(私のイメージですが・・・)
・厚い味 → 濃い味の食べ物:ラーメン、スイーツ、お酒のおつまみ、・・・
・薄い味 → 薄味の食べ物:おかゆ、豆腐、生野菜、だし汁・・・
気についても、飲食物で喩えてみると分かりやすいかも知れません。
・薄い気 → 程良い温度の料理、水、番茶、・・・
・厚い気 → お酒、熱々の料理、わさびなど鼻がツンとする薬味、・・・
といったところでしょうか?
これらが体内ではどのように働くかが4〜5行目にあります。
味厚則泄、→「泄」は泄瀉で下痢のことです。
薄則通。→「通」は気血がよく通じるということでしょう。
氣薄則発泄、→「発泄」とは発汗ということだと思います。
厚則発熱。→「発熱」はそのまま熱を発するということでしょう。
6行目から、「少火」と「壮火」という言葉が出てきます。
「壮火」とは壮(さか)んな火で、「気を散じ」とあることから
過度な陽気を表していると解釈され、これに対し、
「少火」とは「気を生ず」とあることから
正常な陽気を表していると解釈されます。
喩えると、
正常な体温ではなく、発熱した状態が続くと
体力が消耗してしまうようなことだと思います。
最後の行では
味の性質についての説明で
辛甘は発散する性質があるので陽、
酸苦は涌泄させる性質があるので陰、
とあり、五味の性質が書かれています。
「涌泄」とは吐下の作用すなわち
吐かせたり、下したりする作用をいうようです。
さて、五味の性質を陰陽で分けていますが、
なぜこのように分類されるのでしょう?考えてみます。
「辛」→ 働きは「散」 → 発散に働く → 陽
「甘」→ 働きは「緩」 → 気を緩める → 停滞している流れを動かす → 陽
「酸」→ 働きは「収」 → 引きしめる作用 → 陰
「苦」→ 働きは「堅」 → 固める作用 → 陰
(五味の働きについては
前回の記事→素問 陰陽応象大論篇(第5)から その2 を参照ください)
ということでしょうか。
また、五味にはあと1つ「鹹」がありますが
ここでは述べられていません。
考えてみますと
「鹹」→ 働きは「軟」 → 柔らかくする → 陽
となるかと思います。
味や気について、身体への作用を、
陰陽で考察してきました。
全体として抽象的な内容ではありますが、
自分なりに具体例を考えていくと面白いかも知れません。
参考文献
『黄帝内経 素問』 東洋学術出版社
食べることについて②
皆さまこんにちは、イワイです。
前回の続きです。
〝後天の精〟とは生まれ持った〝先天の精〟とは別に
飲食物から補います。この後天の精の全身へのルートをみてみますと、
後天の精
↓
別名 水穀の精微といわれる
↓
一部は気、血に化生→全身の組織、器官に行き渡る
↓
残りの一部は 腎 に収まる
となっています。
次は〝精〟の作用についてです。①〜③
①生殖
②滋養→人体の組織、器官に滋養する
詳しくみてみると、
精は必要に応じて、血へ変化。
↓
血も旺盛、正常に各組織、器官を滋養。
精は気へ化生。
↓
人体の新陳代謝を推動、抑制し生命活動を維持する。
精は人体を構成する基本物質と捉えられており、
東洋医学では精が充足していると、
生理機能は正常に働くと考えられています。
③神の維持
神:広義では、生命活動の総称であり、精が充足することで、神の機能が保たれる。
狭義では、精神、意識 、思惟活動を主るもの。
ここからは、勉強した感想です。
飲食物を食べることで、西洋医学的に考えるとエネルギー源となるということ、一方で東洋医学的に考えると、エネルギー源という役割と五臓六腑が正しい働きを出来るようにしていたり、精神活動も主ることになるので、幅広い意味で捉えることが出来ることに気づきました。
【参考文献】
『新版 東洋医学概論 』東洋療法学校協会
鍼治療をうけて②
2021/04/07
週に1回の治療
すっかり不眠の症状が表に出て来なくなった。
今週は体調が良く、下半身が軽いと感じていた。
歩く体が軽い
すいすいと動く
軽いのに力が入る
そういえば...と思い出した。先週は腹の調子が悪かった
今回の治療中に、体調について聞かれて、
腹の調子が悪いと自分が訴えていたことを思い出した。
先週 水曜日あたりに普段の量より多く食べる機会があって、それからのことだった。
とにかくガスの量が著しくて、便の出方はでたらめ、排便の周期もばらばら。
食事は食べれるし、出せるけどずっと(下痢や便秘はなく)軟便気味。
脾胃の気に一定の損傷が起きていることは明らかと感じられた。
パンクしたタイヤを交換せずそのままに走っているから、
車内でガタガタと揺れがひどい、まるでそんな有り様だった。
それも今、整えられている
今回の治療中には、何度も深い呼吸が起こった。
からだが積極的に欠伸を、深呼吸をしにいっているみたいに起こった。
ただ普段でる欠伸に似ているけど違う。
勢いよく吸って吐いてとやっているけど、自分が意図的にやる時の深呼吸とも違う。
(この前記録に残した、なにか栓が外れて空気が抜ける様な、あのときのとも違う)
結局、治療を終えて体を起こして動き出すまでその深い呼吸が続いた
気の巡り方は、体表を動くというよりじんわりと中にという感覚
腹部には湧いてくる様な動き
(気が満ちるというのはこういうこを指すのか)
欠伸の時の様に涙が出た。じわりと出る、それが何度も続くので
流れ出たあとが温かく
お腹が温かく
手と足が充実している
体の各所に温もりがあって、一瞬
のぼせの症状が出る体調の時の五心煩熱が想起されたが
手と足と、胸 じゃなくて腹。
それから温かさの種類が違う、対極とさえ感じる
(こちらの状態を指す言葉はあるのだろうか?)
________________________
これまで鍼を受けたことがないという人から
鍼はどんなだと興味を持って聞かれることがあり、
こうした感覚を載せて伝えられないものか考えた
自然治癒力という言葉で表すのでは全然足りない
からだそのものの力を持って癒える
体調が戻ったあとこそ自然を知る
紙飛行機がふわりと着地する光景が似合う
中国の思想(01)
老子
一章 真理は固定したものではない
道可道、非常道。
名可名、非常名。
無名天地之始、有名万物之母。
故常無欲以観其妙、常有欲以観其徼。
此両者同出而異名。
同謂之玄。
玄之又玄、衆妙之門。
道を可とする道は、常なる道に非ず。
名を可とする名は、常なる名に非ず。
無は天地の始まりの名、有は万物の母の名。
故に常なる無は其の妙を観さんと欲し、常なる有はその徼を観さんと欲す。
この両者は同じ出にして名を異とする。
同じく、これを玄と謂う。
玄のまた玄を、衆妙の門とす。
【参考文献】
『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店
側・舌
側
豊中院で先生の身体をみさせて頂いた。
先日寺子屋でここを見といてくださいと言われた部分に反応があった。
中に差し込んでいる様な形。
背候診の時もついでに触って様子を伺う。
停滞している印象。
少陽枢機不利が原因かと思った。
舌
今日患者さんの問診、切経などさせて頂いた。
その患者さんを含めて思う事。
舌を見て、
「子供の様な舌だな。」
と思う方がちらほらいる。
このあたりは持って生まれたものではなく、臓腑の現れ方として共通するものがあると思う。
水の溢れ方も特徴的。
切経で
切経で、
ある方の背中を見せてもらったときに
肌の表面の質感が、まるで境界線が引かれた様に
その上下ではっきりと異なる様を見た。
境界線は、左右はそれぞれ肩甲棘に沿う様に見られ、
脊柱に近づくにつれ、より下方まで伸び脊柱で合する。
胃脘部のムカつきを主訴とする方で、
境界線の上方だけで、毛穴が一様に広がっている。
内部にこもる熱が体表に表れていると見てよいのものなのか。
前回(ひと月前)には気が付かなかった。
これからの経過とともに見守りたい。
勉強会など
先日勉強会で症例検討を行いました。
その際に気になった点を書いていきます。
舌
状態から考えて陰液の欠乏、熱、正気の弱りが考えられる。
脈
Oさんから教えていただいた感覚から
瘀血、虚熱、正気の弱りが伺えた。
切経も含めて、まずは脾と胃の関係を考え直したい。
また、症状からして脾気虚を原因とした脾陰虚の様なニュアンスも感じます。
これが原因で病理産物も生成されたのか。
現代語訳 黄帝内経素問上巻 太陰陽明論篇
「四肢は皆気を胃に稟くけども、経に至ることを得ず。必ず脾に因りて、乃ち稟くることを得るなり。
今 脾病みて胃の為に其の津液を行らすこと能わざれば、四肢水穀の気を稟くるを得ず。」
「黄帝がいう。「脾と胃とは、一つの膜を挟んで連ねているだけであるが、脾が胃に変わって津液を輸送するというのはどういう理由か。」
岐伯がいう。
「足の太陰脾経は、三陰と言いますが、その経脈は胃を貫いて脾に連属し、咽喉を絡っています。
このため太陰経の脈は胃の水穀の精気を手足の三つの陰経に送ることができるのです。
一方、足の陽明胃経は、足の太陰脾経の表にあたり、五臓六腑の栄養の供給源です。
このため太陰脾経が胃に変わって津液を送るといわれています。
五臓六腑はいずれも脾経を経て胃の水穀の気を受けています。
このため太陰脾経が胃に変わって津液を送ると言われています。」」
切経から陽明の熱の様な存在も気になったのですが、脾が立て直され陰液が生成される様になれば自然と落ち着くのか?
上の文、気になったので書き残します。
他に瘀血のできる位置もとても勉強になりました。
課題
相手を感じれた?時なんとなく相手の気持ちが移ってきて同じ様な状態になる事が少し増えたのですがこれはまた自分の課題とするところと違うのか。
良い事なのか悪い事なのかわかりませんし、一向に問題をクリアできていないのですが今までにはなかった感覚なので新鮮です。