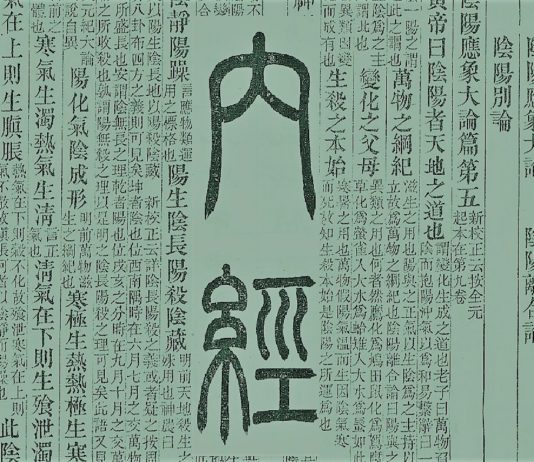夏越祓
毎年この時期になると、家のポストに上の写真にある封筒が入ります。
封筒の裏には
夏は暑気のため、ともすると心身ともに緩みが生じます。
その心の隙に乗じて、伝染病が流行ったり、心身衰惰の結果、職場で思わぬケガや災害等に襲われます。また、お子様の海水浴など、毎年水の犠牲も少なくありません。こういう事は全て一括して神道では穢(けがれ)の現れと申しております。
この穢を祓うために神に詣でて、ご守護を願うのが夏越の祓、または夏越の祭りといい、後に略して夏祭りと言うようになりました。
この袋の中に入れてある人形(ひとがた)は、私どもの身代わりとして、知らず知らずに犯した罪や穢を払い清々しい心身に清めてくれる「呪符」の役目を果たしてくれるものですありますから、来る7月9日、10日の輪くぐり夏越し祭りに、当日この人形に年齢、姓名を書いて、神社へご持参ください。
また、古来の慣例に依り社頭には芽の輪が作ってありますから、これをくぐってこの夏を無病息災に過ごしてください。
とあります。
面白い風習です。
この人形に自分の身体についた穢れをあちこちを撫でて移し、最後に息を吹きかけて、心の穢れと合わせて自分の身代わりになってもらう。
段々こういったことも、真剣に信じるようになってきました。
そして、こちらの神社にも「茅の輪」も設置してくれています。
これをくぐれば心身ともにキレイになると同時に、悪霊退散・疫病退散といった効果がある
とのことです。
「茅(ちがや)」はイネ科の植物で、葉先が尖っていて「茅」に似ているため、茅は悪霊を取り除くとされていたことが背景にあるそうです。
尖っているものとしては、鍼灸で使う鍼もまさしく尖っているものの何者でもありません。
今日はちょうど日曜日なので、参拝できそうです。
舌診(03)
受付のKさんに舌の研究の為にご協力頂きました。
飲食物の影響による舌苔が染まる、
いわゆる”染苔”をさける為に、わざわざ調整していただきました。
表
裏
舌質
舌神:有神
舌色:淡白舌
舌形:嫰・胖大・歯痕・点刺
舌苔
苔色:白苔
苔質:全苔・薄苔
舌診(08)
治療家のT先生に舌の研究の為にご協力頂きました。
舌を撮影させて頂く時は、
念のために表だけで2枚、裏だけで2枚撮影します。
色調の違いを考えて今回はこの画像を選択しました。
表
裏
舌質
淡白舌
嫰・点刺・歯痕
舌苔
白苔
全体・薄苔
仕事終わりに撮影をさせて頂こうかと思っておりましたが、
時間がありましたので、業務の前に撮らせて頂きました。
舌尖の紅が痛々しいですが、”朝” というのも要因の一つかと思います。
裂紋が出来てからかなりの時間が経過しているのかと思います。
T先生の舌は昨年より診させていただいておりますが、
瘀斑の境目が緩やかに感じます。
状況により変化があるのでしょうが、
安定している好転反応を感じます。
肺陰虚証を勉強していて思った事2
乾燥する、という部分について思うところがあったので書いていきます。
咳をし過ぎる:
水分を失っていき乾燥する。
肺が乾燥し肺の熱が上逆することで咳になり、下気道、上気道、口腔内が
熱を受けて乾燥し、乾咳がでる。
津液が減るため?痰はない、または少量。
しゃべり過ぎ、エアコン、喫煙によっても乾燥する、また
久病によっても身体の潤いが失われることがあるとのこと。
煙が陽熱にあたり、その熱で乾燥すると聞きましたが
煙にあたることによって熱を受けるということなのか、それとも
煙を身体に取り込むことによって肺が熱を受けることなのか。
灸実技の授業で教室が煙だらけになっているときは、すごく
陽熱にあたっているということになるのか?
脾で作られた津液が肺にいき、乾燥により、粛降機能が働かなくなると
大腸や腎に影響がおきる。腎は根源的な陰をもつといわれていて
そこが働かなくなることで、再利用できる津液を上昇させることができず
肺や全身に津液を運べなくないために熱を持った肺を冷ますことができなくなる。
肺は津液が少なくなってもひたすら上気道や体表に運んで発散させる。
(この機能は熱で弱まったりしないのでしょうか…?)
腎は再利用できない濁は膀胱を通じて尿となって排出される。
(再利用できる出来ないは、腎の機能?作用?の具合にも関係がある?)
身体が乾燥する病は「痩せる」場合が多いということですが
津液が減り、身体に潤いが足りないためにやせるということは
身体が海藻のように乾くと干からびていくような感じなのか。
色々考えていたら肺陰虚証を忘れそうになってきました。。
実験、公孫など
珈琲
私はコーヒーが合いません。
香りや苦味が好きなんですが、身体に合わない。
自分の感覚として体感しているのは肝の暴走。
散々書籍にあることなので発見でも何でもないのですが、体感としても感じます。
じゃあ、それを思いっきり飲んだらどうなるか。
ボトルコーヒーを一本一気飲みしてみた。
自分の体の反応と術者としての感覚を飲む前、飲んだ後と比較してみました。
術者として
普段から鋭くない感覚が更に鈍くなる。
全く相手を感じる事ができない。
身体を触らせて頂く時に頭に言葉が多くなる。
体感として
自意識が強くなる。
ナポレオンはコーヒーを勇気の出る飲み物として愛用していたらしいのですが、鈍感になっただけじゃないのか。と思った。
また、時間差があるので直後には出ない。
ただ影響がマックスになった時、酒で酔った感覚になる。
調べるとコーヒー酔いというものもあるらしいです。
気逆を起こすと気が大きくなる?
脈の寸には影響があった気がします。
頭には色んな言葉が浮かぶ様に。
エゴが強くなった感覚?
いつも以上に自分の世界だけで全てを完結させている気がしました。
家に帰って自分の肝経の経穴に鍼をしてある程度は和らぎましたが、躁鬱状態ってこんな感じなのかなと思いました。
手に受ける感覚
何か違和感を感じたとして、それぞれ種類が違ってくる。
細分化して言語化できればいいなと思いました。
体感として一つ重い感覚はあったので、まずはそれについて考えていく。
切経
術者と患者が合った時、そこに囚われ過ぎるのは良くないと思いました。
ベタベタ触ると段々反応も薄れ、よく分からなくなってくる。
即時即決、一回でどれだけ情報を頂けるか。
患者とどの様な意識で向き合うか、模索します。
深さも意識したい。
公孫
この穴の認識を深めたい。
奇経八脈考、症例から学ぶ中医婦人科などを中心に調べているのですが、まだイメージが掴めていません。
引き続き調べて行きます。
楽しむこと
表面的なものではなくて、この本質って何なんだろう。
考える事で遠のいていっているかもしれないけど、一旦はこの工程を踏みたいと思います。
はじめましてのご挨拶
はじめまして。鍼灸学校2年生の赤澤と申します。
一鍼堂さんで治療を受けたことをきっかけに鍼灸治療に興味を持ち、
仕事を辞めて思いきって鍼灸の専門学校に入学したものの
入学してからもコロナ禍で授業が中断されることが度々あり、現在もオンライン授業がメインで
なかなか通学できず、実技授業も思うようにできていないという現状に
何をしに学校に入学したのか心折れかけることが多々ありますが、
文句をいってもしょうがないので、今自分にできることに目を向けて、
卒業まで取り組んで行こうと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
最近の興味
最近、水に興味を持ち始めました。
今までは普通に蛇口からの水道水を飲んでいました。
時には浄水器を通してアルカリイオン水や水素水にしたりして飲んでいた時期もありましたが、最近はその土地でしか飲めないお水に興味があります。
ネットで調べてみると、様々な種類の水があるのですね。
湧水
地下水
温泉水
ゲルマニュウム水
海洋深層水
伏流水
などなど
全国各地の名水と言われているお水が、ワンクリックひとつで自宅に届けらけるとはありがたい世の中です。(配達員の方々有難うございます)
水は健康を語る上で、必ず出てくるキーワードと言えます。
「身体の半分以上は水分でできている」
「その半分以上の水をよい水に変える事は非常に重要なことである」
これはよく聞く鉄板の言葉だと思います。
また東洋思想では、
「天一水を生ず」
とも言いますし、世の中を作る最初は水からを→身体をつくる最初は水からと置き換えて考えてみることにします。
また今の世の中は防災にも備える必要があるので、水の備蓄にも役立つのではないかと思います。
脾の運化について
今回は、五臓の脾の働きのひとつ、運化について整理しました。
脾は中焦にあって
気や血を生み出す働きを担う。
脾は運化を主る、と表される。
どのようにして気血を生むのかーそれは毎日の食事を通して行われる
運化の意味はー運ぶこと、変化させること
脾の運化にはざっくりと次のふたつの側面から成る。
飲食物を消化・吸収して得られた水穀の気をからだ全体に運ぶ(運化水穀)
そして、飲食物の消化・吸収・運搬を通して、からだ全体の水の流れを調節する(運化水液)
脾が弱ると消化・吸収が正常に行えなくなる、気や血が足りなくなる。
そして、運化水液の働きが弱り、からだに停滞する。
食べることで体が作られ維持される、
それは生きる為の土台になる。
別の視点では、
エネルギーや栄養を運ぶ働きを担う脾胃が元気だからこそ、
そのほかの臓腑もしっかりと働ける。
そして、臓腑や器官に必要な水液が届けられる(排出が行われる)
ー「後天の本」「気血生化の源」
肺は呼吸を通して、気という、より軽いものを扱う。
脾は運化を通して、地の気や水液をからだ全体に送り巡らす。
階層は違えど必要不可欠なふたつが、上焦と中焦で働いている。
どのように関わり合いながら機能しているのか、
今後、深めていきたいと思います。
____________________________________________
【参考文献】
『中医学ってなんだろう』東洋学術出版社
裂紋舌の深浅
裂紋舌の深浅について考えてみた。
舌診を覚える時、水田に例えたりしていた。
水分量を表す裂紋舌は水分や養分のない干からびた土と似ている思う。
昔、真冬の田んぼに落ちたことがあるが、表面は地割れして硬かったが、まだ中に水分が残って下の層はほんの少し柔らかかった。ただ、キメがなく、酸欠状態の土だった。
そのまま放っておけば、やがて休耕田のようにカラカラに乾燥し、深く亀裂の入った硬い地面に変わる。
裂紋舌の深浅や舌質の剛柔は、水分量や病の進行具合を示す指標になるのではないのかと思う。