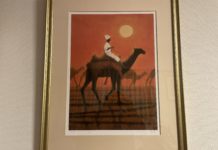患者、食べ飲み など
患者
今週寺子屋で見せて頂いた患者さん、もし自分があの人ならどういう気持ち、体になるか。
声や様子から色々気にされそう。
治療してなかったら心臓が心配だな。
生殖器関係に問題はないかな。
気逆を起こして気にされやすいだろうから、言葉遣いはどうした方がいいかな。
敏感そうだから特に時間をかけたらいけないな。
拾えなかったけど本当に心経の辺りに反応がなかったんだろうか。
あの状態なら出やすいと思うんだけれども…
食べ飲み
先日友人の結婚式があった。
そこでのスケジュールが11時〜披露宴 15時〜二次会 と言った胃腸にとってのハードスケジュールだった。
家に帰ってお腹を触ると胃がパンパン。
足では地機が硬くなっていた。
浅めに刺しても痛かったのですが、腹満は楽になりました。
舌の変化も見ていたのですが、翌日の変化など特に勉強になりました。
また、大人数は大変だなと改めて実感。
自分の課題です。
感覚
本を読みながら何かを触る。
何も見ずに何かを触る。
感覚が全然違う。
触覚だけでなく、全ての感覚がそうだと感じる。
今、きちんと周りの音を拾えているか?
それがノイズの様に聞こえるか、キチンと聞こえるかは自分の状態によって違う。
そこを聞こうとすれば別のものを拾い溢す。
こちらから行くべきじゃないんだろうな。
結局それが何なのか?とその場で気にしてる時点でダメなんだと思います。
実験
↑の事を考えていて、先週の寺子屋ではできる限り周りの状況観察に努めてみた。
やり始めの少しの間はいい感じだったのですが、ずっとやっているとしっくりとこなくなりました。
停滞するといい感じじゃなくなる。
一気にその場の空気とのギャップが出てくる感じがしました。
理論から実践しようとしましたが、これは無理だなと痛感。
実践から理論なら可能なんだと思います。
経穴
勘違いかもしれませんが、その穴に対してどういう認識を持つかで効果が変わってくると、何となく感じた出来事がありました。
補寫といった話ではなく、刺し方でも全く違う目的になるのではないのかなと感じています。
背中
知り合いの身体を借りれたので刺させて頂いた。
普段は腹などでみますが、その時は背中で変化を追ってみた。
脾募と脊柱など一致する部分が見られて勉強になりました。
素問 陰陽応象大論篇(第5)から その2
<学生向け 近日開催予定のイベント>
【学生向け勉強会のお知らせ】東洋医学概論をモノにしよう!
→(随時お問い合わせ受付中です!)
【学生向け勉強会】「素問を読もう!」申込み受付中です
→毎週火曜19時〜 または 毎週木曜13時〜(途中からの参加も可能です。)
こんにちは、大原です。
前回の続きで、「素問を読もう!勉強会」でも
少し触れた内容になります。
(前回の記事→素問 陰陽応象大論篇(第5)から)
前回は、素問 陰陽応象大論篇(第5)の中の
人体を構成するものの、
それぞれの相互転化についての記述について
考えていきました。
↓この一連の流れが重要であるという読み方をしてみました。
「味」→「形」⇄「気」→「精」⇄「化」
さて、素問の記述では、
最初の「味」は「陰」によって生じるとあります。
(「陰」→「味」)
もう一度原文を確認してみましょう。この2行目にあります。
【原文と読み下し】
・・・
水為陰、火為陽。(水は陰となし、火は陽となす。)
陽為氣、陰為味。(陽は気となし、陰は味となす。)
味帰形、形帰氣、氣帰精、精帰化。(味は形に帰し、形は気に帰し、気は精に帰し、精は化に帰す。)
精食氣、形食味、化生精、氣生形。(精は気に食(やしな)われ、形は味に食(やしな)われ、化は生を生じ、気は形を生ず。)
味傷形、氣傷精。(味は形を傷り、気は精を傷る。)
精化為氣、氣傷於味。(精は化して気となし、気は味に傷らる。)
・・・
2行目の「陽」や「陰」とは何を指すのかというと、
「陽」とは「天」のことで、
「陰」とは「地」のことであると、
この文章の前の部分の文脈から解釈できます。
すなわち「味」である飲食物とは、
「陰」すなわち大地のエネルギーによって
生じるということになります。
(「エネルギー」という言葉以外に良いキーワードが思い浮かびませんでした。
他に何か良い訳し方があるでしょうか、教えてください。)
形(肉体)や気、精は、正しい飲食によって得られると
前回の記事でまとめましたが、
さらに正しい飲食とは、
しっかりした大地のエネルギーから生じるということになります。
ちなみに、これらをまとめると
「陰」→「味」→「形」⇄「気」→「精」⇄「化」
となります。
現代の食生活における食材は、
大地のエネルギーをしっかり得たものかというと
そうとも言いきれないのでは?と感じてしまいます。
例えばインスタント食品や人工的に作られた調味料などは、
大地のエネルギーがほとんど無いのではないでしょうか。
また、旬のものでない野菜も
現代はビニールハウスなどによる栽培技術によって
手に入りやすくなっていますが、このような季節外れの野菜は
しっかりと栄養がとれるのでしょうか?
素問の内容から、そのような疑問をふと感じてしまいました。
(現代の農業の技術に関して私は全くの素人ですので、
このような疑問が間違ってましたら謝ります、すみません。)
参考までに、
「五味」の働きについての記述もこのあと出てきます。
辛散、酸収、甘緩、苦堅、鹹耎。
辛は散じ、酸は収め、甘は緩め、苦は堅くし、鹹は耎(やわ)らかにす。
(『素問 蔵気法時論篇』(第22))
さらに、
五味所入、
酸入肝、辛入肺、苦入心、鹹入腎、甘入脾、
是謂五入。
五味の入る所、酸は肝に入り、辛は肺に入り、苦は心に入り、鹹は腎に入り、甘は脾に入る、
是(こ)れを五入と謂(い)う。
(『素問 宣明五氣篇』(第23))
五味の働きについては
現代の薬膳関係の書籍に書かれていますので、
薬膳に興味がある方はご存知かも知れません。
ですが、例えば、
いくら酸味や甘味のある食材を用いて調理したとしても、
その食材にしっかりとした陰がなければ、
味覚としては酸味や甘味を感じたりしても、
実際には身体を養うような本来の食物としての作用が
発現されないのではないでしょうか。
五味は大地のエネルギーから生じるという
原則的な内容について書かれた書籍は
個人的にあまり目にしたことがありませんが、
重要なことのように思います。
参考文献
『黄帝内経 素問』 東洋学術出版社
素問 陰陽応象大論篇(第5)から
<学生向け 近日開催予定のイベント>
【学生向け勉強会のお知らせ】東洋医学概論をモノにしよう!
→(随時お問い合わせ受付中です!)
【学生向け勉強会】「素問を読もう!」申込み受付中です
→毎週火曜19時〜 または 毎週木曜13時〜(途中からの参加も可能です。)
こんにちは、大原です。
素問の勉強会では、現在
陰陽応象大論篇(第五)の内容を読み解いていっております。
さて、素問 陰陽応象大論篇(第五)の中に、
気(人体を動かす力)、
形(肉体)、
味(飲食物)、
精(生命活動を維持する源泉)
それぞれの相互転化についての記述があります。
その原文と読み下しは以下になります。
【原文と読み下し】
・・・
水為陰、火為陽。(水は陰となし、火は陽となす。)
陽為氣、陰為味。(陽は気となし、陰は味となす。)
味帰形、形帰氣、氣帰精、精帰化。(味は形に帰し、形は気に帰し、気は精に帰し、精は化に帰す。)
精食氣、形食味、化生精、氣生形。(精は気に食(やしな)われ、形は味に食(やしな)われ、化は生を生じ、気は形を生ず。)
味傷形、氣傷精。(味は形を傷り、気は精を傷る。)
精化為氣、氣傷於味。(精は化して気となし、気は味に傷らる。)
・・・
原文三行目から、
体内での転化について述べられていますが、
どのように起こっているのかを原文通り順番に読んでいくと、
一見このようになります。
味帰形、 「味(飲食物)」→「形(肉体)」
形帰氣、 「形(肉体)」→「気(人体を動かす力)」
氣帰精、 「気(人体を動かす力)」→「精(生命活動を維持する源泉)」
精帰化。 「精(生命活動を維持する源泉)」→「化(必要な気血などを他の物質から変化させる作用)」
さらに4行目以降も転化についてですが、
精食氣、 「気」→「精」 (「精」は「気」によって食(養)われる、という意味から)
形食味、 「味」→「形」 (「形」は「味」によって食(養)われる、という意味から)
化生精、 「化」→「精」
氣生形。 「気」→「形」
となります。
矢印は、物質などの生成の向きを示していますが、
「形」は「気」を生成したり(原文3行目)、「気」は「形」を生成したり(原文4行目)、
また「精」は、「化」を生み出し(原文3行目)、反対に「化」から生成される(原文4行目)とあり、
チャート図のように読んでしまうと、
混乱してしまう印象を受けませんでしょうか?
ですが、ここでのポイントは、
これらの相互の関連は
その調和が保たれているということが重要だということだと思います。
「気」→「精」などのようにそれぞれ別個で抜き出すのではなく、
これらをまとめて、
「味」→「形」⇄「気」→「精」⇄「化」
のように表してみると、「気」について、
例えば次のように意訳できると思います。
「飲食物を得た肉体からは「気」が生じ、
その「気」が充実していると生命活動の源泉である「精」も充実してくる。
その「精」が充実してくると、飲食物から体内に必要な気血を化する作用を生みだす。」
このように、単に、肉体から「気」が生じるというのではなく、
飲食物を得て充実した肉体から「気」が生じるという、
一連の流れが重要なのだと思います。
同様に、単に「気」から「精」が生みだされるというのではなく、
飲食物を得て充実した肉体によって気が生みだされ、
(肉体や気が充実するためには飲食物もしっかりしたものが必要だと思いますが)
その「気」が充実してくると「精」が生みだされるということだと思います。
一連の流れが重要だということだと思います。
以下に、参考までに、上の原文の意訳を記します。
【意訳】
水は陰であり、火は陽である。
火である陽は、人体においては気であり、
水である陰は、飲食物(味)である。
飲食物によって肉体(形)は形成され、
飲食物を得た肉体からは気が生じる。
その気が充実していると、生命活動の源泉である精も充実してくる。
その精が充実してくると、体内に必要な気血に化する作用を生みだす。
すなわち、精を作り出すには気を消費し、
肉体は飲食物を得ることで成り立っているのである。
また、化する作用によって精は生まれ、
気によって肉体ができるともいえる。
しかしながら、これらの相互関連は、その調和が保たれている場合にうまくいくのであり、
飲食の不摂生・偏った飲食があると、その飲食によって肉体はかえって損傷され、
肉体が損傷するので気も弱り、気から充実するはずの精も傷られることになる。
まとめると、正しい飲食からは肉体や気が充実し、さらに精をも生み、
精が充実していくると気も充実してくる。
反対に飲食の不摂生や偏った飲食は肉体や気が弱り、
精を作り出すこともできなくなるということである。
すなわち気は精をよりどころとしているので、飲食の不摂生によって障害されるのである。
心に汗をかくと涙が出る
私はいつも電車で通勤しています。
先日、朝の通勤時に本を読んでいたら、たまたま文章の感動シーンとぶつかってしまい、不覚にも涙と鼻水でデロデロになってしまいました。
この頃はコロナ禍で常時マスクをしているので、鼻水はあからさまに見えずに済んで助かりましたが、マスクの中はひどい状態でした(笑)
その時、何故急にさっきまで何ともなかったのに、一瞬で涙と鼻水が溢れるんだろうと不思議に思い、ちょっと考えてみることにしました。
涙と鼻水(涕)
五行色体表で考えると
木と金→肝と肺→魂と魄
もしかすると感動などで心(神)が乱れて正常心を保てなくなるのを防ぐため、魂と魄が代わりにその感情を浄化させるために涙や鼻水として体外へ排出するのではないかと考えました。
七情が臓気を損傷し、心神が乱され、異常反応が現れれば、それとともに魂病が出現する。魂魄は依存し合い、分離することができないので、また両者の異常が同時に存在することがよくある。〜中医病因病機学〜
という一文を見つけました。やはり涙と鼻水はセットになりやすい、切っては切れない関係のようです。
夙川にて
図書館、公民館など、外で勉強する事が殆どです。
好きな場所で、夙川沿いの静かなところに”西宮市立中央図書館”があります。
休憩に川沿いで新鮮な空気を吸うのですが、ふと思い出した事がありましたので。
以前に、六甲山からの鉄砲水で犠牲者が出たことがありました。
その時に『山上が曇れば大蛇が通る』という伝承を知ります。
古人が鉄砲水を大蛇に例えて後世に伝えやすくしたのだと思います。
それをきっかけとして、スサノオノミコトがヤマタノオロチ退治を
”治水対策の比喩”であるとの仮説にも出会う事になりました。
クラスメイトが話の中で「東洋医学=スピリチュアル」との認識に違和感を覚えたのを覚えています。
東洋医学を学ぶという事は災害の地に建つ石碑のように、
古人が未来へ向けた思いに耳を傾ける事のように思います。
とか、思い出しながら国家試験に向けての勉強の年末です。
忘備録として。色の見方。
鍼灸学校3年次に、国家試験に備えて過去問や練習問題にあたる中、
東洋医学の勉強の素材としてそのままでは受け入れにくい内容のものにあたることが多かった。
その中の一つ。
3人の子を出産した女性に、出産後表れた症状群から腎虚を導き、解に繋げる。
問題の解説として、単純に出産で腎を消耗したことが原因と結ぶ教師の言葉には荒っぽい印象しか持てなかったが、
そんな単純な構図では説明できていることにならない、と考える一方で、
3人出産して、ひとりの女性として持てるものを “割と” 消耗しているということは言えそうだ、と考えていたのも事実。
「3人産む」ということがどんなものなのか、図る尺度はない筈なのに、そう考えていた。
少なくとも、あの時、違和感の焦点はそこだった。
つい最近になり、別の視点を得る。
先日、母方の親族と顔を合わせる機会があり、年齢の近い従兄弟とその祖母の話になった。
今年99歳になる祖母は5人の子供を育てあげ、それぞれが孫をもうけて大家族になった。
彼女は80代で自分の意思で施設入所を決めて、実際に入所するまでは自分で車も運転したし、
海外へ旅行することを好んであちこち足を運んだ。
何より99歳の現在でも背筋が真っ直ぐで自分のことは大抵自分でなされるそうだ。
(その祖母はといえば8人兄弟とのこと)
小学生の頃に、社会科か何かの授業で各々の家族構成について発表、それを題材として、
今と昔の違いについて話しあった場面のことが不意に思い出された。
その当時(30年ほど前)僕の田舎では子供は2〜3人が一般的でひとりっ子はまれだった。
授業では「昔は子供はたくさん」いて、一家に子供が6人とか8人とか珍しい話でもなかったと教わった。
確かにそう教わっていたのに、実感を持って思い出すのに時間がかかるくらい、現在の情報、周囲の環境に
どっぷり浸かっていることが自覚された。
「3人」という数がもたらす意味が変わる。
以前、先輩の先生から中医学を学ぶにあたり「中国と日本では色の見え方から違っていること」について留意するよう
助言を頂いたことがあったが、その意味の理解が少し進んだ様に感じられる。
忘備録として記録
舌の考察 2023/11/22
最近は舌の考察を寺子屋生どうして写真をとってみたりして行なっています。
今までこんなにじっくり舌を観察する機会がなかったので、やはり勉強になるなと改めて思っています。
自習の方では難経鉄鑑の34難まで進みました。
以前読んだ時は33難が難しくて、一体何のことを言っているのかチンプンカンプンでしたが、今回改めて読み返してみると何となく全体像を理解できたような感じになり、繰り返し読み返す意味を再確認することができました。
舌質 胖大 やや淡白より。
厚みがあって、パンと張った気が充実している舌で、気滞があるのかなと思われる。
しかし舌尖の赤味が他の2人とは違ってみられない。
舌苔も薄く消化管も問題なさそうに見える。
舌の張り感がなく、だらんとした気が抜けた舌。
舌苔は粘稠で厚みがあり、低速モードで消化管の働きが追いついてない。中焦、下焦に停滞している。
備考:生理が終わって、口周りの吹き出物の活動が治ったように思う。
上の2人に比べると、舌の色が暗く、鮮やかさに欠ける印象をもつ。
舌の弾力性も以前の写真に比べると低下している雰囲気がして、気虚が増したように感じる。
舌裏も白抜け感があり、まだらで血の停滞が見られる。
変えてみること
ここ一週間、歩く際に使う筋肉、重心の乗せ方を変えてみています。
続けてみるとふくらはぎ、内転筋の筋肉のつき方が変わって面白いです。
日常的には以前仰って頂いた様に電車でのバランス感覚も違うなと感じました。
また、私の課題である手が重いという問題ですが、色々原因を考えてみると肘がうまく使えていないことも要因の一つにあるかもしれない思いました。
ひじが上手く使えていないとツッパリ棒を相手に押し付ける様な形になり、余分な力が加わって重さに繋がるのかもしれないと感じました。
ですので、そこを意識しつつ、相手の呼吸などに合わせて背候診を行なっていこうと思います。
とある山中にて。
こんにちは、稲垣です。
修行の一環で、とある山中にて作業をさせて頂いております。
感じる事は多々あるのですが、この春に感じた事を記したいと思います。
今年の節分は例年よりも一日早い2月2日でした。
つまり立春は2月3日。
その翌日に山中に入りましたが、都市部の寒さとは違う空気を感じました。
気温は寒いのですが、間違いなく”春”。
ビルよりも、木に囲まれた方が、
季節を正確に教えて頂いているように感じます。
その春ですが、
藤沢周平の作品に出てきそうな
東北武士の気概のような力強さを感じました。
”長い冬に積もった寒さを、苦難を跳ねのけて芽を出す力強さ”的な。
車のギアでいうと1速、2速とかそんなギア比でしょうか。
そんな空気を感じながら作業をしていると。
肝氣の力強さを思い、疏泄機能・条達機能とはこういう事なのかな?と感じたり。
弦脉とはこういう事なのかぁ?と感じたり。
色々な事の辻褄があう感覚を得る事が出来て楽しい時間を過ごせます。
極めて価値ある時間を頂いています。
一人で黙々と作業をする事が、
そんな楽しく思考出来るコツのように思いえますが、どうなのでしょう。
この場所だけに限らず、様々な山を楽しみたいと思います。
血分病機
こんにちは、稲垣です。
血分病機についてまとめます。
【血分病機】
血は営より深層にあり、血分病変は営分病変よりもさらに重くいとされ、
心・肝・腎などに重大な障害の可能性があるとされる。
・熱深動血
熱邪が血分まで深く入りこんで火に変わり、火毒が燃えあがり、血絡を損傷し、血流を混乱させる。
血熱が心を傷れば、主神の蔵ゆえに意識障害・譫語・狂躁が現われる。
・血瘀血畜
血熱が気を損傷し、気滞をつくり血瘀に発展させる。
邪熱が血とぶつかる、陰液を熱邪が損傷させて営血を消耗させた場合、など瘀血となる。
さらに発展し、邪熱と瘀血がぶつかりあえば「血結胸」「下焦畜血」などとなる。
・血熱動風
血熱が盛んになり、厥陰まで入り込み、肝を犯して筋脈を焼く。
陰血を消耗させ、火より風を生じさせる。痙攣などが発生する。
少火は壮火となり、風を起こして、さらに火を煽る。
意識の混迷や厥証を発生させる。
・耗血動血
熱の血分侵入では、耗血・血竭・亡血・動血を起こす。
血の不足により筋を潤すことが出来ず、また陰が陽を抑えられずに
血虚生風、虚風内動を起こす。
【参考文献】
『中医病因病機学』東洋学術出版社