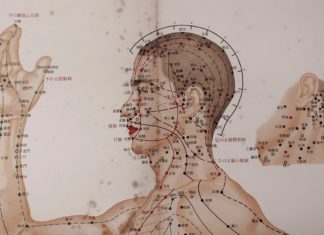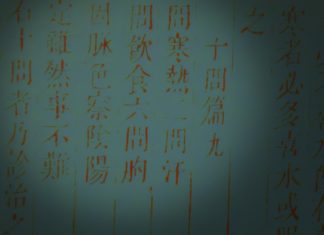異名同穴③
李世珍の下で働いていた方に、異名同穴について尋ねたことがあります。
「李世珍の家の伝来の呼び方がある。」との事。
その時は、中国の『宗族(父系中心の一族)』や『圏子(利益を共にする集団)』といった文化圏を想像しました。
③3つの異名のあるもの
穴名 異名
陰郄穴 : 少陰郄穴、石宮穴、手の少陰郄穴
隠白穴 : 鬼疊穴、鬼眼穴、陰白穴
会陰穴 : 下極穴、平翳穴、屏翳穴
京門穴 : 氣付穴、氣兪穴、腎募穴
氣衝穴 : 氣街穴、羊屎穴、氣冲穴
厥陰兪穴 : 関兪穴、厥陰穴、闕兪穴
三陽胳穴 : 通門穴、通間穴、通関穴
上巨虚穴 : 巨虚上廉穴、上廉穴、足の上廉穴
衝門穴 : 慈宮穴、上慈宮穴、前章門穴
水分穴 : 中守穴、分水穴、正水穴
人迎穴 : 頭五会穴、五会穴、天五会穴
兌端穴 : 壮骨穴、兌通鋭穴、唇上端穴
太淵穴 : 鬼心穴、太泉穴、大泉穴
大陵穴 : 心世穴、鬼心穴、心主穴
中膂兪穴 : 脊内兪穴、中膂内兪穴、背中兪穴
通天穴 : 天臼穴、天旧穴、天白穴
手の五里穴 : 尺の五里穴、大禁穴、尺の五間穴
天突穴 : 玉戸穴、天霍穴、天瞿穴
然谷穴 : 龍淵穴、然骨穴、龍泉穴
陽輔穴 : 絶骨穴、分肉穴、分間欠
陽陵泉穴 : 筋会穴、陽の陵泉穴、陽陵穴
白関兪穴 : 玉関兪穴、玉房兪穴、陽兪穴
胳却穴 : 強陽穴、脳蓋穴、絡郄穴
【参考文献】
『臨床経穴学』東洋学術出版社
『鍼灸医学事典』医道の日本社
『新版 経絡経穴概論』医道の日本社
舌診(08)
治療家のT先生に舌の研究の為にご協力頂きました。
舌を撮影させて頂く時は、
念のために表だけで2枚、裏だけで2枚撮影します。
色調の違いを考えて今回はこの画像を選択しました。
表
裏
舌質
淡白舌
嫰・点刺・歯痕
舌苔
白苔
全体・薄苔
仕事終わりに撮影をさせて頂こうかと思っておりましたが、
時間がありましたので、業務の前に撮らせて頂きました。
舌尖の紅が痛々しいですが、”朝” というのも要因の一つかと思います。
裂紋が出来てからかなりの時間が経過しているのかと思います。
T先生の舌は昨年より診させていただいておりますが、
瘀斑の境目が緩やかに感じます。
状況により変化があるのでしょうが、
安定している好転反応を感じます。
診病奇侅(01)
中脘
脾部中脘塞り、中脘水分に動あり、
又脾塞り、水分に動ありても、中脘に動なきは、食にあらず、
《私議》
中脘と水分について感じるところあり、考察を深めたいと思います。
【参考文献】
『診病奇侅』医道の日本社
東洋医学探訪(02)
鍼灸学生の授業の一環で解剖実習があります。
東洋医学を学ぶ者として
『太古の医家達も、間違いなく解剖実習で学んでいるだろうな』
と考えておりました。
京都で医学史の1ページに触れてまいりました。
山脇東洋觀臓之地
ーーーーーーーー碑文ーーーーーーーーー
近代医学のあけぼの 観臓の記念に
1754年 宝暦4年閏2月7日に
山脇東洋(名は尚徳 1705~1762)は所司代の官許をえて
この地で日本最初の人体解屍観臓をおこなった。
江戸の杉田玄白らの観臓に先立つこと17年前であった。
この記録は5年後に『藏志』としてまとめられた。
これが実証的な化学精神を医学にとり入れた成果のはじめで
日本の近代医学がこれから
めばえるきっかけとなった東洋の この一業をたたえるとともに
観臓された屈嘉の霊をなぐさめるため
ここに碑をたてて記念とする。
1976年3月7日
日本医師会
日本医史学会
日本解剖学会
京都府医師会
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
六角獄舎跡は二条城の南の因幡町にあります。
跡地は集合住宅であり、石碑のみの設置でした。
異名同穴への一考察。
稲垣さんが
以前に異名同穴①という記事を作ってくれた。
こういった勉強はやはり重要であり、
今後の為には必ずなると思う。
そういった訳で、僕も考察を挙げてみよと思う。
経穴は元々孔穴と呼ばれており、
『素問』以前の古代では
臓腑との関連性と言うものはほぼ分かっていなかったようだが、
それが『黄帝内経』(ここではこう記しておきましょう)の編纂により、
中国医学の基礎ができ、
それ以後『難経』や『傷寒論』へと続いたと考えられている。
それに合わせ経穴の研究も始まり、
夫々 名前がつけられたのだと。
これが、現在の基本的な考え方だと僕は思う。
ただ稲垣さんが記したように、
経穴には様々な名前(原文には一名●●と記す)があり、
これに関しては、
単純に様々な流派が存在したと考える。
これは真柳誠氏の書籍等も含め考えたのだが、
一例として『黄帝内経』を基礎とした”黄帝流派”、
そして鍼の名医であった”扁鵲流派”があったのだと思う。
流派が違うというのは、
現代の鍼灸流派で言うと、考え方、捉え方の違いくらいだと思うが、
当時は実際に『黄帝内経』だけでなく、
様々な治療集団があり(元々 統一されてない国であったし)、
全て根底から異なっていたのではないか。
そうなると、
治療に使う経穴名というものも全然変わり、
それを後世の医家達が『明堂』のような書物を編纂する際に
色々な書籍を参考にした結果、
こういうものになったのであろうと。
で、『黄帝内経』を基礎とした書物が遺っていたから
これを基軸に経穴名もつくられたのでは?と考えた。
まぁ、どこにも確証がないので、
一意見として。
素問 陰陽応象大論篇(第5)から その2
<学生向け 近日開催予定のイベント>
【学生向け勉強会のお知らせ】東洋医学概論をモノにしよう!
→(随時お問い合わせ受付中です!)
【学生向け勉強会】「素問を読もう!」申込み受付中です
→毎週火曜19時〜 または 毎週木曜13時〜(途中からの参加も可能です。)
こんにちは、大原です。
前回の続きで、「素問を読もう!勉強会」でも
少し触れた内容になります。
(前回の記事→素問 陰陽応象大論篇(第5)から)
前回は、素問 陰陽応象大論篇(第5)の中の
人体を構成するものの、
それぞれの相互転化についての記述について
考えていきました。
↓この一連の流れが重要であるという読み方をしてみました。
「味」→「形」⇄「気」→「精」⇄「化」
さて、素問の記述では、
最初の「味」は「陰」によって生じるとあります。
(「陰」→「味」)
もう一度原文を確認してみましょう。この2行目にあります。
【原文と読み下し】
・・・
水為陰、火為陽。(水は陰となし、火は陽となす。)
陽為氣、陰為味。(陽は気となし、陰は味となす。)
味帰形、形帰氣、氣帰精、精帰化。(味は形に帰し、形は気に帰し、気は精に帰し、精は化に帰す。)
精食氣、形食味、化生精、氣生形。(精は気に食(やしな)われ、形は味に食(やしな)われ、化は生を生じ、気は形を生ず。)
味傷形、氣傷精。(味は形を傷り、気は精を傷る。)
精化為氣、氣傷於味。(精は化して気となし、気は味に傷らる。)
・・・
2行目の「陽」や「陰」とは何を指すのかというと、
「陽」とは「天」のことで、
「陰」とは「地」のことであると、
この文章の前の部分の文脈から解釈できます。
すなわち「味」である飲食物とは、
「陰」すなわち大地のエネルギーによって
生じるということになります。
(「エネルギー」という言葉以外に良いキーワードが思い浮かびませんでした。
他に何か良い訳し方があるでしょうか、教えてください。)
形(肉体)や気、精は、正しい飲食によって得られると
前回の記事でまとめましたが、
さらに正しい飲食とは、
しっかりした大地のエネルギーから生じるということになります。
ちなみに、これらをまとめると
「陰」→「味」→「形」⇄「気」→「精」⇄「化」
となります。
現代の食生活における食材は、
大地のエネルギーをしっかり得たものかというと
そうとも言いきれないのでは?と感じてしまいます。
例えばインスタント食品や人工的に作られた調味料などは、
大地のエネルギーがほとんど無いのではないでしょうか。
また、旬のものでない野菜も
現代はビニールハウスなどによる栽培技術によって
手に入りやすくなっていますが、このような季節外れの野菜は
しっかりと栄養がとれるのでしょうか?
素問の内容から、そのような疑問をふと感じてしまいました。
(現代の農業の技術に関して私は全くの素人ですので、
このような疑問が間違ってましたら謝ります、すみません。)
参考までに、
「五味」の働きについての記述もこのあと出てきます。
辛散、酸収、甘緩、苦堅、鹹耎。
辛は散じ、酸は収め、甘は緩め、苦は堅くし、鹹は耎(やわ)らかにす。
(『素問 蔵気法時論篇』(第22))
さらに、
五味所入、
酸入肝、辛入肺、苦入心、鹹入腎、甘入脾、
是謂五入。
五味の入る所、酸は肝に入り、辛は肺に入り、苦は心に入り、鹹は腎に入り、甘は脾に入る、
是(こ)れを五入と謂(い)う。
(『素問 宣明五氣篇』(第23))
五味の働きについては
現代の薬膳関係の書籍に書かれていますので、
薬膳に興味がある方はご存知かも知れません。
ですが、例えば、
いくら酸味や甘味のある食材を用いて調理したとしても、
その食材にしっかりとした陰がなければ、
味覚としては酸味や甘味を感じたりしても、
実際には身体を養うような本来の食物としての作用が
発現されないのではないでしょうか。
五味は大地のエネルギーから生じるという
原則的な内容について書かれた書籍は
個人的にあまり目にしたことがありませんが、
重要なことのように思います。
参考文献
『黄帝内経 素問』 東洋学術出版社
色々わからないけども
身体を触るとき意識が一つに引っ張られていたことを指摘して頂きハッとした。
何かを見ようとして、その分他が疎かになっていたんだと思う。
意識を働かせない様にしなければ。
頭ではなく体が主。
テーマとしてはずっと持っているものなんだけど難しい。
このテーマで進めるには自分の人間性も見直さなければいけないけど、いちいち一つの事に囚われているところがダメなんだと思う。
そもそも体に限らず全ての事はこれ!って言うより一連の流れで繋がっているんだから何か違うような気がする。
身体をみる時も犯人探ししてる訳ではないんだから。
自分の状態として、前に意識が深く沈む?みたいな感覚があった時が一番良かった。
そうなっていく為にも生き方も大事なんだろうなと思う。
色んなことに対してサラッと生きれる様になりたいな。
そんなこんなで最近は勉強というより自分の人間性について考える時間が多くなっている。
まあ自分みたいな人間は自己否定してるくらいでちょうど良い様な気がする。
色んなものをへし折ってへし折って更地の状態にしたい。
人の幸せを喜ぶとかもその先にあるものだと思う。
まあ素朴が一番です。
脈診(04)
瀕湖脉学七言訣(二十、弱脉)
弱来無力按之柔、
柔細而沈不見浮。
陽陥入陰精血弱、
白頭猶可少年愁。
弱脉は力無く来て、按じても柔、
柔は沈にして細、浮では見られず。
陽は陥入し、陰精血は弱、
白頭(老人)は考えられるが、少年なら愁う。
脉が骨周辺まで沈む理由が何なのか..
自問自答してみる。
年老いて骨が弱くなり営気を必要としているから、
骨への栄養補給の為に沈下する?
いや、肌肉の中空を維持出来ない為に沈む?
衛気が衰えて、エマージェンシー発生の為に
脉が皮毛に栄養補給にやってくるのが浮脈?
現象に対しての理由は多々ありそう。
【参考文献】
『中医脉学と瀕湖脉学』(株)谷口書店
胃・小腸・大腸
霊枢を読み進めていって勉強している事を書いていきます。
《現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻》 P104
邪気蔵府病形篇「黄帝がいう。「私は五臓六腑の気が、みな井穴から出て、滎穴と輸穴を経て合穴に入ると聞いたことがある。
その気血はどの道を通って注ぎ、進入した後どの蔵府および経脈と連結しているのだろうか。その道理を聞きたいものだ。
岐伯が答える。「これは手足の陽経が別絡から内部に進入して、六府に連続しているのです。」
黄帝がいう。「滎穴・輸穴と合穴には、治療の上で一定の作用があるのか」。
岐伯が答える。「滎穴・合穴の脈気は深いところにあるので、内府の病気を治療できます」。
黄帝がいう。「人体内部の府の病は、どうやって治療するのか」。
岐伯がいう。「陽経の合穴を取ります」。」
黄帝がいう。「合穴には各おの名称があるのか」。
岐伯が答える。「足の陽明胃経の合穴は三里にあります。手の陽明大腸経の脈気は足の陽明胃経を循り巨虚上廉で合します。手の太陽小腸経の脈気は足の陽明胃経を循り巨虚下廉で合します。手の少陽三焦経は足の太陽膀胱経で合します。足の太陽膀胱経は委中で合し、足の少陽胆経は陽陵泉で合します」。」
→下合穴の説明が書かれていました。
腑病にはこれらを使いなさいと提示されています。
ここでは特に、足陽明胃経の上廉(上巨虚)・下廉(下巨虚)が大腸・小腸の合穴に設定されている点が気になりました。
《中医薬大学全国共通教材 腧穴学》 P 64
「中医理論によると大腸小腸は全て、広義の胃に属すので大腸小腸の下合穴は胃経上にあるのである。」
《中医薬大学全国共通教材 全訳中医基礎理論》 P130
「胃の通降作用とは、小腸が食物残渣を大腸に送ったり、大腸が糞便を排泄したりする機能も含んでいる。」
→答えなのでしょうが黄帝内経における根拠が書かれていません。
いや、普通に考えて胃から大腸まで繋がっているじゃないか!とよぎりますが、それは西洋医学の解剖学的所見なので東洋医学を考える上では参考にできません。
極力黄帝内経に理由を求めていきます。
胃〜大腸は、水穀の受納〜糟粕の排出までのラインのはずなので、まずは水穀が糟粕になるまでの流れを追っていきます。
<現代語訳 黄帝内経素問 上巻> P210
五臓別論篇「六腑には、常に水穀が充実しているものですが、反対に精気は充実していません。
この道理は、水穀が口から入ったあと、胃は実するが腸は空虚であり、食物が下へ送られる段階になると、腸は実するが胃は空虚になると理由にもとづいています。」
《現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻》 P479
腸胃篇
「「黄帝が伯高に問う。「わたしは六腑の消化器官がどのようになっているか、腸胃の大小・長短、水穀を容れる容量の多少などを知りたいと思う」。
伯高言う。「すべてをお話しいたしましょう。
穀物が口から入って体外に出るまでの消化器官の深浅・遠近・長短の数値は次のとおりです。
唇から歯までは長さ九分、口の端から端までは幅二寸半。歯から会厭までは深さ三寸半、水穀五合を容れることができます。
舌は重さ十両、長さ七寸、幅二寸半。咽門は重さ十両、幅一寸半、咽門から胃までは長さ一尺六寸。
胃の形は曲がりくねっており、それを伸ばすと長さ二尺六寸、周囲一尺五寸、水穀三斗五升を容れることができます。
小腸は腹腔の中にあり、後は脊柱に付き、左から右へ向かって周り廻り、腹腔内で幾重にも折り重なって廻り、下口は廻腸に注ぎ、外側は臍の上に付き、廻り折れ曲がり、湾曲すること全部で十六回、周囲二寸半、直径八分と三分の一、長さ三丈二尺。
廻腸は臍の所に位置し、左に向かって廻り、下向きに重なって、折れ曲がり湾曲すること、同じく十六回、周囲四寸、直径一寸と三分の一、全長二丈一尺。
広腸は脊椎に付き、廻腸が送る糟粕を受け取り、左に向かって廻って脊椎の前に重なり、上から下へ行く程太くなり、最も太い所で周囲八寸、直径二寸と三分の二、長さ二尺八寸。
腸胃の水穀を運輸消化する過程は、口唇から肛門まで総長六丈四寸四分、全部で三十二回の湾曲があります」。」
《臓腑経絡学》 P 63
「大腸は、廻腸、広腸、直腸、肛門(魄門)から成る。」
《中医学ってなんだろう》 P 241
「「大腸の伝導」は、広い意味での「胃の降濁」の一部と言えるものです。
胃気が下降していることは、大腸の伝導の前提となります。」
→飲食物が胃に入って糟粕を排出するまでの過程が示されており、それは胃を起点に一連の流れで繋がっているので古人はこのラインを胃の代表する一つのグループとして考えた。
腸の伝導機能とは胃の降濁機能の一部とも言える。
関連が深いからこそ、わざわざ「腸胃篇」という一つの篇にまとめたのかもしれない。
↓「胃の通降(降濁)機能」
①胃◯→小腸→大腸
②胃→小腸◯→大腸
③胃→小腸→大腸◯
④胃→小腸→大腸→◯(糟粕)
続いて「胃経上にある下合穴を刺し腑病を治す」とはどの様な事なのか考えてみたいと思います。
参考資料
<現代語訳 黄帝内経 霊枢 上巻> 東洋学術出版社 南京中医薬大学編著
<現代語訳 黄帝内経 素問 上巻> 東洋学術出版社 南京中医薬大学編著
<中医薬大学全国共通教材 腧穴学> たにぐち書店 主編 楊甲三
<中医薬大学全国共通教材 全訳中医基礎理論> たにぐち書店 主編 印会河
<中医学ってなんだろう> 東洋学術出版社 小金井信宏著
痰
今日は痰について書いていこうと思います。
痰は津液が濃密になり、粘ることにより形成されるものだそうです。
ネバネバ、ドロドロしたイメージです。
津液はサラサラした水のイメージです。
ではなぜサラサラしたものがドロドロに変わってしまうのでしょうか?
津液というのは飲食物が水穀の精に変化してそれが津液に変わる
また、気が津液の元という考えもあります。
つまり、津液を作る過程でなんらかの異常があり、痰ができてしまうのでしょうか?
あるいは、津液がなにか不純物が混ざってドロドロになってしまうのか。
あるいは、熱で津液が焼かれてドロドロになってしまうのか。
何が原因で痰が形成されてしまうのかが疑問です。
津液を形成するのは基本的には脾の役割で、つまり脾の失調によって痰が形成されてしまう。
そして、痰は気に従ってあらゆるところへ留まるとあるので、痰による症状は様々です。
肺に行けば痰や咳嗽が出る
脾に行けば胸焼け
経絡上に留まればあらゆる部位の疼痛、など症状は多岐に渡ります。
そして、気の流れを止めれば、気鬱、気滞が起こり、万病の元です。
脂肪は痰という考えにも至るのでしょうか?
つまり、太り過ぎの方は脾の働きが悪く、
正常に運化が出来なくて、食べてもお腹が減り、
水穀が正常に気化されず痰になって、脂肪として体の周りに痰がついているという考えも一つあるかも知れません。
痰がどのようなことが原因で形成されてしまうことについてよく考えたいと思います。