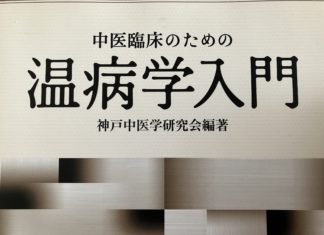色々メモ
手がビリビリ
人の身体を触らせてもらって感じることのある手のビリビリって感じは何なんだろう。
この感覚を探っていく必要がありそう。
治療後のベット
治療後のベットって何か残っているのかな。
人によってだけども、イメージとして何か薄黒く?モヤっとしたものが残っている気がする。
考え事
胸の部分がずっと気になっている。
神は働きすぎると疲れる。
自分の身体でも、思考すると気が上がる。
考えすぎ、思考しすぎると動悸がする。
一時的に落ち着けるだけなら桂枝加竜骨牡蛎湯(竜骨・牡蛎)を使えば思考の暴走、動悸は治る。
心の暴走は宗気にも影響するためか息切れも起こる。
現代語訳 素問 霊蘭秘典論篇 P161
「心なる者は、君主の官なり。神明焉より出づ。…膻中なる者は、臣使の官、喜楽焉より出づ。」
調べていこうと思ったけどここはとりあえずここまでにします。
悪癖が出てる。
形
漢字はもともと意味があったはずなのに字義を知らないと形に拘ってしまう。
そうなってくるとあんまり意味がなさそうだなと思う。
意識
今までも意識していたけど、日常の意識を使いかたをもうちょっと変えてみよう。
自分がその時どうしたいと思ったか、何に魅かれたか、嫌だと思ったこと。
学校で勉強ばかりさせられると遠のいていきそうなところ。
一鍼堂で教わって大切だと思ったことのみ実践。
変えてみること
ここ一週間、歩く際に使う筋肉、重心の乗せ方を変えてみています。
続けてみるとふくらはぎ、内転筋の筋肉のつき方が変わって面白いです。
日常的には以前仰って頂いた様に電車でのバランス感覚も違うなと感じました。
また、私の課題である手が重いという問題ですが、色々原因を考えてみると肘がうまく使えていないことも要因の一つにあるかもしれない思いました。
ひじが上手く使えていないとツッパリ棒を相手に押し付ける様な形になり、余分な力が加わって重さに繋がるのかもしれないと感じました。
ですので、そこを意識しつつ、相手の呼吸などに合わせて背候診を行なっていこうと思います。
衛分気分営分血分
今読んでいる本です。
以前から衛気営血についてしっかり向き合ってこなかったので、温病学はずっと気になってた本でした。まずは入門となっているので理解しやすいかと思ったのですが、やっぱり簡単ではないですね。
でもとても勉強になります。
皮膚病なんかに応用できそうです。
朗読、会話
朗読
最近人に合わせるって難しいなと痛感しています。
合わせにいったらより合わなくなる感じがします。
正直どうしようかと悩み中なのですが、何かしらやっていかないと変わらないので色々試していっています。
最近試し始めた事が人の朗読しているところの真似です。
心から入れれば一番いいのでしょうけど、できていないのでまずは形から入ろうと思ってYouTubeなどで人が行なっている朗読を真似してみています。
人との会話中に全く同じ事をしていたら違和感が生まれそうですが、相手と同じ事をする必要があるので少しは相手の理解に繋がる気がします。
また、長い文章になると腹から声が出ていないと読みきる事ができないので伝わりやすい声を出さなければいけなかったり、瞬発的に言葉を出す訓練にもなります。
会話
ストレスなく一緒に過ごせる人は波長が合って自然に過ごせる。
家族でも体調不良を起こすと様子が違ってくるので違和感から色々察知しやすいと言った話をよく聞く。
違和感を察知できるのは、同じ空気感をもった人の違和感だと思う。
鍼灸院には若者からお年寄りまで幅広い年齢の方が来るし、色んな個性を持っている。
そういった相手を理解しようと思えば尊重しなければ話は始まらない。
綺麗なものばかりに囲まれているとそう言った人にしか対応できなくなるし、逆もそうなる。
本当に会話上手な人は違和感を感じない。
きっと一致してるんだと思う。
ネガティブなもの
会話の中でネガティブなものが出てくるとそれに同意してはいけない。
もっていかれる。
ただ真っ向から否定するとそれもまた問題なので違和感を感じさせずにかわす必要がある。
こんにちは高山です。
頭痛や、食欲不振も、不眠も、疲れも、風邪も、
全てが五臓の弱りや、働き過ぎ、
そして、切診や望診、ツボの反応はその五臓の失調を表しているのだと感じます。
しかし、ツボに至っては特殊で、そこに針を刺すと
その五臓の失調が改善されたり、体の熱を取り除けたり、
外邪を撃退することができるようです。
これに関しては、なかなかの不思議です。
お腹の中に全て収まっている五臓が、なぜ手や足、背中、
体中のある特定の部位で反応が出るのか。
五臓と経絡は繋がっているからというかのもありますが、
それだけでじゃないような気もします。
そして、一鍼堂の先生たちは、そこに小さい鍼で刺して
大きい五臓を動かす。小さい力で大きなものを動かす。
それだけツボには大きな力があると言うことでしょうか。
「ツボにはこんな効果があって、こういう症状の時に使うといいよ」って学校では単純に教えられていますが、
実際そういうものでもない感じがします。
そこが、西洋医学との大きな違いかもしれませんね。
いくらツボの部位を見たって自分には目では見えませし、よくわかりません。
わからないことがありすぎます。笑
でも今は、目でも見える、頭でも考えられる弁証ををしっかり学びます。
欲しかった本入手
以前から欲しかった意訳黄帝内経太素が安値で売られていたので手に入れる事ができました。
まだ読み始めたところですが自身が内経を読んで疑問に思っていたところがハッキリ書かれていたりして勉強になります。
今回は勉強用のブログとして、書籍から学んだ事を書いていこうと思います。
本一辺倒にならない様に、モードを切り替えながら生活していこうと思います。
まだパラパラ読み始めたところですが、気になった部分の一部を書いていきます。
意訳黄帝内経太素 P131 五臓命分
「志・意と者(は)精・神を御し魂・魄を収め、寒・温を適え喜・怒を和す所以者也。」
P132
「志・意が和す則(と)精・神は専直(すなお)となり魂・魄は散ぜ不、悔・怒も至ら不、五臓が邪気を受けることは不矣(ない)」
ここでは志・意が切り離されていない点も気になる。
現代語訳 黄帝内経霊枢 上巻P161 本神篇
「物を任うゆえんの者これを心と謂う。意の存する所これを意と謂う。意の存する所これを志と謂う。」
全訳 内経講義 P201
「李中梓の注「意がすでに決まり、堅固になったものが志である。」」
記憶などで例えられた場合、意は短期記憶力で志は長期的記憶力と説明されていました。
(意の在する所これを志と謂う。)
医学三蔵弁解 P151 帰脾湯
「人参は心気を補い、遠志は腎中の志気を補います。心腎の二気がよく交通すると、脾気がその昇降の間を保ち、三臓の気が自然と充実してきます。」
帰脾湯は心脾両虚の薬ですが、心神不交も兼ねる。
しかし帰脾湯の物忘れの特徴的な現れ方は「直前の記憶がない」という点。
さっきまで何をしていたのか分からなくなる。(意病)
でも、意志は切り離せるものではなく、実際に遠志という生薬で腎気(志気)を心に届ける過程で脾気(意)を巻き込んで治している。
この後のストーリーとして意志が安定して魂・魄なども安定、喜・怒も過剰なものが無くなればいいなと思いました。
参考書籍
意訳黄帝内経太素 第一巻 築地書店 小曽戸丈夫著
現代語訳 黄帝内経霊枢 東洋学術出版社 南京中医薬大学著
全訳 内経講義 たにぐち書店 田久和義隆訳
医学三蔵弁解 たにぐち書店 伴尚志 現代語訳
印象的だったこと
日曜日、腹診と脈診の勉強会に参加させて頂きました。
その際驚かされた事がお腹の変化の早さ。
白石先生のお身体を衛気診で触らせて頂いた時に特に顕著に感じたのですが、左の肝相火のエリアで強い熱感があり、白石先生もそこを触られている時違和感を感じられる部分でした。
余りにも印象的だったのでここですかと確認していると段々熱感が冷めてきてなくなっていった。
次確認するともう残っていなく、お身体を触らせて頂く時にサッと診る必要性を感じました。
また、脈診を行う際、座った時に腰の角度を変えると左肩の窮屈さが無くなって診やすくなり、患者との距離感も今までよりいい感じに落ち着きました。
その感じで行うと今までと診ている時の景色も変わり、自分自身も小さく感じられた。
受け手にその際の感想を聞いても圧を感じにくかったそうで変化が感じられて嬉しかったです。
寺子屋で椅子に座って勉強させて頂いている時でも実践できそうなのでやっていこう。
2年生最後の日
2年生最後の実技は色んな情報を生理して計画を立てパートナーに自由に治療をする内容でした。
今まで、頭痛や膝関節痛など想定して先生の決めた配穴を治療する内容が実技のメインでしたが、いきなり自由となると、頭が真っ白になります。
今朝から筋トレによる筋肉痛と口苦があるという訴え。
紅舌 微黄、呼吸が浅い。右手の僅かな顫動、右足の貧乏ゆすり、外踝の乾燥、天枢の冷えと左少腹の拒按、目の充血。後頸がパンパン。
体からどのように情報を得て整理して選穴するか、焦りばかりが先立ってパニックになりました。
気持ちの迷いや自信のなさは治療に反映されるもので、あれこれ施術をしてみても特に結果も得られず、先生が刺した百会のみが効いたようで、「この一穴で良かった」というパートナーの言葉に面目なく、とても悔しい気持ちでいっぱいで授業の後、私も口が苦くなってきました。
歯が痛い日々
歯が痛い。
歯痛ってこんなに辛いものんなんですね。
昔に虫歯で治療した歯が疼くので、被せを外して再度削ってもらったのですが、その歯が痛すぎる(泣)
仮歯状態なんですが、麻酔が切れた後から痛みが始まってずっと痛いんですけど。歯が気になって集中できず、何事もやる気が起きなくなっています。もちろん勉強も・・・
再度かかってる歯医者さんに相談したら、恐らく歯髄炎でしょうと言われました。通常は一週間くらいで痛みは治るそうです。
歯の神経を抜くのは嫌なので、この痛みに耐えるためにロキソニンを毎日飲んでいます。
それでも痛くて気になってしまうので、何かいい方法はないかと思いついたのが針麻酔でした。昔行った勉強会でそんな実技もしたはずだと、資料を引っ張り出し、電気パルスをつなげて取り敢えずやってみようかと。
患部は下の歯なので、三叉神経の第3枝の大迎と下関。あと合谷と曲池。
パルスを行っている時は何となく痛みが薄らいでいるような感じがするものの、鍼を抜くとやっぱり歯の痛みは消えてなかったです(泣)
やり方がマズかったのでしょうか。
痛みが去るまで、我慢するしかなさそうです。
最近試していること
最近試してる事①
目に頼らなかったらどうなるんだろうって事で色々試してみています。
目を瞑って10分程度過ごす。
その際ゆっくりでもいいから歩きながら、猫の位置を探ってみる。
分からなかったら目を開けて場所を確認。
当たったら触ってみる。
いつもと違う感覚で面白いです。
しかし物にぶつかるかもしれない恐怖で歩くのが中々怖いです。
視覚障害の方は点字ブロックに対して杖が当たった時の音と触覚で歩行を行っているそうなのですが、神経張ってないとできないなと思いました。
できれば目を開けながら研ぎ澄まそう。
使わない事はできると思う。
道の物為る、惟れ恍惟れ惚。惚たり恍たり、其の中に象有り。恍たり惚たり、其の中に物有り。
窈たり冥たり、其の中に精有り。其の精甚だ真なり、其の中に信有り。
老子21章とも繋がるのかな。
最近試してる事②
じゃあそれを目を開けながら近づけようとして、色々方法はあると思うのですが目を背けながら対象物に触るという事を行ってみています。
また違った印象を受けます。
最近試している事③
会話する時、伝えたい事が伝わった瞬間を探る。
トーン、テンポ、躱しかたなど。
また、伝わりにくい状態はどんな状態?
自分がその状態ならどうなる?
この前最悪な精神状態だった時の自分の感覚も参考になります。
妊婦
妊婦さんを見て、もし「治療してくれ」と言われたらどうするんだろうと思った。
1人ではなく、2人分の命を見なければいけないので状況が違う。
母体も分け与えている状態。
そもそもの目的が違うので、脈なども正常時とは違う。
臍も参考になりそう。
ここで胃気などにも踏み込むことになると思うが、今勉強している傷寒論とも関連させていきたい。
まだ多分何かあるんだろうなと言った段階です。
フロイト
最近ちら〜と見ていっているのですが、面白い考えの人だと思いますし、勉強になってます。