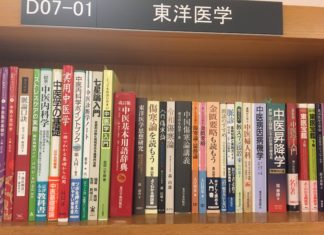京都薬用植物園の呉茱萸(ごしゅゆ)
武田薬品工業(株)の京都薬用植物園で、年に4回行われている研修会があります。
今回は『晩秋の研修会』との事。
一般向けの研修会で、特に専門的な講義が行われるというものでは無いのですが、実体験もさせて貰えるのを楽しみに参加しています。
私は2回目の参加となります。
今回は漢方処方園、樹木園、温室を回りました。
「味見してみますか?」のコーナーでは呉茱萸(ごしゅゆ)を頂きます。
物凄く辛いのをご存知でしょうか?・・辛いです!
呉茱萸
[効能]
◦ 暖肝・散寒止痛
◦ 下気止嘔 など
この辛さを感じると”効能”になんとなく納得が・・
前回の研修会でも味見をさせて頂きましたが、体験する度に植物のもっている”力”を強く感じます。
漢方薬においては、個々の植物を適切な配分でコーディネートする事で、服用の効果を最大にしているのだろうと考えさせられます。
逆に、個々の主張が強いので、調和をとる材料、飲み易くする材料を共に配合する必要があるのかとも思います。
鍼の調和は切経や刺鍼をする”その時”に、人間の手によって加減できるところなのでしょうか。
薬との違いであったりするように思うのですが、いかがなものでしょう?
薬草のあまりの刺激の強さに色んな事を考えてしまう『晩秋の研修会』でした。
【参考文献】
・中医臨床のための中薬学(東洋学術出版社)
私と鍼灸
はじめまして 先月から学生として参加させていただくことになりました。
今後こちらのブログで何かしらの成長の記録が残せればいいなと思っています。
先ずは初めてなので簡単な自己紹介的な事を書きます。
鍼灸の資格を取得して8年になりますが、卒業後は鍼灸業界には就職せずに元々の職業だった薬剤師として今も薬局で働いています。
元々東洋医学への興味は漢方薬から入りました。漢方薬の勉強会でたまたま鍼灸のデモを拝見する機会があり、その鍼は身体に刺さないで行うものだったのですが、治療を進めるに従って身体の反応がみるみる変化していき、まるでその先生は魔法使いのようでした。
それを目の当たりにした私はかなりの衝撃でした。たった鍼一本でこんなにも早く、しかも刺さないで身体を良くすることができるなんて、しかも手技的には全く難しそうには見えなかったんです。
これなら私にも出来るのでは?と正直簡単に思ってしまったんです。
それが私の鍼灸との出会いで始まりでした。
つづく?
こんにちは高山です。
頭痛や、食欲不振も、不眠も、疲れも、風邪も、
全てが五臓の弱りや、働き過ぎ、
そして、切診や望診、ツボの反応はその五臓の失調を表しているのだと感じます。
しかし、ツボに至っては特殊で、そこに針を刺すと
その五臓の失調が改善されたり、体の熱を取り除けたり、
外邪を撃退することができるようです。
これに関しては、なかなかの不思議です。
お腹の中に全て収まっている五臓が、なぜ手や足、背中、
体中のある特定の部位で反応が出るのか。
五臓と経絡は繋がっているからというかのもありますが、
それだけでじゃないような気もします。
そして、一鍼堂の先生たちは、そこに小さい鍼で刺して
大きい五臓を動かす。小さい力で大きなものを動かす。
それだけツボには大きな力があると言うことでしょうか。
「ツボにはこんな効果があって、こういう症状の時に使うといいよ」って学校では単純に教えられていますが、
実際そういうものでもない感じがします。
そこが、西洋医学との大きな違いかもしれませんね。
いくらツボの部位を見たって自分には目では見えませし、よくわかりません。
わからないことがありすぎます。笑
でも今は、目でも見える、頭でも考えられる弁証ををしっかり学びます。
衝脈
少し前から奇経八脈について書籍にて学ぶようになりました。
先日、研究生同士でモデルになり治療する機会があったのですが、その時の主訴がL2当たりに腰痛があるというものでした。
舌診や腹診、脈診、切経などを一通り行なった結果、左の地機と太渓に鍼をおいたのですが、その際、被験者によると腹部深部の嫌な感覚と足のそれぞれの鍼のおいた穴が繋がった感覚ががあったようで、置鍼とともに段々和らいで行ったようです。
それと呼応したのか背中の痛みも薄まったと言われていました。
身体の深部という言葉に、奇経八脈の「衝脈」を思い浮かべました。
私なりに奇経を交えて考察したいと思います。
衝脈は五臓六腑十二経脈の海で、五臓六腑は皆、衝脈によって血を受けていると言います。
また天人地三才理論によれば、督脈は天脈、任脈は地脈、衝脈は人脈になります。つまり督脈と任脈を繋ぎ、陰陽のバランスをとっているとも言えます。
衝脈の流注自体は複雑でいろんな説がありますが、今回関係がありそうなところを抜粋すると、〜臨床に役立つ 奇経八脈の使い方〜 著:高野 耕造
・李時珍は、衝脈の腹部における走行について「素問」骨空論と「難経」の折衷案を採用した。つまり、足の少陰腎経と足の陽明胃経を走行するとしている。
・胸部の衝脈は、浅層を走行するルート(経穴があるルート)と深層を走行するルートの2本のモデルを設定する方がよい。
・衝脈の下肢の流注は、大腿部内側面を下降し、足の太陰脾経と足の少陰腎経の間を通過する。そして、膝窩の陰谷に到達している。
・衝脈の下腿部の流注は、陰谷から2脈に分かれる。一つは、陰谷から足の少陰腎経に沿い、内果の後方から足底部の湧泉に向かう。もう一つは、斜め前方の足の太陰脾経を下降し、三陰交と交わり、足の太陰脾経とともに内果をめぐり、公孫から隠白に向かう。
・衝脈の足の太陰脾経を通る分枝は、足背面に出て拇趾と示趾の間を下って太衝に至る。
・衝脈の流注は、背裏(脊椎の臓面)を上行し大杼まで達している。
・衝脈は足の太陽膀胱経の一行線の脊柱前面を上向し、督脈を背裏から支えている。
取穴したツボは下腿部の脾経と腎経でした。衝脈の流注とも関係しているかと思います。また反応があった腹部の位置ですが、正確には確認してなかったですが、左側の胃経と腎経の辺りだったかと思います。
ちょうどその裏面の左背部(三焦兪から腎兪辺り)に膨隆がみられました。施術後、膨隆は幾分柔らかくなり、平になろうとしているように思えました。
またこの著者は左右の腎から供給される精気は帯脈を通じて左右の衝脈に流れるとしてます。
おそらく日頃の疲れがベースにあるところ、前日の睡眠不足で更に腎気虚損となり、腰痛が強く現れたと思われます。
一般的に奇経は臓腑とは直接連携はせず、正経の気血の調整を果たしていると言われます。
しかし衝脈は十二経の海と言われているため、経絡の異常や五臓六腑の不調による影響が色濃く現れやすいはずです。
今回は衝脈(人)を充実させるためにも、先天の精(天)に関わる腎経と後天の精(地)に関わる脾経に施術している事になります。
恥ずかしいほどの浅学ですが、少しずつ学びを深められたらと思います。
易経 その2
つづき
この易経ですが、一般的には「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いのイメージがつよいですが、本を読んでみてそれだけではないことがわかりました。
易経には大昔の人が、世の中の仕組みや人生においての法則があって、その法則には一定のルールがあり、それを64種類の物語にして教えてくれているらしいのです。
その法則を理解して身につければ、もはや占う必要性もなくなり世の中の森羅万象、物事の道理、そしてその先行きが見通せるようにもなるというのです。
そう聞くと更に興味が湧き、是非理解を深め、その智慧の恩恵に与りたいと思うのも必至です。
そんな易経ですが、いつの時代に出来上がった考え方なのかと調べてみると、今、日本で一般的に使われている「易」は「周易」と言って周王朝時代に確立したそうです。
その周王朝時代の日本は何時代か見ると、縄文時代でした。
恐るべし中国史です。
そんな昔から世の中の道理が解明されていたのにびっくりです。
東洋医学といい、易経といい太古の先人に感謝します。
方剤学(1)
八法
『医学心悟』(程鍾齢)には「病の源を論ずれば、内傷外感の四字によりこれを括る。病の情を論ずれば、すなわち寒熱虚実表裏陰陽の八字をもってこれを統べる。しかして治病の方は、すなわちまた汗・和・下・消・吐・清・温・補の八法をもってこれを尽くす」とある。
温法
温法とは、温裏・散寒・回陽・通路などの効能により、寒邪を除き陽気を回復し経路を通じて、裏寒を解消する治法である。裏寒の成因には外感と内傷の別があり、外来の寒邪が裏に直中するか、陽気不足や誤治による陽気の損傷によって陰寒が内生する。このほか、裏寒には臓腑経絡という部位の違いがある。それゆえ、温法にも温中散寒・回腸救逆・温経散寒の別がある。
○温中散寒剤
中焦虚寒や中焦の裏寒に適用する。
脾胃の陽気が虚衰して、運化と昇陽が不足し、腹痛・腹満・食欲不振・口渇がない・下痢・悪心・嘔吐・舌苔が白滑・脈が沈細、沈遅などの症候がみられる。このほか外寒が中焦に直中して裏寒が生じることもあり、素体が陽気不足の場合に発症することが多い。
(01)理中丸《傷寒論》
(02)呉茱萸湯《傷寒論》
(03)小建中湯《傷寒論》
(04)大建中湯《金匱要略》
○回腸救逆剤
心腎の陽気衰弱による内外倶寒の陰寒証に適用し、陰寒内盛によって生じる陰盛格陽・戴陽などの真寒仮熱にも用いる。
陽気衰微の内外倶寒では、元気がない・四肢厥冷・畏寒・身体を縮めて寝る・不消化下痢・舌質が淡・脉が沈細、沈で無力などがみられる。悪化し、陽気が格拒されると、体表部の熱感・煩躁など格陽の症状や口渇・煩部紅潮など戴陽の症候があらわれ危急状態となる。
(01)四逆湯《傷寒論》
(02)参附湯《正体類要》
(03)回陽救急湯《傷寒六書》
(04)黒錫丹《和剤局方》
○温経散寒剤
陽気の不足や陰血不足で経脉に寒邪を受け、血の運行が阻滞された状態に用いる。
手足の抹消の冷えや肢体のしびれ痛み・脉が沈細などの症候がある。
(01)当帰四逆湯《傷寒論》
大建中湯(温中散寒剤)
〔主治〕
中焦陽虚・陰寒上逆
〔組成〕
蜀椒・乾姜・人参・膠飴
〔方意〕
急いで温中補虚・散寒降逆して止痛・止嘔する。
主薬は辛・大熱の蜀椒で、脾胃を温め散寒除湿・下気散結に働く。
大辛・大熱の乾姜は、温中散寒して中陽を振奮し、逆気を散じて止痛・止嘔する。
甘温補中の人参・膠飴は脾胃を補益して本治し、膠飴は緩急にも働く。
辛甘の薬物のみで中陽を温建し、補虚散寒の力は小建中湯より峻烈であるので「大建中湯」と名付けられる。
後天の本
脾と胃とはともに中焦にあり、脾は陰であり、胃は陽であるので、両者は表裏の関係にある。
胃は受納を担当し、脾は運化を担当し、互いに協力しあっている。
そのため、どちらかに病変が発生したときには、もう一方に害が及んでしまう。
したがって実際に脾胃の病変が起きた時には、水穀の受納・運化・配布機能の全てに渡って影響が現れる。
脾胃は気血を化生し、五臓六腑と体内外を潤して肌肉を満たし、四肢を壮健にするので、後天の本といわれる。
【参考文献】
『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社
『中医病因病機学』東洋学術出版社
どうなんだろう
勉強で母親の身体を診させてもらった。
特に気になる点は左少腹急結・左少腹部や股関節あたりの色が黒くなっている・中脘あたりが緊張・舌は腐膩があり、全体的に紫舌・舌下脈絡の特に左側の怒張・脈は渋・左のみ深く沈めると脈が確認出来なくなる・左太渓の顕著な陥没と発汗・足先は冷えている。
以前脈を取らせてもらった時は疲れると脈が7回に一回飛んでいた。
問診はせずに症状で気になる点を後で確認すると左腰に違和感があり、まれに左少腹部に張った感じが起こるとの事。
根本は腎の弱りなのか。
瘀血を取るにしても正気を立て直す必要があると感じた。
よくゲップが出る人なのですが、この胃の働きの低下にも腎虛・瘀血が関係してそうな気がする。
治療穴としては左太渓で腎の立て直しを行うシーンかなと想像。
また、活血も組み合わせる必要があるのかと思った。
左の三陰交を抑えると軽い圧痛があるとの事だったのでここも治療穴に含めることができるのか。
色々考えてみたものの分からない点だらけで難しい。
心血虚証
心の血不足によって血脈が空虚になり、身体を滋養することができなくなる。
心血が不足すれば「神」にも影響が出る。
思慮過多、心労過多、目の使い過ぎ、血の生成不足(脾胃の失調からくる)などが原因。
心悸、怔忡、胸悶、眩暈、健忘、不眠多夢、顔面蒼白などの症状が現れる。
心血虚が痩せやすいのは、脾胃からの影響を受けて血の生成不足が起こり、
身体が栄養を吸収できないため。(舌もやせてくる)
心血が不足し、神を滋養できなくなると落ち着かなくなり、不安になる、心悸怔忡がおこる。
(眩暈や健忘が現れるのは血が少なくなり、髄海を養えないため)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
自分の確認手段など
週末
先週の週末くらいですが、学校での様子をみると全体的にイライラしている様子の人が多かった気がします。
こちらから話を振る訳でもなく、久しぶりに昔出ていた症状が出てきたなど会話で出てきた。
そういう時期だったのかなと勉強になりました。
肝火の人は目と喋り方が爆発的な特徴を持つ気がします。
自分の確認手段
最近自分のどんな状態が良くて、どんな状態が良くないか前よりは実感できる様になってきた気がします。
良くない状態を作ってしまっている時、現実に存在する音、匂いなどに対する取りこぼしが多く、みるものの視点が近い。
その状態になっている時を確認すると変な没頭の仕方をしてしまっている事が多い。
改善方法としては、今に集中したら状態は良くなる。
もっと受動的に。
要らないものが多すぎる。
もっと自分と周りの環境を一致させたいな。
場所によって
小腸経の切経を行う時、相手の顔近くに手を置いてもらうやり方で労宮でみようとすると物理的に距離感が近くなりやすい。
最近は手の指でもみれたらいいなと思い、指先でも軽く触れるよう色々指先で触る訓練中です。
流れ
細かい部分を見るのはいいけども、そこに囚われた瞬間他の情報との関連を切ってしまっているので別物になる。
診断時、そうならないためにもサッパリ生きなきゃなと思います。
温煦作用は気の生理作用?
気の生理作用について。
気には推動・温煦・防御・固摂・気化の5種類の生理作用があると授業で教わった。
その時は特に疑問を持つこともなかったが、中医学の本に、
「温煦作用は陰陽の「陽」の機能であり、「気」の機能ではない」と書かれていた。
”「陽」は温煦を主り「陰」は涼潤を主る。陽は温煦すなわち温熱性を主り五臓六腑・組織器官および気・血・津液・精を温暖にし、陰は涼潤すなわち寒冷と滋潤性を備え、陽の温熱性を抑制・調節し陽と共同協調して体温を一定に保っている。”
(『新装版 中医学入門』神戸中医学研究所より抜粋)
一方で、
”温煦作用は気の作用で、気は熱源として働き、気によって産生された熱により組織器官を温めすべての生理機能がスムーズに行われるようにする。”
(『新板 東洋医学概論』 医道の日本社より抜粋)
温煦作用は陰陽?気?結局どっちなのだろう
読んでも答えはわからないので、疑問のままおいておくことにします。