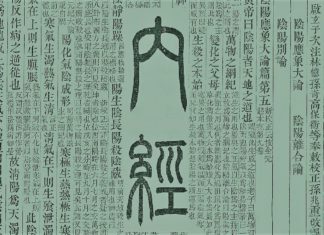脉要精微論篇 第十七(01)
黄帝問曰、診法何如。
岐伯對曰、診法常以平旦。
陰氣未動、陽氣未散、飮食未進、
經脉未盛、絡脉調匀、氣血未亂。
故乃可診有過之脉
切脉動静、而視精明、察五色、
観五藏有餘不足、六府強弱、形之盛衰。
以比参伍、決死生之分。
患者さんが来院され、部屋に案内して暫く。
問診に入らせて頂き、四診を行うも
患者さんの全体象が掴めていないなぁ・・と反省の日々。
対峙した時の弱さをつくづく思う。
治療する側として、心持ちから何から必要なものが多々あり。
切脉一つするにせよ、無駄遣いを心掛けなくてならないと緊張感を持つ。
【参考文献】
「現代語訳 黄帝内経素問 上巻」東洋学術出版
楽しい!
寺子屋メンバーで勉強会をしながら、
それぞれの経験を集めて
あーでもない、こーでもないと話し合い
感じた事を共有する濃密な時間。
とても幸せな時間だと思う。
ひとつ得たヒントから自分の迷いが払拭された時、
急に世界が広がることがって
楽しい!と思えることが更なる原動力になる。
自分になかった身体の使い方、
今日得たものを何万回も繰返し、
身体を作っていくこと。
そして楽しい!と思えることが増えるように
どんどん深みにハマっていけばいい。
単純化など
単純化
ありがたい事に最近色々やることをやらせて頂いている。
すると色んな余計なものが入りにくくなってきた。
余裕が無くなるとミスを起こしてしまう傾向は相変わらずですが、そうならない様に自分をコントロールしていきたい。
やるべき事に向き合ってさっさとクリアしていく。
そのためにも自分の中で色々単純化させていく必要あり。
バイアスを取っ払う。
治療にも繋がる。
批判的思考
自分は裏が見えていない事が多々ある。
何か形を受け取ったものも、内包されるものが違っている事がある。
その違和感に気付けるか。
先に起こるものへヒントが隠されている事もある。
思い返せばでは遅い。
ある種の健全な疑う心も必要。
清濁全て飲み込める様に。
それを瞬間に判断できる様に色々経験を積む必要あり。
繕うな
良いものを作ろうとした時、そこへ自分がどの程度関わる事が良いか。
まだ配分が上手くいっていない。
目的の達成のためにどうすればいいか。
人を信じてお任せするところはする。
お任せして良いかわからないなら相談する。
そこを任せられないのもある種のエゴ。
自分の弱さ。
人と向き合う
どんな忙しかろうが寺子屋の時にお身体を貸して頂いている患者さんにきちんとで向き合う。
向き合い方が全然足りない。
患者さんに限らず、大切にすべき人たち全員に言える話だと思う。
となって来ると相手への話。
本質的に大切なのは相手の事をどれだけ考えれるか。
良い面も悪い面も向き合う。
というか善悪なんてないから。
それがどの様な現れ方をするかというだけ。
わかっていたら躱せるものも増えてくる。
親友と
友人に体を診せて貰った。
ベロ見せてといってベロは出せるけど
裏見せてと言って裏返せない。
こうできる?とやって見せて、
それでもできないみたい。
無意識にか指をベロの下に入れて裏を見せてくれようとしている。
モゾモゾと動くだけで、やはりできない。
人のそんな様子を目の当たりにした。
激しく上気していて、喋り始めるともうとまらない彼に
少しでも落ち着いてもらえるように鍼をさせてもらった。
経験
===========================
2021/11/16 『経験』
さらけ出してもらったことを受けて動かされるものがあると思った。患者さんから、痛みが少し和らいだ、マシになった、と伝えてもらうことが、こんな風に推進力になるとは以前想像しなかった。そしてまた、それを先生方に共有してもらえることが、自分の内にこんな感情を生むのかと新鮮だった。
===========================
2021/11/17 『得難い日』
届けたいところに鍼を届けらるように。そう考えている時点でもう違ってしまっていることは明確なのに、あれこれ考えがよぎるし、体が硬い、頭も硬い。そんな折、院長から意識の置き方について話して頂く機会があった。同じ日、下野先生から、体の使い方について具体的な指導をして頂いた。得難い日について、これ以上書きようがないくらいです。
===========================
2021/11/24 『お腹』
裏熱を孕むお腹。実際の患者さんのからだを診せてもらう中で、手で触れることを通して、裏熱という言葉が採用されているその意味が少しだけ知れたと思った。
触れて、感覚として最初に覚えたのは、鈍い・鈍磨、ということ。そして、そう感じたのには、皮膚表面付近がいやに分厚く感じられることが関係していると言えそうだと考えた。この厚みは何がもたらすのか?また、分厚さが遮蔽しているためか内側からの温感が感じにくい。もっと他にも、何か絡み合ってこじれた感じも受ける。通りにくいのは熱だけか?熱は籠り、その熱はどこへ移動する?体のほか精神面ではどの様に影響するのか?検討を続けたい。
臓腑の気
お久しぶりです。高山将一です。
風邪で長患いしまいました。
今日からどしどし疑問や、学び、気づきを述べていこうと思います。
初歩的な疑問が前々からあったのですが、「臓腑の気」とはいったい何を指すのでしょうか?
一つは臓腑の機能、もう一つは、気の一種を意味しているのか?
多くの本には、脾気や、肝気は、その臓腑の機能を指すと書いてあります。
しかし、病機には、たとえば、なんらかの原因で脾気が
化生出来なくなって、運化機能の失調で、食欲不振や、
精神疲労が見られるとあるが、
この場合、「脾気が化生出来なくなって」とあるので、
機能を指しているのではなく、物質としての気を指していると考える。
また、
臓腑の機能は、臓腑本体が機能しているのか?それとも
臓腑の気が臓腑の機能を果たしているのかも疑問です。
例えば、脾の運化、統血は脾本蔵が機能しているのか
それとも、脾気が働いているのか、
それとも、両者共に働いて機能するのか、疑問です。
この捉え方の違いで大きく治療法が変わってくるような気がします。
患者、食べ飲み など
患者
今週寺子屋で見せて頂いた患者さん、もし自分があの人ならどういう気持ち、体になるか。
声や様子から色々気にされそう。
治療してなかったら心臓が心配だな。
生殖器関係に問題はないかな。
気逆を起こして気にされやすいだろうから、言葉遣いはどうした方がいいかな。
敏感そうだから特に時間をかけたらいけないな。
拾えなかったけど本当に心経の辺りに反応がなかったんだろうか。
あの状態なら出やすいと思うんだけれども…
食べ飲み
先日友人の結婚式があった。
そこでのスケジュールが11時〜披露宴 15時〜二次会 と言った胃腸にとってのハードスケジュールだった。
家に帰ってお腹を触ると胃がパンパン。
足では地機が硬くなっていた。
浅めに刺しても痛かったのですが、腹満は楽になりました。
舌の変化も見ていたのですが、翌日の変化など特に勉強になりました。
また、大人数は大変だなと改めて実感。
自分の課題です。
感覚
本を読みながら何かを触る。
何も見ずに何かを触る。
感覚が全然違う。
触覚だけでなく、全ての感覚がそうだと感じる。
今、きちんと周りの音を拾えているか?
それがノイズの様に聞こえるか、キチンと聞こえるかは自分の状態によって違う。
そこを聞こうとすれば別のものを拾い溢す。
こちらから行くべきじゃないんだろうな。
結局それが何なのか?とその場で気にしてる時点でダメなんだと思います。
実験
↑の事を考えていて、先週の寺子屋ではできる限り周りの状況観察に努めてみた。
やり始めの少しの間はいい感じだったのですが、ずっとやっているとしっくりとこなくなりました。
停滞するといい感じじゃなくなる。
一気にその場の空気とのギャップが出てくる感じがしました。
理論から実践しようとしましたが、これは無理だなと痛感。
実践から理論なら可能なんだと思います。
経穴
勘違いかもしれませんが、その穴に対してどういう認識を持つかで効果が変わってくると、何となく感じた出来事がありました。
補寫といった話ではなく、刺し方でも全く違う目的になるのではないのかなと感じています。
背中
知り合いの身体を借りれたので刺させて頂いた。
普段は腹などでみますが、その時は背中で変化を追ってみた。
脾募と脊柱など一致する部分が見られて勉強になりました。
痛みの誘因と脈状と
痛みを訴えられるのは左側の股関節。
脈弱、左右では右手で捉えにくいと感じる。
とくに右側関上で弱く感じられる。
その他の所見から脾胃に一定の弱り、
また津液不足があることを拾いつつ
主訴との関連性は不明ながら、
数カ所に鍼を置き立ちあがってもらいどうか尋ねると
最初より痛みが強くなったと言われる。
この時、脈に大きな変化はない。
疎通目的で同側、経絡の走行上に取穴したところ
ここで脈が変化、左側の捉えにくさは感じられなくなり、
今度は先程までの痛みは軽くなった。
来院された時より軽減していた。
一穴目からの取穴含めて
脈状の変化の関連性については今は不明。
どのくらい経れば整理されるのかも分からないが
経験として留め置く。
中国の思想(05)
老子
六十六章 統治者はへりくだらねばならぬ
江海所以能為百谷王者、以其善下之。
故能為百谷王。
是以欲上民、必以言下之、欲先民、必以身後之。
是以聖人、処上而民不重、処前而民不害。
是以天下楽推而不厭。
以其不争故、天下莫能与之争。
江海のよく百谷の王たるゆえんは、その善くこれに下るをもってなり。
故によく百谷の王たり。
ここをもって民に上たらんと欲すれば、必ず言をもってこれに下り、
民に先んぜんと欲すれば、必ず身をもってこれを後る。
ここをもって聖人は、上に処るも民は重しとせず、前に処るも民は害とせず。
ここをもって天下推すことを楽しみて厭わず。
その争わざるをもっての故に、天下よくこれと争うことなし。
(引用:『中国の思想[Ⅳ]老子・列子』P105~P107)
《私議》
以前、会社員をしていた時は『人・物・金』を管理するのが仕事でした。
その時の上司からよく言われたのが「頭を垂れる稲穂かな」。
経験豊富な年功を積まれた方々の立ち居振る舞いをみて、
内心『流石!』と思う事は本当によくありました。
今は臨床に立っておりますが、患者さんを目の前にして思う事もあり、
繊細さも難しさも感じます。
【参考文献】
『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店