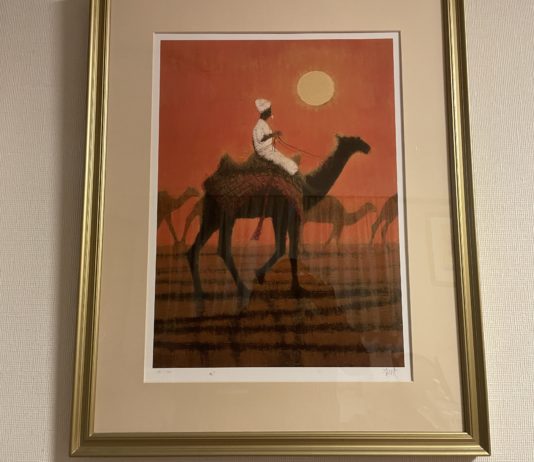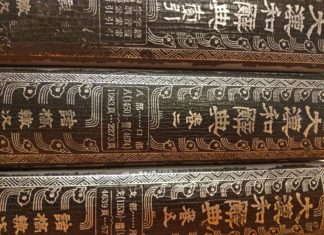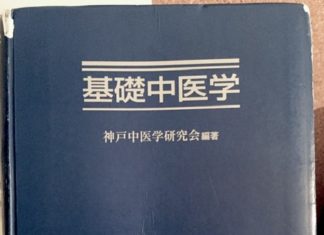風寒邪の咳嗽から穴性を学ぶ④
前回の続きです。
中医鍼灸 臨床経穴学 P25
「風寒外束、肺失宣降(風寒の邪による宣降失調)
症状:喉が痒い、咳嗽、痰は稀薄である。鼻閉、鼻水。声が重い。または発熱、悪寒、頭痛。無汗。舌苔薄白、脈浮など。
処方:中府、風門、大椎(瀉)…疏風散寒、宣肺止咳。」
残りは風門・大椎の意味を考えてみます。
この組み合わせは風寒外束時によくセットで使われている様です。
差別化してみると、
同書籍 P335
「効能鑑別 風門、大椎、列欠、外関、合谷
この5穴には、ともに解表の効があるが、格穴それぞれに固有の特徴がある。
①風門:去風疏衛解表、宣肺の効がある
②大椎:宣陽退熱解表、項背部の表邪を解表する効がある
③列欠:疏衛解表、宣肺、止咳、平喘の効がある
④外関:清熱解表、上焦の熱を清熱する効がある
⑤合谷:去風疏衛、清熱解表、宣肺、清肺の効がある」
穴性学ハンドブック
風門は風類腧穴に分類され、効能では瀉で疏衛宣肺(+灸で祛風散寒)
大椎は寒類腧穴に分類され、効能では瀉で宣陽解表(+灸or焼山火or吸角で解表散寒)
→ともに解表作用ではありますが、風門は去風、大椎は散寒解表に重きを置いている印象を受けました。もう少し掘り下げてみます。
中医鍼灸学の治法と処方 P259
宣肺止咳法「風門:風門は熱府といい、足太陽膀胱経と督脈の会であり、風寒邪が侵入する門戸である。同穴と大椎を合用すると、疏風散寒・発汗解表が可能となる。」
→逆に言えば、風門は大椎と合わせないと疏風散寒・発汗解表が可能でない状態なのだと思いました。
一方、大椎から考えてみると、
中医鍼灸臨床経穴学 P751
「列欠(瀉)を配穴すると、発汗解表、宣肺平喘の作用が生じる。同作用は湯液における麻黄湯(「傷寒論」方)の効に類似している。」
→つまり風門の代用が列欠でも務まるのだと感じました。
もう一度P 25に戻ると
①風門:去風疏衛解表、宣肺の効がある
②大椎:宣陽退熱解表、項背部の表邪を解表する効がある
③列欠:疏衛解表、宣肺、止咳、平喘の効がある
④外関:清熱解表、上焦の熱を清熱する効がある
⑤合谷:去風疏衛、清熱解表、宣肺、清肺の効がある
→つまり大椎+疏衛解表、宣肺の作用があれば、大椎+風門と同じことが再現できるのではないか?と思いました。
大椎はこう言った状況で変えの効かないものなのか、
また探してみて見つかればなと思います。
参考文献:
中医鍼灸臨床経穴学 東洋学術出版社
穴性学ハンドブック たにぐち書店 P131、182
中医鍼灸学の治法と処方 東洋学術出版社
舌診(04)
舌苔について整理する
【苔色】
白苔
表証を示し、傷寒の太陽病や温熱病の衛分証でみられる。
黄苔
熱証を示す。表に熱が留まったり、邪熱が裏に入ったり。
化熱もあり表寒化熱や陽虚の水湿不化をあらわす。
灰苔
裏証を示し、裏熱・痰飲・寒湿などでみられる。
黒苔
裏証を示し、熱極か陽虚寒盛など病変の重篤な段階でみられる。
緑苔
瘟疫や湿温などであらわれ、湿熱・痰飲などの化熱が考えられる。
霉醤苔
紅・黒・黄の混ざった苔で、湿濁が長期にわたって化熱を示す。
【参考文献】
『中医臨床のための 舌診と脈診』医歯薬出版社
『新版 東洋医学概論』医道の日本社
噯と曖
読み物で、漢字の微妙な使い方の違いに時折立ち止まる事があります。
例えば、『井、滎、兪、經、合』の”滎”が”榮”となっていたり。
「ん?」となってしまう時です。
今回は”噯”と”曖”について
口へん、日へんの微妙な違いなのですが。
噯(あい)
1⃣いき。あたたかい氣。
2⃣おくび。
曖(あい)
1⃣かげる。かげって、ハッキリしない。
2⃣くらい。暗くて見えない。
↓
例:曖昧(あいまい)ハッキリしない。紛らわしい。
つまりゲップは
”噯氣(あいき)”であって”曖氣(あいき)”ではないのですが、この漢字の入れ替えが多いように思います。
因みに
”噫気(あいき)”もゲップ。
噫氣(あいき)
1⃣吐き出すいき。呼氣。
2⃣おくび。食べた過ぎた時など、胃にたまったガスの口腔外に出るもの。
噯氣(あいき)
1⃣おくび。吹呿。噫気。
噯の意味より、噫氣よりも噯氣の方が少し温度が高いゲップに感じるのは気のせいでしょうか。
【参考文献】
『大漢和辞典』(株)大修館書店
備忘録(1)
アルバイトとして障害者の介助や老人の介護をおこなっておりますが、
今回は、とある方の入浴を介助いたします。
洗髪の際、
ゴシゴシ、ゴシゴシ、、
Aさん「もっと強くして下さい。」
稲垣 「大丈夫ですか?それでは。」
ゴシゴシ、ゴシゴシ、、(結構強くしてるけど大丈夫かな?)
Aさん「もっと強くして下さい。」
稲垣 「(゚д゚)!えっ(マジで!)。わかりました。」
ゴシゴシ、ゴシゴシ、、
Aさん「強くやり過ぎて、昔は血が出たことがあるんですが、それが良いんです。
HAHAHAHAHAHA。」
稲垣 「・・・。」
Aさん「でも、寝不足の時は強さに耐えれない時があるんです。」
★ ”養蔵”できない事での、”皮毛”への影響を思う。
脈診について
長い年数をかけて習熟していくものと習う
書籍では列記されているけど、
遅数をみるのと、浮沈や虚実をみるのとでは全然ニュアンスが違うと考える
「ぴんと張った弦に触れたように、まっすぐで長くはっきりと触知できる」
このような書き表し方になるのは
脈気を捉えるためには、実際指先に触れる感覚を通して行うことになる為で
時間をかけて養っていくべきは、脈状分類の技術というより、脈に触れてリンクするため
の意識の向け方なのかも知れない
そもそも、この考え方は全くの検討違いなのかも知れないが今は分からない
疑問が変化した記録として
腰の弱点
===========================
2021/09/27 『腰の弱点』
自分の腰部における弱点、第2-3腰椎周りで相変わらず左右差が大きいことを再確認。左側に力なく、右側に張る・凝る・隆起する。左の空虚な感じは、怖さを伴う。
上がりがちな重心と結びつけて意識したことが無かったが、関連しないわけがない。
また、人それぞれにそうした癖をもってバランスを取っている状況、その中にあるからだを診せてもらっていることを留意できるように。
===========================
2021/09/28
この枠の中で考えておけば良いんじゃないか、ここは場に合わせておけばまとまるんじゃか、前回の流れを踏襲しとけばいいんじゃないか。
考えているようで全然考えていない。
===========================
2021/09/29 『むら』
1本目の置鍼の前と後で、反応の変化を追う。脈状で沈位に経気が行き届いたのをみる。舌診では、舌裏が色褪せた状態から巡っているときの明るさを帯びた色調に変化していた。
先輩から、観察した内容について問われた時に、脈のみの変化だったとそのとき答えたのはなぜか。
符合する情報としない情報
何をもって採用して、しなかったのか
大事な点を詰めることを怠る
===========================
2021/09/30 『寺子屋で』
舌を観察して各々考えを述べる 述べ合う。交わされる言葉の内容が換わり始めた。
学校でのことを振り返ると、こういう場は持つことができていなかった。体の所見の情報を拾う感覚を養うための基礎が完全におざなりなものになっていた。
===========================
2021/10/01 『感情』
怒るとき、身体の感覚に向けられる意識はたちまちに粗雑になる。下方ではなく上に向かう、突き上げる。度がキツいと鼓動は速くなりさらにその体勢を助長する。感情は全身反応。
疏泄を担う肝の気機を狂わす種となる。いまはこの切り口で読むのがしっくりとくる。
逆子の灸
学校の授業で、
逆子に効く灸は至陰であり、鍼灸師ならみんな知っている有名な経穴の一つだと教わりました。
でもなぜ至陰が逆子に効果あるといわれているのか?理由が気になるので調べてみました。
逆子は中医学では「腎の気に問題がある」と考えられる。
至陰は腎経ではなく膀胱経なのに、なぜつかわれるのか?
腎と膀胱は表裏の関係にある
中医学では表裏を応用した治療法が多様され、1つ1つのツボまで陰陽や五行に分類する。
至陰は「金」に属し「金」は「水」の母。
水(腎)を治療するので水の母である金に属するツボを選んでいる。よって至陰がそれにあたる。
(『中医学ってなんだろう ①人間のしくみ』著 小金井 信弘 より抜粋)
至陰を使うことは、逆子=至陰の灸と、ただ暗記するよりかは理解できたのですが、
では、腎経のツボをつかったら効果はどうなのか?
そもそも逆子は「腎」だけの問題なのだろうか?
気になるので、逆子について中医学の婦人科系の本なども読んでみて引き続き探ってみようと思います。
腎の納気について
はじめまして。鍼灸学生の白石といいます。
五臓の生理の基礎について学びなおす中で、
初学者向けに書かれた書籍を読んでも理解が難しいというか、
しっくりこない部分があって、
今回はその中のひとつをテーマに選びました。呼吸について。
五臓では肺がその生理機能として「気を主り、呼吸を司る」とされています。
肺は「呼吸の気を主り、一身の気を主り」ます。
この点は、肺はメインの運動器官であり、気体交換の場にあたるということで
馴染みやすいです。
(一身の気の部分については割愛)
そして呼吸に関して、腎は「納気を主る」とされています。その意味は、
肺の吸入した気を節納して、呼吸を調節する機能をもつことを指します。
学校の授業では、この肺と腎の働きを並べて
「肺は呼気を主り、腎は吸気を主る」とだけ習いました。
言葉として理解はできても、府に落ちない感じが残っていました。
この点について、今回理解の助けとなる説明を得ました。以下の内容です。
「肺は気の主であり、腎は気の根である。肺は出気を受け持ち、腎は納気を受け持つ。」
「つまり呼吸とは、肺と腎が共同してしている仕事であってそうして、
呼吸は浅くはならず一定の深さを保つ。」
「納気という機能は腎の封蔵という性質が呼吸運動の中に現れたもの。」 以上
腎が気を納めるのに対して、肺は実動を担当する臓器というニュアンスから、
肺は呼気を腎は吸気を主る、という言葉が用いられたのだろうと解釈しました。
今後につなげたいと思います。
____________________________________
【参考文献】
『基礎中医学』神戸中医学研究会
『中医学ってなんだろう』東洋学術出版社
滋味深い
滋味深いとは
栄養価に富んで味のよく感じられること。
ゆっくり味わうことで醸し出される味や雰囲気。持ち味がにじみでることによって感じるおいしさ。
母と一緒に長年通っているお店で食事をしたとき、出されたお料理に母が「滋味深い」と感想を述べたら、
シェフがすごく嬉しそうな表情で「滋味深いは最高の褒め言葉です。そういう料理を作りたいといつも思っているので。」と
仰っていたことが印象に残っていました。
鍼の施術でも、
すぐに効果がでるよりもある程度時間が経ってから効果を感じるのが理想と
下野先生がお話されることがあったのですが、
それは料理も鍼も何年もの間、毎日毎日試行錯誤した結果できることで、
滋味深いと聞いたときに、鍼に使う言葉ではないと思うのですが、
一朝一夕ではできないという意味で共通しているものがあるな〜と
お料理を食べながら鍼のことを思い浮かべていました。
仕事の帰りに少彦名神社
少彦名神社
【御鎮座】
道修町には、明暦四年(1658)頃から薬種商が集まっており、享保七年(1722)
124軒が幕府より道修町薬種中買仲間として公認された。
この仲間が生命に関する薬を神の御加護のもとに間違いなく取り扱えるよう、中国の薬祖神・神農氏と共に、
安永九年(1780)京都・五条天神から少彦名命をお招きして、仲間会所(現在地)におお祀りした。(引用:神社の案内より)
(´ー`)
仕事の帰りに足を延ばし、少彦名神社に参拝に行ってきました。
御鎮座より今年で240年という事で、お薬と大阪との長い付き合いを感じます。
学生時代より度々お参りに来ておりますが、卒業後では初めて来させて頂き、試験合格のお礼をさせて頂きました。
卒業し、鍼灸師となった立場で神様に手を合わすというのは違った思いがあります。
本日は梅雨時の隙間、暑さは止みませんが、良い風が吹いていたように思いました。