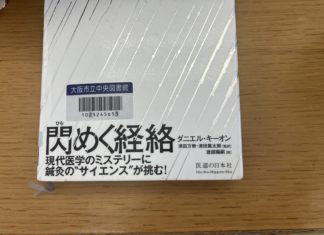様子など
様子
まれに中の様子がわかる事がある。
先週は顕著で、隣の部屋の様子が映像化された。
勘違いかもしれませんが感覚として残しておきたいと思います。
流れ
受付をしていて乱れ始めると何かが起こる。
不思議です。
正しい流れの時は乱さない様に流れに沿っていきたい。
自分の性質
うんざりする事が多い。
その後の立ち上がり方も含めて見直していきたい。
先週聞いたこと
自分の腹でも確認。
取れなかったけど、あの人もこんな感じだったのかな。
次回以降この部位も取れる様になりたい。
力
昔よりは余分なものは減ったと思う。
でも残っている部分がまだまだ沢山ある。
心と体は切り離せないなとつくづく感じます。
脈
人にとらせてもらった。
尺部を深めに抑えた時、全身?で感じる何かがあった。
深みに入れた感覚はあったけど、それが何なのか分からない。
経験として置いておきます。
関衝穴
自分で自分のからだのうえで
経穴の反応を追う中で
様々なことをみる。
関衝穴近くをとるとき
緊張が解けて呼吸が一段深まる
ことが(よく)起こる。
反応はダイレクトで即効性がある。
ただ、自分のからだの上だけのものなのか。
ある方から、
5本の指の中で
体幹に直接繋がっているのが薬指と
教わった時のことが思い出される。
2年生最後の日
2年生最後の実技は色んな情報を生理して計画を立てパートナーに自由に治療をする内容でした。
今まで、頭痛や膝関節痛など想定して先生の決めた配穴を治療する内容が実技のメインでしたが、いきなり自由となると、頭が真っ白になります。
今朝から筋トレによる筋肉痛と口苦があるという訴え。
紅舌 微黄、呼吸が浅い。右手の僅かな顫動、右足の貧乏ゆすり、外踝の乾燥、天枢の冷えと左少腹の拒按、目の充血。後頸がパンパン。
体からどのように情報を得て整理して選穴するか、焦りばかりが先立ってパニックになりました。
気持ちの迷いや自信のなさは治療に反映されるもので、あれこれ施術をしてみても特に結果も得られず、先生が刺した百会のみが効いたようで、「この一穴で良かった」というパートナーの言葉に面目なく、とても悔しい気持ちでいっぱいで授業の後、私も口が苦くなってきました。
先ずは基礎から
ほぼ10年ぶりに東洋医学の基礎理論の本を開いてみました。
結構忘れています。
東洋医学、特に中医学の言い回しって独特ですよね。元々が中国語の表現からの解釈になるせいもあるんだと思いますが、それが余計に理解するのを困難にさせます。
例えば
肝についての記載
陰を体とし、陽を用とす (基礎中医学 神戸中医学研究会 p45参照)
なんのこっちゃです。抽象的すぎて困ります。もっとハッキリ具体的に書いて欲しいものです(笑)
柔肝という文字もよく見ます。
肝の陰血を補うことで、肝陽を調整する治法
肝の陰血をもとに陽気が作動(陰を体とし、陽を用とす)し、肝陰の柔潤によって肝陽の剛強を抑制し、和らげている。 (基礎中医学 神戸中医学研究会 p46参照)
肝陰がなくなると柔→剛強に変貌するとあります。何だか物騒なことになりそうです。
そういえばC型肝炎の治療にインターフェロン療法が行われますが、昔に医療の現場で聞いたことがあります。治療を受けている患者さんの性格がだんだん変貌するそうです。怒りっぽくなったり、抑鬱症状が出たり、そうなると家族は大変なようで、そういう症状が強いと治療を一旦中断することも多いそうです。もしかしたら東洋医学的に考えてみると、インターフェロンによって肝陰が傷つけられてしまうのかもしれません。
脂漏性角化症
20代の頃から、顔の一部に繰り返しできるイボに悩まされており、
イボの範囲が広がるタイミングに毎回皮膚科を受診してきた。
診断名は「脂漏性角化症」別名、老人性疣贅といわれるもので、はっきりとした原因は不明だが
老化や紫外線の影響ではないかといわれた。
20代で老化が原因といわれるのは全く納得がいかなかったが、
当時、部活で真っ黒に日焼けをしていたためそのせいかなと思い、
日焼け止めをせっせと塗り、皮膚科で処方されたイボによいといわれるヨクイニンをのみ、
病院で液体窒素(ものすごく痛い)で患部を治療してきた。
しかしそれでも完治することはなく現在(かれこれ20年弱)にいたる。
東洋医学にふれるうちに、私は瘀血の症状がわりと強いし、
完治しないこのイボもも
私の場合はもしかしたら瘀血が原因なのでは?と思うようになった。
シミも紫外線が原因といわれているし瘀血の特徴の一つであるので、
私を悩ませたしつこい脂漏性角化症も紫外線が一つの原因なら瘀血がよくなれば効果がでるのでは??
イチ鍼灸学生の、つたないひとつの仮定ではあるけれど、今後の経過を自分の身体で検証していこうと思う。
東洋医学の用語に関して
今月初旬より、寺子屋でお世話になっております。
初めて東洋医学の本を読ませて頂いておりますが、用語に関して、特有の世界観を感じました。
例えば、五臓におきまして、
西洋医学では具体的な臓器を意味しますが、東洋医学では機能を意味するということ。
(東洋医学において人体は神様であるため、解剖しないことが前提にあると教えて頂きました。)
五臓をはじめ、用語全般に広い意味合いを含んでいる印象を受けました。
つい、正確な意味を知りたくなりますが、
限定しすぎないからこそ他部位と関連性を持ち、全体を見る(森を見る)東洋医学の世界観に合うのかな、と感じました。
まだまだ、捉え方が曖昧ですが、浅くでも読み進めていこうと思います。
側・舌
側
豊中院で先生の身体をみさせて頂いた。
先日寺子屋でここを見といてくださいと言われた部分に反応があった。
中に差し込んでいる様な形。
背候診の時もついでに触って様子を伺う。
停滞している印象。
少陽枢機不利が原因かと思った。
舌
今日患者さんの問診、切経などさせて頂いた。
その患者さんを含めて思う事。
舌を見て、
「子供の様な舌だな。」
と思う方がちらほらいる。
このあたりは持って生まれたものではなく、臓腑の現れ方として共通するものがあると思う。
水の溢れ方も特徴的。
お灸のダメージを減らせるか など
受付にて
仕事をしていて、ある時に先生にあるべき景色を見せて頂いた。
イメージされたのは波打たない湖の様な景色。
静かでどこまでも続く様でした。
頭ではわかったつもりでも体感して深みを知る。
以前院長も見せて下さった様に思うがまた違う景色。
とても良い経験になりました。
お灸のダメージを減らせるか
月曜の授業内容に百会に置鍼というものがあった。
切皮→弾入→5分くらい置鍼→抜針といった感じ。
ただやった事あるしあんまり置かれたくないので切皮したらすぐ抜いてとお願いした。
それだけだとあまり変化なし。
しばらくして自分で思うやり方ならどう変化するだろうと思って
同じ種類の鍼で置鍼はなしという基本的な条件は同じで施術してみた。
結果として起立性低血圧のような眩暈を引き起こす事ができた。
月曜、火曜に膀胱経辺りに過去最大量のお灸を受けるのでちょっとでも防止できないかなと実験してみました。
鍼の感覚も含めて勉強になりました。
左右対称
ずっと体の癖を治す為に色々工夫している。
その中でもふと自身の右目が乱視である事に気づく。
知らず知らず左ばかり使っていれば顔の中心から見ていない訳でズレも生まれやすい。
という事で今家で左目に眼帯をつけて過ごしています。
発見として面白い事が右目ばかり使うと体は右軸で動き始めるという事。
使っていない部分が使われたのか体のアチコチがバキバキいいます。
閃めく経絡
以前から気になっていた本を読んでます。図書館で借りれました。
「閃めく経絡」ダニエル・キーオン著
私は今まで東洋医学について記した本で、西洋人が書いた本を読んだことがありませんでした。振り返れば、ほぼ日本人か中国人で、韓国人は1人か2人くらいでしょうか。なのでとても珍しく感じました。ちなみにこの本はアマゾンでも好評価です。
著者はどんな人なのかと見てみたところ、救急診療専門医のイギリス人で、中国に留学して鍼灸を学ばれていたようです。
なので、もともと現代医学に明るく、特に発生学が得意なのか、その知識の上で鍼灸を学ばれて感じたことを掘り下げ、分析して想像した内容になっているのかなぁという印象を受けました。
著者は、「発生学からの知識に数学を取り入れて、鍼灸がどのように作用するか理解するようになる方程式を作り上げる。それは無限に複雑で美しい形であると同時に洗練された単純性を表したものになる。」ということを記しています。
今まで東洋的な言い回しに慣れてきた私には、いかにも西洋的な文面だなと感じざるおえませんが、このような考え方で西洋医学はここまで発展してきたのだろうとも思います。
まだ、この本を半分くらいしか読んでいませんが、著者は「気」とは何か、なぜ「経絡」がこのような配置になっているのかを、人体がどのように発生し、どのように作用しているのかを理解すれば明らかになると考え、発生学の見地から答えを見出そうとしています。
この後の展開が楽しみです。
近年、西洋圏でも東洋医学が盛んに学ばれ、人気があると聞いています。そうなることで、この著者のような人も増えてきて、今までになかったいろんな切り口で考えられるようになり、東洋医学もより発展していくかもしれません。そしてそうなればいいなとも思います。
張景岳曰、
明清時代、痰に関する研究は日増しに整備されていった。
張景岳は「痰には虚と実とがあり、・・・最良の治療は、痰を発生させない事である。これが天を補うということである。」
と述べている。(『中医病因病機学』第20章 痰飲病機)
気になりましたので備忘録として置いておきたいと思います。
先生方で『景岳全書』を購入するなら、”この出版社がおススメ”などあればご教授頂ければありがたく思います。
【参考文献】
『中医病因病機学』東洋学術出版社