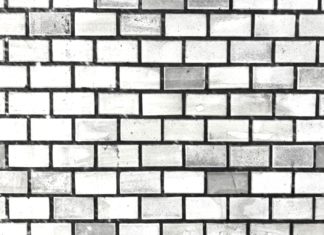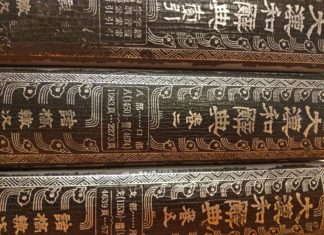歯痛
学校の東洋医学の授業で歯痛(歯に関係のない歯周辺の痛み)についてを習う。
私も歯痛になったことがある。痛みの性質としては、
痛みの場所は上の時もあれば下の時もある動く→気滞?
キリで突かれるような刺痛→瘀血?
灼熱感を伴う痛み→熱証
下顎から歯根にかけて走る痛み→?
触ると鈍痛、歯肉腫脹
いろんな痛みが混在していたので、教科書の病症のように1種類の痛みでは例えられないし、病因も単純そうではない。教科書や病症分類は極端な例しか載っていないのではないか。
教科書では病症の一例として、肝火上炎で歯痛が起こると書かれている。
現在もストレスを感じた時は当時の1/10ぐらいの痛みが稀に再現される。
当時の歯痛は随伴症状と照らし合わせると、肝鬱気滞もしくは、肝火上炎への移行期だったのではないかと考察する。
今なら脈や舌も見て他の視点からも考察できるのに…と思うが、やっぱり歯痛は嫌だ。
客氣の”客”
景岳全書 伝忠録
夏月伏陰續論
『主氣と異なるものとして、客氣がある。天は五氣を周らし、地は六氣を備えている。・・
・・この客氣は冬であろうと夏であろうと、その季節とは異なる氣を引き起こして、人々を病気にさせる氣である。・・』
『夏期になると陰気は伏して内にある。これは本来、天地の間における陰陽消長の理である。・・』
の冒頭から始まるこの篇ですが、
朱丹溪との陰陽の考え方の違いを解説し、張景岳の持論を展開している章になります。
この章を咀嚼した内容は別の機会に上げさせて頂くとして、
ときおり出てくる”客”が気になりましたので、調べてみる事としました。
【客氣(かくき)】
1⃣一時のから元気。血氣の勇。假(仮)勇。
2⃣其の歳の運を動かす外部から來る運気。主気に對(対)していふ。
客
①よせる。よる。身を寄せる。
②まらうど(客人)。主の對。
③上客。一座の尊敬する人。
④かかり人。
⑤外來人。
⑥あひて。
⑦たびびと。
⑧たび。
⑨居處(いどころ)の定まらない者。
⑩人。士。
⑪とくい。得意。顧客。
⑫來しかた(過ぎ去った時)。過去
⑬姓。
この夏月伏陰續論の客氣に関していえば、主たる氣とは別の
「病をもたらす得体の知れない氣」といったところでしょうか。
景岳全書の後の章、「命門余義」の中には
『・・三焦の客熱として邪火がある場合も火が原因となっているのであり、・・』
とあります。この客熱もまた、主体の火化とは異質の火に感じられます。
經穴では、
小陽胆経の經穴で上関穴を別名:客主人といいますが、この場合は
「頬骨弓を挟んだ、下関穴の相手方」という意味として、鍼灸学校で教えて頂きました。
その意味合いだけなのかどうか、今後の新たな発見を目指したいと思います。
【参考文献】
『大漢和辞典』大修館書店
『新版 経絡経穴概論』医道の日本社
『現代語訳 景岳全書 伝忠録』たにぐち書店
食べることについて②
皆さまこんにちは、イワイです。
前回の続きです。
〝後天の精〟とは生まれ持った〝先天の精〟とは別に
飲食物から補います。この後天の精の全身へのルートをみてみますと、
後天の精
↓
別名 水穀の精微といわれる
↓
一部は気、血に化生→全身の組織、器官に行き渡る
↓
残りの一部は 腎 に収まる
となっています。
次は〝精〟の作用についてです。①〜③
①生殖
②滋養→人体の組織、器官に滋養する
詳しくみてみると、
精は必要に応じて、血へ変化。
↓
血も旺盛、正常に各組織、器官を滋養。
精は気へ化生。
↓
人体の新陳代謝を推動、抑制し生命活動を維持する。
精は人体を構成する基本物質と捉えられており、
東洋医学では精が充足していると、
生理機能は正常に働くと考えられています。
③神の維持
神:広義では、生命活動の総称であり、精が充足することで、神の機能が保たれる。
狭義では、精神、意識 、思惟活動を主るもの。
ここからは、勉強した感想です。
飲食物を食べることで、西洋医学的に考えるとエネルギー源となるということ、一方で東洋医学的に考えると、エネルギー源という役割と五臓六腑が正しい働きを出来るようにしていたり、精神活動も主ることになるので、幅広い意味で捉えることが出来ることに気づきました。
【参考文献】
『新版 東洋医学概論 』東洋療法学校協会
個人的によく読む、東洋医学・鍼灸関係のBlog
ツボ探検隊
http://www.shinkyu.com/index.html
兵庫県神戸市東灘区住吉にある、松岡鍼灸院さんの、各種Blog記事です。
香杏舎銀座クリニックさんの各種Blog記事です。
漢方医
https://www.higasa.com/blog/kanpoui
漢方医2
https://www.higasa.com/blog/kanpoui2
香杏舎ノート
https://www.higasa.com/blog/note
保険漢方の終焉
https://www.higasa.com/blog/endik
民間治療見聞録
https://www.higasa.com/blog/memoirs
神戸東洋医学研究会
http://kobeemf.com/
気功や鍼灸について、阪神間で色々と活動されてるようです。
清明院院長のブログ 最高の鍼灸の追求
http://www.seimei-in.com/wp/
東京都、新宿駅の近くで「清明院(せいめいいん)」という鍼灸院を営んでおられる、竹下先生のブログです。
このブログに初めて訪れた方へ
http://www.seimei-in.com/wp/b1017/
一鍼堂さんのブログは、当然よんでます。
随時、追加、編集していきます。
他にも良いブログがあれば、ご紹介していただければ嬉しいです。
腹診で 2
(前回の続き)
症状としては
・気鬱
・浮腫み(下肢)
・睡眠は浅く、悪夢が多い
以前にお腹が似た状態だったときも、気鬱があった。
“分厚さ”は何がもたらすのか。
浮腫みとの関係か、精神状態や気鬱の表れか。
処置後には「硬さ」の密度が少し下がり、
ゆとりが生まれた印象を受けた。
張景岳曰、
明清時代、痰に関する研究は日増しに整備されていった。
張景岳は「痰には虚と実とがあり、・・・最良の治療は、痰を発生させない事である。これが天を補うということである。」
と述べている。(『中医病因病機学』第20章 痰飲病機)
気になりましたので備忘録として置いておきたいと思います。
先生方で『景岳全書』を購入するなら、”この出版社がおススメ”などあればご教授頂ければありがたく思います。
【参考文献】
『中医病因病機学』東洋学術出版社
八綱弁証
学校で中医学の基礎として教わり、
それからは、考察を立てるうえでの
基礎においてきた。
ただしこれまで、そこに
何故その方法を用いているのか、
そうした視点がまったく抜け落ちていたことを
気付かされた。-蝶番-
一緒に学ぶ者が、
同じポイントで先生の言葉にうなづいている、
そんな空間が無性に嬉しく感じられた。
これもひとつの小さな発見だと思った。
関衝穴
自分で自分のからだのうえで
経穴の反応を追う中で
様々なことをみる。
関衝穴近くをとるとき
緊張が解けて呼吸が一段深まる
ことが(よく)起こる。
反応はダイレクトで即効性がある。
ただ、自分のからだの上だけのものなのか。
ある方から、
5本の指の中で
体幹に直接繋がっているのが薬指と
教わった時のことが思い出される。
今日の気付き
今日は白石さんの舌の写真を撮りました。
なかなか思うようにうまく撮れない・・。
教えていただいたコツを忘れないようメモして次回の撮影に活かします。
その後、腰の調子がイマイチと白石さんがお話されていたので、腰をみさせてもらったところ、
左の腰が右にくらべ張っており色も暗い感じがあったので、そこばかりに意識がいっていたのですが、
診る人によっては右の腰のほうがよくないと言われることもあるよ〜とお話されていました。
考えが偏りすぎて情報を見逃してはいけないですね。
まだまだ私の視野が狭いので毎回毎回学ぶことばかりで、勉強会、楽しいですo(´∀`)oワクワク
施術日記(03)
T.I 先生との治療練習3回目です。
週ごとに、同じ経脈上に刺鍼する事で変化をとります。
舌診の鍛錬
【目的】
① 一週間前と同穴にて、鍼の番号を変えて違いを診る。
② このシリーズは今回で3回目。
鍼の ”前後” という短期的にできる変化とは違う、中期的な変化を探す。
舌の中央の苔・裂紋には長い歴史を感じるので、
この変化を狙うのは、
長期的に考えなくてはならないのかもしれません。
舌尖と舌辺の赤みは、ぼんやりといつものようにある。
舌の出し方に、強張った感じはみられない。
陰陵泉(右):0番鍼にて置鍼(5分)
一段と力が抜けたように感じる。
刺鍼後には舌尖と舌辺の赤みは、淡く穏やかになるのはいつもの通り。
舌の水分量の違いが、事前事後で間違いなく変化する。
2週間前は・・
この2週間前に舌診した際、
舌の出し方が右へ傾いていたのが特徴的でした。
舌尖の尖がり具合や舌の周辺の赤みは現在もありますが、
現在は少しマイルドになっているように感じます。
ご自身で治療をされているのもあり、
このシリーズでの正確なエビデンスという訳ではありませんが、
変化は感じられます。