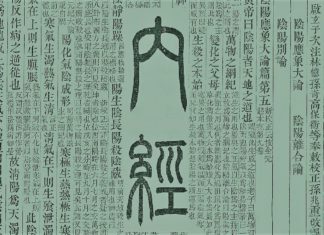側頭部痛 1
ある方の体を診せて頂いた。
肋骨弓あたりを中心に
比較的軽い、動きはあるけど
そこに停滞する感じ。
臍下から下焦に向けて
もっと硬くて重い、キツい感じ
動きがすぐには見られなさそうな印象。
脈象では
沈位で案じて潰れる様が見られた。
(続く)
湧く泉
最近、母親に鍼をしています。
体表観察の練習に観させてもらってるうちに、ちょっと打っておこうかなと選んだツボが湧泉でした。足裏にあるので普通は他人に打つのには躊躇しがちなツボかと思いますが、そこは家族なので変な遠慮もありませんでした。本人も痛くないとも言っているので、実家に寄った時にはお決まりのように打っています。
何年も前から、母親から足の異常は聞いていて、足の裏から指先にかけて痺れた感じがあり、本人にとってかなり気持ちが悪く気になっているみたいでした。病院で診てもらったことがありましたが、特に異常はないと言われて治療はされなかったようです。ひどい時には指先が赤く腫れた感じになったり見た目の変化も現れるとも言っていました。
私としては、老化が原因で足の屈筋支帯のような神経の通るトンネルがダメになって神経を圧迫して痺れてるのかな?と漠然と想像していました。だからもう治らないのでは?と。
そしたら一回打ったあと、また打って欲しいとお願いしてきました。
本人曰く、鍼を一回打った翌日に何だか足の裏の感覚がいつもと違ったようで、歩いていても足裏の感覚が良くなってる感じがしたそうです。それは回を重ねるごとに改善していると今は喜んでいます。足の甲の氷を載せたような冷えも取れたとも言っています。
湧泉
本穴は足心に位置する腎経の井穴であり、脈気が湧き出す処であるため、湧泉と命名された。
~鍼灸学 東洋学術出版社~
湧泉にそんな力があるんでしょうか。
肺のイメージ
肺のイメージで言うと、他の臓器に比べて綺麗なイメージがあります。
肺には基本的に津液や気しか入らないですが、逆に脾は食べ物が関わるのでドロドロしたイメージがあります。
そして臓器の中で一番上にあって、そこから気をあらゆる
組織や臓器に気を送っているので
偉い感じの臓器なのかなと。
でも、意外と弱々しいく繊細というイメージがあります。風邪が入った時など、真っ先に弱って、咳や悪寒を起こします。
そう考えるとタバコは本当に身体に悪いなと思います。
天空の気の代わりにタバコの煙を吸って、それが肺で処理されて、まず肺が弱ります。その後、実証は持てませんが、
そのタバコの煙が肺の宣発作用で五臓六腑に行き渡れば
新たな害を及ぼしてしまうのではないかなと思います。
タバコが及ぼす病気に肺がんはもちろん、胃がん、心筋梗塞、膀胱癌、脳梗塞etc、、、怖い、
風邪と似てタバコは百病の長なのかもしれません。
肺を大事にしましょう
ps.写真は京都の清水寺に巡礼しました!
肺も清水でありたい!
呼吸・意識・本
呼吸
最近呼吸で自分の状態を整えようとしてチャレンジ中です。
呼吸で
意識している事は吸う→吐く というより
吐く→吸う の意識。
やり方があっているかどうかは分かりませんが、多分丹田呼吸だと思います。
自分なりに良い感覚なんじゃないかと思う潜った、沈んだ感覚に近くなる。
行うと手も少し温くなってきます。
日常での意識
外の世界がどう見えているか
自分の状態によって変わる気がしてます。
夕焼けも見ていて綺麗なんですが、頭の中が思考で占拠されている時はあまり入ってこないというか、外の世界にフォーカスがいっていない。
そんな頭の状態の時は見るものの視点が近くなっていて、全体を見渡す事ができなくなっている。
切診を行う時に何かに着目してしまうと同じ感じがします。
最近気になっている本
最近死を間際にした人の気持ちや考えが気になっていて、そんな感じの本をチラチラ読んでいます。
最近読んでいるのは吉田松陰の留魂録で、獄中で死が確定していても冷静ですごい人だったんだなと勉強させて頂いてます。
冬休みは夜と霧を読んでみようかなと計画中です。
脈診で感じたこと
ある方の脈を診せてもらった。
浮 •中では抵抗がなく、触れている感覚に乏しい。
脈上においた指をぬるりとかわすように進む。
テンポは一定。脈幅の細さもあってか
陰の気配が強い印象。(分類は滑脈か?)
処置後には、雰囲気がまるで変わり、
脈幅は同じく細いが、なかに芯ができて
充実した印象の脈となる。
良い経過が見込める、そう予感させるものがあった。
経過を見守りたい。
側・舌
側
豊中院で先生の身体をみさせて頂いた。
先日寺子屋でここを見といてくださいと言われた部分に反応があった。
中に差し込んでいる様な形。
背候診の時もついでに触って様子を伺う。
停滞している印象。
少陽枢機不利が原因かと思った。
舌
今日患者さんの問診、切経などさせて頂いた。
その患者さんを含めて思う事。
舌を見て、
「子供の様な舌だな。」
と思う方がちらほらいる。
このあたりは持って生まれたものではなく、臓腑の現れ方として共通するものがあると思う。
水の溢れ方も特徴的。
順気一日為四時篇 第四十四(01)
黄帝曰、願聞四時之気。
岐伯曰、春生、夏長、秋収、冬蔵、是気之常也、人亦応之。
以一日分四時。
朝則為春、日中為夏、日入為秋、夜半為冬。
朝則人気長、長則勝邪、故安。
夕則人気始衰、邪気始生、故加。
夜半人気入蔵、邪気独居干身、故甚也。
黄帝曰く、願わくば四時の気を聞かん。
岐伯曰く、春は生、夏は長、秋は収、冬は蔵、これは気の常なり、人もまたこれに応ず。
以て一日を四時に分つ。
朝は則ち春を為し、日中は夏を為し、日入は秋を為し、夜半は冬を為す。
朝は則ち人気が長じ、長則ち邪に勝り、故に安なり。
夕は即ち人気が衰え始め、邪気が生まれ始まる、故に加なり。
夜は人気が蔵に入り、邪気が独り身に居り、故に甚だしきなり。
【参考文献】
『黄帝内経 霊枢 下巻』東洋学術出版社
春
試験が終わり、色んなことに挑戦する余裕が出てきました。
色々調べていくと、1、2回生の時の様に好きな事に浸かっていき、その中で想像が膨らんで楽しいです。
最近は「生きるとは何なのか」といったテーマで調べ物を進めています。
その中で季節感というものも改めて取り入れたいと思いました。
今の季節で言うと春に何を感じるか。
1日1日と変わりますが、今は冬のキリッとした厳しさに比べてフワフワする日が多い様な…
色々体感しながら学びを進めていきます。
中国の思想(04)
老子
二十六章 ”静”は”動”を支配する
重為軽根、静為躁君。
是以聖人、終日行不離輜重。
雖有栄観、燕処超然。
奈何万乗之主、而以身軽天下。
軽則失本、躁則失君。
重は軽の根たり、静は躁の君たり。
ここをもって聖人は、終日行けども輜重を離れず。
栄観あるといえども、燕処して超然たり。
いかんぞ万乗の主にして、身をもって天下より軽んぜん。
軽ければすなわち本を失い、躁なればすなわち君を失う。
(引用:『中国の思想[Ⅳ]老子・列子』P63)
《私議》
修行中の身において患者さんを診させて貰う際、
”上逆下虛”の場合には、陰陽の重りの方をしっかりと保つ事を考えます。
四診合算において、そのままスタンダードで良いのか悪いのか、、
足りていない情報をかき集めるのに必死になってしまいます。
問診に於いても、患者さんとの間合いに注意しないといけないな・・と思う日々です。
【参考文献】
『中国の思想[Ⅵ]老子・列子』徳間書店
歯肉炎の治法
先日、左下の歯の虫歯治療で麻酔をした後、歯肉炎を起こし咽頭が腫れて食欲も落ちました。
内庭穴、合谷穴、下関穴、大迎穴に鍼をしましたが効果がありませんでした。
その日の夜中に顔の熱感と鈍痛で目が醒めました。
舌 やや紅 厚白膩苔
脉 浮、数、滑?
心窩部が重苦しくやや吐気伴う
前日、寝不足で肝火を増長させて、元来脾胃が弱っている状態で脂濃い物を食べてしまい食滞による胃熱が影響したのか。
脾が弱るから腎も弱るし、その逆も。
全てが影響しているようにも思います。
胃熱からくる歯痛には内庭穴と書籍にあり、内庭穴を探ると圧痛がありました。
しばらく置鍼して様子を見ました。
あまり効果を得られなかったので、舌の厚白膩苔が気になり陰陵泉を追加すると次第に痛みも引き脉も沈んでいきました。
後日…
左歯肉の腫れが中々引かない。
左通天周辺に圧痛があり、単刺で痛みが解消。
また後日…
ふた月前から上歯も歯根炎で治療中のため、治療後は炎症と鈍痛があります。
左下の歯肉炎も中々腫れが引かず痛みがありました。
下肢に熱があり、右上巨虚は虚し、左上巨虚に圧痛がありました。
左右反応点にお灸をすると、歯にダイレクトに響き拍動痛が憎悪。
次に鍼をすると痛みが治りました。
痛みを伴う場合は、対処療法も必要ですが、治病求本が大原則だと思います。
正気の弱りで歯肉や歯根が炎症しているので、痛みを取りながら病の本質も治療する選穴ができるように、これからの課題としていきます。