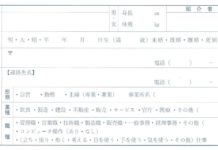猛暑
患者さん
前回寺子屋で患者さんのお身体を借りる際、極力相手がそのままの自分でいられる様に、こちらの雰囲気に引っ張らないようにと意識しました。
相手の雰囲気に溶け込んでいくように意識。
先生の患者さんへのワンクッション挟む様な挨拶なども聞いていて参考になります。
映画
映画、サウンドオブメタルを見ました。
色んな視点や主人公の感情変化が上手く描かれたとても良い作品でした。
内容は突発的に聴力を失った人の話です。
失ったことで生じる世間とのギャップ。
その中でどうにか聞こえるように、元の生活に戻れる様にと試行錯誤しますが、どうも幸せにはなれない。
結局最後のシーンでは色んなものが破綻して喪失、見方によっては悲惨なものでしたが、その中でも主人公が帰る場所を見つかって良かったと感じました。
自分の生活でも聞こえる、聞こえない関係なく帰るべき場所は必要だと思います。
バガボンドの「おっさん穴」が思い返される。
訓練
最近溶け込む訓練として色んな人と会う様にしています。
やはり考えている事は違う事がほとんどで、話していてもやはり人間なので違いはある。
でもその人にはその人の物語があるので合わせる訓練にはなる。
その為には尊重が必要。
昔この先生の考え方好きだな〜と思った人がいて、大体の内容として
「みんな何かしらの夢を見てるんだからその夢に付き合うのも優しさ」
と仰っていた。
優しさというと少し誤解を受けそうなニュアンスに聞こえますが、仰っている意味はわかる。
主観はそれぞれ違う。
相手の物語に寄り添って初めて答えてくれるものなんだと感じています。
きちんと相手を大切にしなければいけない。
ルーティーン
最近は一鍼堂に行く前に難波神社で拝礼してから向かう様にしています。
何を願う訳でもないのですが、そこからが入りやすいので気に入っています。
猛暑
この時期暑くなり、水分摂取が多くなる。
そういった人の話を最近よく聞く。
同じ条件を作ってみるために、自分も長時間運動時して普段よりも水を大量に飲むようにしてみた。
現れた症状は口渇は病まず、胃部の不快感と倦怠感。
先々週みさせて頂いた患者さんも陽明のある部分に熱を持っていたことが思い返される。
激しい運動時、胃にも熱が生まれ、口渇が起こる。
その熱をさまそうと冷たいものを欲する。
胃熱を覚ます意味では一定の冷たいものは正解だと思う。
しかし多くは冷たい水やスポーツドリンクなどをチョイスし、そこに水分も多くなる。
脾が対処できなくなり、湿を溜め込む。
ここで熱+湿という条件が揃った舌を見てみる。
面白いことに表面に泡が貼っていた。
自身の体質的に酒を飲んだ時に出るこの泡。
熱と湿が中焦で発生した時に生まれるもの?
最近モデル患者さんで確認されるお腹の状態にも近づいた。
水分を摂取しすぎることなく、どうにかして胃熱への対処を行う事が必要か。
そういえば西瓜が昔からこう言った時に使われていて、天然の白虎湯とも呼ばれている事を思い出した。
瓜科の植物は熱を覚ましつつ利尿するものが多いのでこの時期は重宝しそうです。
他に自分の体の現象として勉強になった事が尿量の減少。
そこで気になった事が、果たしてよくトイレに行く患者さんが本当に利尿しているか?という疑問。
水をたくさん飲むから出さなきゃと思ってトイレに行くとしても、もしかしたら少量しか出ていないかもしれない。
相手の行動の色眼鏡を抜く訓練にもなり良かったです。
そう思うとその人の行動が自分の思っている通りの状態でない事も考えられるので、四診と結びつかない情報に意味がないと改めて実感しました。
楽しい!
寺子屋メンバーで勉強会をしながら、
それぞれの経験を集めて
あーでもない、こーでもないと話し合い
感じた事を共有する濃密な時間。
とても幸せな時間だと思う。
ひとつ得たヒントから自分の迷いが払拭された時、
急に世界が広がることがって
楽しい!と思えることが更なる原動力になる。
自分になかった身体の使い方、
今日得たものを何万回も繰返し、
身体を作っていくこと。
そして楽しい!と思えることが増えるように
どんどん深みにハマっていけばいい。
六經病機(03)
太陽病病機
【03】邪入經輸
傷寒論
辯太陽病脉證并治上 第五
第十四条
太陽病、項背强几几、反汗出惡風者、桂枝加葛根湯主之。方三。
「太陽病、項・背が几几として強張り、反して汗が出 悪風なるもの、桂枝加葛根湯これを主る。」
辯太陽病脉證并治上 第六
第三十一条
太陽病、項背强几几、無汗、惡風、葛根湯主之。方一。
「太陽病、項・背が几几として強張り、汗が無く、悪風、葛根湯これを主る。」
太陽表邪が經に入れば、經に沿って輸ばれるので、經氣の通りが悪くなり、
筋脉に栄養が届かなくなり、項背部が強張るなどの症候が現われる。これが邪入經輸。
風邪が經に入って輸ばれれば、表が虚して自汗がでる。これが桂枝加葛根湯証である。
寒邪が經に入って輸ばれれば、表が実して無汗となる。これが葛根湯証である。
【参考文献】
『中医病因病機学』東洋医学出版社
『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社
『傷寒雑病論』東洋学術出版社
脾胃湿熱の「湿熱」について
東洋医学概論の教科書にあった脾胃湿熱でしたが、湿熱とは
食べ過ぎ・飲みすぎが原因で体内に入ったままになっている「水」が
熱の影響で湿気?のようになっているものなのか?
ヒントを探して中医弁証学を読んでみましたが、今日はハテナが多いです。
湿は重濁性と粘滞性をもっていて、湿邪による病は長引きやすく、進行が緩慢
粘滞性があるために長引きやすいような感じがしますが、
病の進行が緩慢というのはいいことなんでしょうか?
それともわかりにくい?ということなのでしょうか。。
気機を阻滞させやすく清陽(?)に影響しやすい。
湿気の多い環境や居住地の場合、湿邪は外から皮毛に入る。
また、脾胃虚弱や水分の取りすぎ、過食などは湿の内生をまねく。
湿の病は内外の湿が合わさって発生することが多い。
私自身が雨の多い土地で生まれましたが、どれくらいの期間その環境で過ごすか、というのも関係があるのでしょうか。
(それによって湿邪に対して耐性ができるみたいなことはあるのか?そもそも邪に対して耐性ってなんだろう…)
(大阪は日本の中でも湿度が高い土地柄から、梅雨の時期になると湿邪による症状が起きやすい、と授業の時に聞いたことがあり、根拠を調べてみましたが思うような答えは出てきませんでした…)
臓腑の気
お久しぶりです。高山将一です。
風邪で長患いしまいました。
今日からどしどし疑問や、学び、気づきを述べていこうと思います。
初歩的な疑問が前々からあったのですが、「臓腑の気」とはいったい何を指すのでしょうか?
一つは臓腑の機能、もう一つは、気の一種を意味しているのか?
多くの本には、脾気や、肝気は、その臓腑の機能を指すと書いてあります。
しかし、病機には、たとえば、なんらかの原因で脾気が
化生出来なくなって、運化機能の失調で、食欲不振や、
精神疲労が見られるとあるが、
この場合、「脾気が化生出来なくなって」とあるので、
機能を指しているのではなく、物質としての気を指していると考える。
また、
臓腑の機能は、臓腑本体が機能しているのか?それとも
臓腑の気が臓腑の機能を果たしているのかも疑問です。
例えば、脾の運化、統血は脾本蔵が機能しているのか
それとも、脾気が働いているのか、
それとも、両者共に働いて機能するのか、疑問です。
この捉え方の違いで大きく治療法が変わってくるような気がします。
五月山
久々に自然の中でリフレッシュしてきました。
ちょうどモミジも真っ赤になっていて、晴天とのコントラストが綺麗に映えてました。
それからコロナ禍が始まってから、ずっと会えてなかった友達と久々に会うことができました。
机に向かう時間をキャンセルして、たまにはスローライフもいいですね。
「11/10(土) 漢方薬「桂枝湯」を学ぼう!」の感想
講師は大原先生より学びました。
傷寒論より太陽病~厥陰病を説明され、
実際に桂枝湯を煎じ、飲用を楽しみながら温かい時間を過ごさせて頂きました。
学生の身で、混沌の日々を過ごしておりますが
通行人や電車で同乗する人達を観る際に、仕草や素行を観察してしまいます。
例えば
この人は落ち着きがない、汗が多い、座り方が横柄、疲れてる、顔色が悪い、
歩き方、目の力強さ、物の持ち方、声の大きさ、、、、
その標は?本は?
虚している?、実している?、陽虚?、陰虚?、内熱?、肝気?、腎虚?、、、、と
しかし、本日の漢方講座を経験すると、今までは力の入り過ぎた感覚で見ていた様に思いました。
飲用より身体を整えていく感覚を思うと
力を抜いて観察し、全体像より症状とか異変の把握に努めなくてはならないと感じました。
臓腑を補した影響が、体全体へと達すると思えたからなのでしょうか。
この”『補する』を重点とする”という事を
「10/7(日) 学生向け勉強会」後半戦の院長特別講座で教えて頂きました。
その後半戦のフィーリングは一つの起点となっていますが、共通項を得られたのが本日の収穫の一つです。
大原先生、お疲れ様でした。
いつも配慮頂く院長に感謝いたします。ありがとうございました。
【番外編】
(講座が終了し、方剤の効能についての雑談中)
大原先生
「・・は腎陽と腎陰の両方を補うんですよ。逆じゃなくて両方を補えるんです!」
稲垣
「なるほど、太極を大きくするのですか・・」
と返答した際の大原先生の顔が
『稲垣、易経できやがったな』的な顔は脳裏から離れません( ̄▽ ̄)
できる事だらけ
体の使い方でずっと指導して頂いている事を強く意識する。
方向性。
土台を固めた上で預けて脈をみる。
鍼を行うときにもその感覚が活きる気がする。
押手などでしっかり固定化した上でどこに届けるのか。
人に練習させてもらって、この意識で置いたらいい感覚だった。
この先に微細な調整などもあるんだろうな。
指の使い方なんかも少し馴染んできて良い感じです。
生まれた感覚を大切に、ブラッシュアップしていきます。
寺子屋時に学びの姿勢に関して受けた言葉に対して思うところ。
結局のところ、それを生業とするプロとしての責任感を持った上で、楽しんで学びを進めれるかというところに帰ってくると思う。
伝えて頂いた学び方なら、何事にも答えや正解といった枠を作らないので限界がないし、やれる事は無限に広がっていく。
先に患者さんの治療があるならこれ以上の事はないよなと思う。
実験、公孫など
珈琲
私はコーヒーが合いません。
香りや苦味が好きなんですが、身体に合わない。
自分の感覚として体感しているのは肝の暴走。
散々書籍にあることなので発見でも何でもないのですが、体感としても感じます。
じゃあ、それを思いっきり飲んだらどうなるか。
ボトルコーヒーを一本一気飲みしてみた。
自分の体の反応と術者としての感覚を飲む前、飲んだ後と比較してみました。
術者として
普段から鋭くない感覚が更に鈍くなる。
全く相手を感じる事ができない。
身体を触らせて頂く時に頭に言葉が多くなる。
体感として
自意識が強くなる。
ナポレオンはコーヒーを勇気の出る飲み物として愛用していたらしいのですが、鈍感になっただけじゃないのか。と思った。
また、時間差があるので直後には出ない。
ただ影響がマックスになった時、酒で酔った感覚になる。
調べるとコーヒー酔いというものもあるらしいです。
気逆を起こすと気が大きくなる?
脈の寸には影響があった気がします。
頭には色んな言葉が浮かぶ様に。
エゴが強くなった感覚?
いつも以上に自分の世界だけで全てを完結させている気がしました。
家に帰って自分の肝経の経穴に鍼をしてある程度は和らぎましたが、躁鬱状態ってこんな感じなのかなと思いました。
手に受ける感覚
何か違和感を感じたとして、それぞれ種類が違ってくる。
細分化して言語化できればいいなと思いました。
体感として一つ重い感覚はあったので、まずはそれについて考えていく。
切経
術者と患者が合った時、そこに囚われ過ぎるのは良くないと思いました。
ベタベタ触ると段々反応も薄れ、よく分からなくなってくる。
即時即決、一回でどれだけ情報を頂けるか。
患者とどの様な意識で向き合うか、模索します。
深さも意識したい。
公孫
この穴の認識を深めたい。
奇経八脈考、症例から学ぶ中医婦人科などを中心に調べているのですが、まだイメージが掴めていません。
引き続き調べて行きます。
楽しむこと
表面的なものではなくて、この本質って何なんだろう。
考える事で遠のいていっているかもしれないけど、一旦はこの工程を踏みたいと思います。
血分病機
こんにちは、稲垣です。
血分病機についてまとめます。
【血分病機】
血は営より深層にあり、血分病変は営分病変よりもさらに重くいとされ、
心・肝・腎などに重大な障害の可能性があるとされる。
・熱深動血
熱邪が血分まで深く入りこんで火に変わり、火毒が燃えあがり、血絡を損傷し、血流を混乱させる。
血熱が心を傷れば、主神の蔵ゆえに意識障害・譫語・狂躁が現われる。
・血瘀血畜
血熱が気を損傷し、気滞をつくり血瘀に発展させる。
邪熱が血とぶつかる、陰液を熱邪が損傷させて営血を消耗させた場合、など瘀血となる。
さらに発展し、邪熱と瘀血がぶつかりあえば「血結胸」「下焦畜血」などとなる。
・血熱動風
血熱が盛んになり、厥陰まで入り込み、肝を犯して筋脈を焼く。
陰血を消耗させ、火より風を生じさせる。痙攣などが発生する。
少火は壮火となり、風を起こして、さらに火を煽る。
意識の混迷や厥証を発生させる。
・耗血動血
熱の血分侵入では、耗血・血竭・亡血・動血を起こす。
血の不足により筋を潤すことが出来ず、また陰が陽を抑えられずに
血虚生風、虚風内動を起こす。
【参考文献】
『中医病因病機学』東洋学術出版社