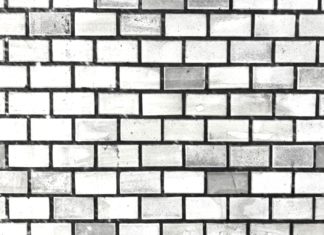舌の経緯
寺子屋である患者さんの舌診をさせていただきました。
西洋医学的に同じ診断をされた別の方の舌を以前写真に撮っていたので比較してみました。
舌型は異なりますが、どちらも舌色や苔の配置などが特徴的でバランスが極端になっている事に気付きました。
今日見させてもらった舌や、以前写真におさめた舌も断片的で、どのような変化が起きるのかまだ想像ができません。
そこで、症状が悪化した時、快癒に向かった時、舌がどうなるか、患者さんの生活環境や職業、発症しやすい時期など、症状が悪化するまでの経緯も先生に聞いてみました。
「またこの症状が出たらどうしよう…」と不安に思う気持ちが更にプレッシャーを与え症状を悪化させる要因になるという先生の言葉が印象的でした。
歯痛
学校の東洋医学の授業で歯痛(歯に関係のない歯周辺の痛み)についてを習う。
私も歯痛になったことがある。痛みの性質としては、
痛みの場所は上の時もあれば下の時もある動く→気滞?
キリで突かれるような刺痛→瘀血?
灼熱感を伴う痛み→熱証
下顎から歯根にかけて走る痛み→?
触ると鈍痛、歯肉腫脹
いろんな痛みが混在していたので、教科書の病症のように1種類の痛みでは例えられないし、病因も単純そうではない。教科書や病症分類は極端な例しか載っていないのではないか。
教科書では病症の一例として、肝火上炎で歯痛が起こると書かれている。
現在もストレスを感じた時は当時の1/10ぐらいの痛みが稀に再現される。
当時の歯痛は随伴症状と照らし合わせると、肝鬱気滞もしくは、肝火上炎への移行期だったのではないかと考察する。
今なら脈や舌も見て他の視点からも考察できるのに…と思うが、やっぱり歯痛は嫌だ。
経穴(01)
【地機】
学生時代に使用した経穴の教科書を新・旧で比較してみる。
旧教科書の”地機”は”陰陵泉”より5寸下、
新教科書は”地機”は”陰陵泉”より3寸下、とされている。
考えらる可能性は「2つとも違う」「片方が正解」「2つとも正解」。
重要なのは点でなく、線をとらえる事にあるのかな?と思う。
今後の切経の参考にして行きたいと思います。
旧
『経絡経穴概論』(株)医道の日本社
初版:1992年3月20日
●地機(郄穴)
取穴部位:内果の上8寸、脛骨内側縁の骨際に取る。
(注)脛骨内側顆の下際から下5寸に当たる。
筋肉:ヒラメ筋
運動神経:脛骨神経
知覚神経:伏在神経
血管:後脛骨動脈
新
『新版 経絡経穴概論』(株)医道の日本社
初版:2009年3月30日
●地機 SP8(脾經の郄穴)
部位:下腿内側(脛側)、脛骨内縁の後際、陰陵泉の下方3寸
取り方:脛骨内縁の後際、内果尖と膝蓋骨尖とを結ぶ線を3等分し、
膝蓋骨尖から3分の1の高さに取る。
解剖:ヒラメ筋・長母指屈筋〈筋枝〉脛骨神経,
《皮枝》伏在神経,後脛骨動脈
【参考文献】
『経絡経穴概論』(株)医道の日本社
『新版 経絡経穴概論』(株)医道の日本社
服薬
自分の体で薬を色々試している。
この前、ある薬を服用してすぐに先週刺した箇所周辺に反応があった。
しかし長続きせず。
瀉法の薬だから当然か。
一過性の反応もあるものだと感じた。
動き方として面白いものがあるので、この薬の反応はまた追っていきたい。
しかし一般的に漢方薬はゆっくり効くというけど、実際はそんなにゆっくりでもないよなと感じます。
山楂子など
山楂子
実験として無理して食事を大量に摂取。
やはり次の日は大ダメージ。
症状として気になったところは鼻詰まり・咳・軽い腰痛・股関節痛
舌下静脈が浮き出て、脈は沈気味になった。
行った実験は山楂子を大分多めに摂取。
気になる原穴付近にも体感として反応あり。
勿誤薬室方函口決には浄府湯という処方がありますが、ここで大切なのは山楂子だと思いました。
ネットでは処方構成、文章を確認しましたが今手元に本がないので、また原文を確認したいと思います。
とにかく身体への現れ方がとても勉強になりました。
命
生命の危機に瀕したとき、人間は一番能力を発揮する。
最近そう思う事が増えました。
事象
東洋医学を考えるとき、文字面になってはいけない。
一定の揺らがない法則があり、それは日常の現象でも当たり前に観測される。
人間も自然の中の一部なのだからそれは当てはまる。
そのイメージを持ってくると見えてくるものもあるのではないか。
そう考えてみています。
環境
沢山の勉強をさせて頂いている本当にありがたい環境にいるなと思います。
発見があるとやはり嬉しいし、拡がってくる。
しかしそうなった時に怖いのが自分。
それが日常になっては絶対にいけない。
自分自身で非日常にする努力を行うべきで、そこに甘えてしまう事は本当に恥ずかしい事だと思います。
自分なんて碌でなしを肯定するわけにはいかない。
せっかくなんで
最近、漢方薬を自分でアレンジして飲んでいます。
先月の強い寒波がやってきたくらいの時に、時々寒気に襲われていておかしいなと思っていた時期がありました。とりあえず桂枝湯も入ってるからと思い、以前にもらって余っていた柴胡桂枝湯を飲み始めたら、横隔膜下の引きつりが和らいでいるのに気がつきました。
改めて自分は胸脇苦満状態だったんだと思いました。
上半身を左右に伸展すると左側の方が硬く、左腸骨稜に付着している筋肉が引っ張られて痛みがあります。夢分流腹診でいう、左の肝相火が実しているということでしょうか。
とりあえず疏肝理気をしてあげたいです。
勤めている薬局に生薬があるので、今飲んでいる柴胡桂枝湯に生薬をプラスして、自分の身体を使って実験してみたいと思います。
鍼治療を受けて
先日鍼治療を受けて感じたこと
鍼を置かれた後、
即座に足底の方に向けて動き出す
勢いがあってまるで足から抜けていくような動き
同時に大きな呼気が生じる、
呼吸が何度か続けて起こる。
ふと治療に入る前に心に抱えていた、感情的なこだわり
(直近で起こった事について「解せない」と思う、苛立ち、怒りに似た感情)
が手放せて軽くなったことに気づく
(これは気滞に当てはまるのか?)
この直後に体の別の部位、
肩の力みについて意識が入り、肩の緊張が緩む。
この肩の力みは腰の弱さ(慢性腰痛あり)と関連していると自覚する
____________________________
ある部分の滞りが他の部位にも波及していくように
ほどける時にも推進力のようなものが働くのだろうか
普段はおとなしい腰痛が悪化する時には、
体が疲労倦怠の状態にあることが多い。
腰に違和感を感じ始めた後に続くのが、
上半身と下半身の疎通不良、からだ全体の動きの硬さや気鬱の症状
(気虚が先で、気滞が後か?)
記事を書きながら、考えていたが
「どちらが」という検討に意味がないと思えてきた
ただ、はっきりとしたこと
これまでは気病が4種に分類されていること、
この4つをこれまで概念的にしか見てこなかった。
表れる症状を単語と結んで並べていただけだった。
鍼治療を受けて③
この1〜2週間、鍼治療で置鍼中に覚えるからだの感覚と似たものが、
通勤の車内や食後に体を休めているとき、朝方 起き抜けの時間帯に、度々現れる。
これもまた変わっていき、鈍化するかもしれないし、もっと別なものに変わるかもしれない。
感受性が高まる背後にあるものは一体何か。
ひとまずいま感じていることを記録したい。
からだの調子は良い、かといってからだに不調がなくなったわけではなく、
不調の波がくれば強い首コリや腰の弱さなどがしんどくて違和感を覚える。
それでも感じ方の種類が違うというか、
痛みや違和感に対して以前の様に嫌わなくなったというか、
身体のうえに生じる感覚を受け取るのに抵抗、邪魔していたものがひとつ落ちたのか、
その分 中が静かになったように感じる。言葉で捕まえるのが難しい
患者、食べ飲み など
患者
今週寺子屋で見せて頂いた患者さん、もし自分があの人ならどういう気持ち、体になるか。
声や様子から色々気にされそう。
治療してなかったら心臓が心配だな。
生殖器関係に問題はないかな。
気逆を起こして気にされやすいだろうから、言葉遣いはどうした方がいいかな。
敏感そうだから特に時間をかけたらいけないな。
拾えなかったけど本当に心経の辺りに反応がなかったんだろうか。
あの状態なら出やすいと思うんだけれども…
食べ飲み
先日友人の結婚式があった。
そこでのスケジュールが11時〜披露宴 15時〜二次会 と言った胃腸にとってのハードスケジュールだった。
家に帰ってお腹を触ると胃がパンパン。
足では地機が硬くなっていた。
浅めに刺しても痛かったのですが、腹満は楽になりました。
舌の変化も見ていたのですが、翌日の変化など特に勉強になりました。
また、大人数は大変だなと改めて実感。
自分の課題です。
感覚
本を読みながら何かを触る。
何も見ずに何かを触る。
感覚が全然違う。
触覚だけでなく、全ての感覚がそうだと感じる。
今、きちんと周りの音を拾えているか?
それがノイズの様に聞こえるか、キチンと聞こえるかは自分の状態によって違う。
そこを聞こうとすれば別のものを拾い溢す。
こちらから行くべきじゃないんだろうな。
結局それが何なのか?とその場で気にしてる時点でダメなんだと思います。
実験
↑の事を考えていて、先週の寺子屋ではできる限り周りの状況観察に努めてみた。
やり始めの少しの間はいい感じだったのですが、ずっとやっているとしっくりとこなくなりました。
停滞するといい感じじゃなくなる。
一気にその場の空気とのギャップが出てくる感じがしました。
理論から実践しようとしましたが、これは無理だなと痛感。
実践から理論なら可能なんだと思います。
経穴
勘違いかもしれませんが、その穴に対してどういう認識を持つかで効果が変わってくると、何となく感じた出来事がありました。
補寫といった話ではなく、刺し方でも全く違う目的になるのではないのかなと感じています。
背中
知り合いの身体を借りれたので刺させて頂いた。
普段は腹などでみますが、その時は背中で変化を追ってみた。
脾募と脊柱など一致する部分が見られて勉強になりました。
梅核気
肝気鬱結を勉強している際に気になる言葉が出てきたので調べてみました。
肝気鬱結の症状には、イライラする、憂鬱、有声のため息がよく出る、
胸腹部の脹痛、月経不順などがあるが、その中に「梅核気」というものがありました。
「梅核気」は現代病名だと神経性咽喉部狭窄症(ヒステリー球)というそうです。
のどに梅干しの種があるような違和感があり、飲み込もうとしても
吐き出そうとしてもなくならないが、飲食は普通にとれる。
気の滞りによって咽喉部に痰が生じていることによって異物感があるようです。
ストレスが原因の病は現代に多いような感じがしますが、金匱要略にも
「婦人、咽中に炙臠(あぶった肉の切り身)有るが如きは、半夏厚朴湯之を主る」
とあり、婦人・・・と書かれているが、男性にも起こる。
他の臓器の影響(脾胃が多い?)、過度の情志、情志の抑制などによって肝の
疏泄作用が失調することによって発生した気滞が肺に昇って起こる。
理気去痰解うつ作用のある半夏厚朴湯を用いて治療するとあるように、薬物による治療が行われることが多い。
梅の種は肉のかたまり、というより大きいしもっと固いように思いますが
実際に梅核気があるような方に尋ねると名前の由来となっている梅の種が
つまっているような、ということはわからないけど息苦しい感じがあり、不快であるとのこと。
臨床医学総論でもヒステリー症を勉強した際に、ヒステリーはギリシャ語で「子宮」を
意味することから昔は子宮が原因で引き起こされる女性の病気とされていた、と習いました。
西洋でも東洋でも同じように病を分類していることもあるのかと思うと興味深く感じました。