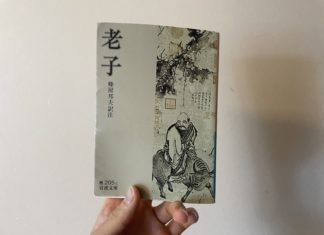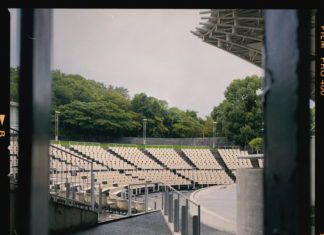上ル・下ル(02)
介護施設などで、少しでも通常と違う事があると連絡をするシステムがあります。
連絡ノートであったり、端末機器への入力であったり。
中枢性の疾患のある利用者も多く居られ、時として介護士を悩ませたりします。
機嫌が悪かったり、意味不明な事を発したりと。
記録には『〇〇様、不穏。△△など、される。』などと記されたりします。
そんな”不穏”な状態の方で多くみられるのが便通が滞っているケース。
大便秘訣について再確認する。
病因病機により四つに分けるとすると、
①熱秘:実熱による。顔面紅潮や口渇、口臭の可能性あり。
②氣秘:気滞による。曖気が多く、腹部や胸肋部の張満感の可能性あり。
③虚秘:気虚(息切れ、疲労感など)あるいは血虚・陰虚(顔色が悪い、疲労感など)による。
④冷秘:陽虚による。大便がゆるく、腹部や四肢の冷えなどの可能性あり。
上がるものが上がり、下がるもの下がらないと
様々なところで問題が出てくるのかと思う。
備忘録として記す。
【参考文献】
『新版 東洋医学概論』医道の日本社
老子の第一章から想像
先日老子を読み終えました。
速読を意識したので二周目はじっくり読んでいきたいと思います。
第一章
道可道、非常道。名可名、非常名。
無名、天地之始。有名、萬物之母。
故常無欲以觀其妙、常有欲以觀其徼。
此兩者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄、衆妙之門。
訓読文
道の道とす可きは、常の道に非ず。名の名とす可きは、常の名に非ず。
名無きは天地の始め、名有るは万物の母。
故に、常に欲無くして以て其の妙を観、常に欲有りて以て其の徼を観る。
此の両者は同じきより出でて而も名を異にす。
同じきを之を玄と謂う。玄の又た玄、衆妙の門。
・この文章から今の時点で感じている事
これが道だというものは常の道ではない。
道は万物の根元ではあるが、それを言葉で説明することは出来ないし、ましてや名付けることなど出来ない。
全ての事象は道から為るが、道を観ようとすれば無欲でなければいけない。
無欲のため観えるものは妙であり、奥深い。
有欲であれば徼しか観ることが出来ない。
妙とは「あまりにも奥深くて見ようとしても見えないこと」で、
徼とは「帰結や端」という意味とされます。
妙も徼も同じ玄から生まれるものではあるけれども観ているものが違う。
王弼は
「両者は始と母である。同出とは同じく玄から出ること。異名とは名付けられる場面が同じでないこと。首(はじめ)に在れば始といい、終にあれば母という」と注釈されています。
図解雑学 老子では
「「名有る」状態が「万物の母」だというのは、万物は名が与えられてはじめて万物と認識されるからで有る」
としました。
第四十二章では
「三生万物」という言葉がありますが、これは「天地間の陰陽の気が混ざり合って万物を生むということ」とされます。
つまり欲がある立場に立てば
徼という「天地間の陰陽の気が混ざり合って生まれた万物に名前がつけられた状態」しか観えないのではないでしょうか。
確かにそれは玄から生まれたものの一つではあるけども、端であって全てではないのかなと思います。
何事も無欲の立場で妙を観なければいけないのではないかと思いました。
道は奥深くて決してこれ!と捉えられる存在ではけれども、老子の様に無欲の立場に立てば感じることが出来るものなのではないのでしょうか。
道理という言葉は広辞苑では「物事のそうあるべきすじみち」とされますが、
道の理はどこまでも奥深いので、妙であり「玄の又た玄、衆妙の門」とされたのではないのかと思います。
臨床現場にまだ立っていませんが、きっとそういったことも必要なのではないか。と感じています。
参考資料
老子 岩波文庫 蜂屋邦夫著
図解雑学 老子 ナツメ社 蜂屋邦夫著
広辞苑 第七版 岩波書店
膩苔が強い舌を観察します。
こんにちは稲垣です。
舌診について研究を重ねてまいります。
【前】
舌体は紫舌で、
舌尖から舌辺にかけての歯痕の部分に
赤みが強く感じらます。
舌尖に点刺が多く、舌尖より舌根にかけての
中央部分に黄膩苔が強い。
潤いが少ないように思います。
舌裏に関しては舌下静脈がハッキリと見え、
両側が暗く血の滞りを感じます。
【後】
今回は、刺鍼中もコミュニケーションをとりながらでしたので、
ゆっくりと休んで頂く形ではありませんでした。
舌面に関しては、変化は少ないですが
舌尖あたりの苔が少し引いて
舌体の色が見やすくなったように感じます。
舌裏の色調が明るくなったように感じるのと
両側の暗さが少し明るくなっていうように思います。
舌面の黄苔や潤いの少なさより
熱が強く津が焼かれているように感じます。
その熱の所在が重要に思いますが、
舌尖の点刺との共通点が気になります。
以前より練習として診させて頂いており
ひどい時は紫舌と膩苔が極めて強くなります。
化火をどのように抑えるのかが課題と思いますが、
舌裏からみえる瘀血が下焦を滞らせ、
気機を上昇させてる要因と考えております。
熱化させずに自身でセーブできる力を持つ事
を長期的に考えて施療を行っております。
経過を観察していきます。
同情
数週間ぶりに診せてもらって
復調した患者さんの姿に、
前回は浮き沈みする揺れる姿に
一喜一憂していたことに
はっきりと気付かされる。
同情はしないー
以前教わっていたことが指していることが
少し分かった気がした。
食べることについて①
皆さま、初めまして。
受付をしております、鍼灸学生のイワイです。
ここでは、日々の学習のことやそこで生じた疑問など様々なことについて、学生なりに書いていきます。
どうぞよろしくお願いします。
早速ですが、新年度になりました。
桜が満開で見頃を迎えてますね!
春といえば、「新しいこと」を始めるのに適した季節だというわれています。新しいチャレンジや生活など、楽しみな気持ちと新しいことに取り組む不安もあると思います。
私達の身体は何か取り組むとき必ずエネルギー、気力、体力が必要になります。
そこで、新しいことに向き合うために、日々の生活の中で欠かすことのできない〝食事〟について勉強し、食べることで身体へどういう影響がでるのか、西洋医学と東洋医学での、それぞれの概念について勉強しました。
西洋医学的には、私達が食事した際、口から入った食べ物は 口→食道→胃→小腸→大腸→肛門 という順ではいって、外で便として出て行きます。この過程の中で、体内に栄養素を取り込み、身体に必要な物資に再合成し、吸収されています。
では、東洋医学的にはどういう概念でしょうか?
東洋医学的に考えると、まず人体の構成や生命活動を維持するのに最も基本的な物資のことを〝精〟といいます。
この〝精〟には、父母から受け継いだ〝先天の精〟と飲食物を摂取することにより得られる〝後天の精〟の2つから成り立ちます。先天の精の量は生まれたときから決まっていますが、後天の精は飲食物を摂取することで絶えず補充されています。
次回は、後天の精について勉強したことを書いていきたいと思います。
—————————————————————
【参考文献】
「生理学 第3版 」東洋療法学校協会 編
「新版 東洋医学概論」東洋療法学校協会 編
東洋医学探訪(01)
もう夏の終わりですが、私の日焼けは遊びではありません。
修行の結果です。
京都を散策してまいりました。
『延命院』とは『医療施設』
御由緒
(引用:武信稲荷神社の”案内”より)
平安時代初期、清和天皇貞観元年(859年)
西三条大臣といわれた 右大臣左近衛大将 藤原良相(よしすけ)公によって創祀。
平安時代の古図には三条から南の神社附近一帯は
「此の地、藤原氏延命院の地なり」と記されている。
延命院とは藤原右大臣によって建てられた医療施設であり、
当社は延命院と勧学院(学問所)の守護社として創祀された。
後世、藤原武信(たけのぶ)公がこの社を厚く信仰し、
御神威の発揚につとめたので、武神神社と称されるようになる。
その後延命院・勧学院は失われるが神社だけが残り、
創祀以来一千余年にわたり広く人々に信仰されて今日に及んでいる。
撮影をけっこうしましたが、蚊にはご注意ください。(経験談!)
親友と
友人に体を診せて貰った。
ベロ見せてといってベロは出せるけど
裏見せてと言って裏返せない。
こうできる?とやって見せて、
それでもできないみたい。
無意識にか指をベロの下に入れて裏を見せてくれようとしている。
モゾモゾと動くだけで、やはりできない。
人のそんな様子を目の当たりにした。
激しく上気していて、喋り始めるともうとまらない彼に
少しでも落ち着いてもらえるように鍼をさせてもらった。
先々週の施術で
水分穴の少し右だったように思う。(今も反応あり)
刺入深度は1ミリか2ミリか。
置鍼開始して少しして、
息がうまく吸えていないことに気づく。
吐くことはできている。
入ってこない、がそのことに特に不安はない。
数分して抜鍼の後、それまでの状態をはずみに
誘いこまれるようにからだにもたらされた深い呼吸と何か。
横隔膜の動きが抑制されていたのか。
これも穴性のひとつにあたるのか。
他の方においても似た作用をもたらすのか。
合谷の穴性「生血」を考える
合谷の穴性について調べてみます。
穴性学ハンドブックでは補で生血の効果があるとの事です。
しかし「補血」ではなく「生血」である事に違和感を覚えます。
血を生み出す効果がある様なので、中医鍼灸臨床経穴学を中心に調べていきます。
P 65
<効能>
③補法:補気固表・益気固脱・益気摂血・行血・生血
湯液における黄耆、人参、党参、白朮、炙甘草、百合、黄精などの効に類似
P 79
「合谷を補すと補気の作用があり、瀉すと行気散滞の作用がある。したがって、気虚のために統血が悪くなっておこる失血証、「有形の血は自ずとは生じず、無形の気により生じる」という道理によって起こる血虚証、気虚による血行障害の病証に対しては、本穴を補して補気をはかると、摂血、生血、行血の作用をもたらすことができる。」
→つまり
「気血両虚の状態で補血だけ行っても自身の血を作る力は回復しない。
合谷による補気を行う事で血を生じさせる力を付けましょう。」
これが合谷の生血なのだと思いました。
実際どの様な使われ方をしているか見てみます。
P 69
「膿は気血が変化して生じる。久瘡には、膿が外溢して気血両傷となるものが多い。または瘡が長期にわたって治癒せず食欲も低下し、さらに膿が外溢することにより気血大傷、正気虚衰となり久瘡がおこる場合もある。
1.瘡面の肉芽の生成が遅い場合
合谷、三陰交(補)…気血の補益」
P229
三陰交
「本穴には、統血、凉血、全身の血分の虚損を補益する、全身の血液の運行をよくするなどの作用がある。」
中医臨床のための方剤学 P260
当帰補血湯
「皮膚化膿証が潰破したのち瘡口が癒合しにくいのは、気血が不足して肌肉の産生が悪いためである。」
医学三蔵弁解 P133
「気血は互いに根ざしていますので、これを気虚とするときにはすなわち血虚しているものであり、血虚するときには気もまた虚しているものです。
治法には標本の区別があります。
気虚によって血虚となっているものは、気虚を本として血虚を標とします。
血虚によって気虚となっているものは、血虚を本として気虚を標とします。」
→生血で血を生むと言っても血虚していれば、三陰交の様な補血の効果を持つ経穴との配穴が必要なのだと分かりました。
他に合谷・血海(補)などの配穴も見られたので、状況に応じた「補血」の効果を持つ配穴を行う必要があるのだと思います。
今のところは
生血=気の血を作る力をつける事で血を補う
補血=血を直接的に増やす事で補う
との認識になったのですが、間違っている可能性もあるので一穴一穴を確認しながら調べていきたいと思います。
参考資料
中医鍼灸臨床経穴学 東洋学術出版社
穴性学ハンドブック たにぐち書店
中医臨床のための方剤学 東洋学術出版社
医学三蔵弁解 たにぐち書店
臓腑と感情
=================================================
2021/09/14 『臓腑と感情』
“『素問・陰陽応象大論』には
「怒傷肝」,「喜傷心」,「思傷脾」,「憂傷肺」,「恐傷腎」
とある。異なった感情刺激は、それぞれの臓腑に影響を与える。”
(中医基礎理論 P244)
この部分について、学生の時に授業で
(過度の)感情が臓腑を損傷する、という構図で説明
されて違和感を覚えたが、その理由が少し分かった。
強い感情が
もたらす気の作用が臓腑の「気」を乱す=狂わせる。
そして、それがパターンの様にになることもある。
ーたぶん、捉え方は変わっていく。現在の記録として
*【引用】全訳 中医基礎理論/たにぐち書店
=================================================
2021/09/15 『背部兪穴の取穴』
切経で触れるときに背部では
受け取る感覚が手足で取穴するときと
かなり違って感じられる。
手足部と同じように取れるはず、と
考えアプローチするからその違いを前に、
立ち止まることになる。
少なからずそういう面もありそうだと考えた。
体幹は経絡の走行ももっと入り乱れているだろうし、
何より内臓のすぐ裏にあたる部分でもある。
背部兪穴の考え方もある。
次回の機会には思い込みを少しでも横に置いて、
ツボの状態を観察したい。
=================================================
2021/09/16 『舌診×写真』
ある方の舌を観察してー
色は淡紅、だが舌全体に青い色調が加わり色味として重たい印象。
薄膩苔、少し白沫も見られた。
舌裏は淡紅、色に褪せた感じが見受けられた。
治療の前後の状態を観察。
治療後には、
おさまりがいい、落ち着いた雰囲気に、そして潤いが増していた。
(観察する少し前に水分を摂った、関連性としてどの程度考慮すべきか?)
今回は、写真におさめた。
治療前後で、並べて拡大して見比べてみた。
処置前は、舌の輪郭があきらかに凸凹だったことが見てとれた。
それが治療後、およそ滑らかな曲線を描く輪郭に変化していた。
印象の違い、その理由のひとつだと考える。
写真の撮影の仕方だけでなく、確認の仕方にも色々と工夫ができそうだ。
(認められた所見に関する考察はまた別の機会に記したいと思います)
=================================================
2021/09/17 『苔』
6月から
継続して定期的に舌の状態を見せてもらっている方の舌の所見
として、薄苔か無苔に近い状態をずっと見てきた。
この方の素質として捉えた方が良いのかと考えていた。
それが10日前くらいにはじめて薄苔が舌根部に見られ、
つい先日、それが以前よりも定着している様を見た。
先立って他の所見や症状が変化している状況の中で、
この段階でようやく、という感想を抱いた。
これが逆だったら、どのように受け止め考えることになるのか..