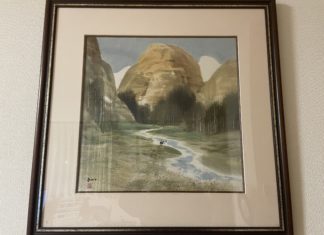舌診(06)
舌形について整理する
【舌形】
老
粗糙(そそう) :舌面の紋理のきめが粗い。
堅斂(けんれん):舌体が堅くしまった感じ。
蒼老(そうろう):色が濃い。
嫰
細膩(さいじ):舌面の紋理がきめ細やかで潤いがある。
浮胖嬌嫰(ふはんきょうどん):舌体がはれぼったくて柔らかい感じ。
胖大
舌体が正常よりはれぼったくて大きく、舌を伸出した時に口の幅いっぱいになる。
腫脹
舌体が堅く腫脹し、甚しければ口腔内を満たしたり、
口外に出たままで回縮・閉口ができない。
歯痕
舌体の辺縁に見られる歯による圧迫痕。
痩薄
舌体がやせて小さくなったり薄くなったもの。
裂紋
陰血が不足して舌面を栄潤できなかったり、陰津の散布を阻滞したりして発生する。
苔のみの裂紋と混同に注意が必要。
光滑
舌面に苔が無く乳頭が消失し、光ったように見える。
点刺
点は紅・白・黒色を呈し舌面の点状隆起であり、熱入営血や心肝火旺などを示す。
刺は舌面に立ち上がった軟刺や顆粒のことで、気分熱盛や胃腸熱盛などを示す。
瘀点、瘀斑
舌面より隆起しない斑点で、点状のものを「瘀点」、斑状のものを「瘀斑」という。
紫舌と同意であったり、熱入営血での斑疹出現の前兆であったり、血瘀であったりする。
舌下脈絡
舌下静脈の怒張・蛇行があれば気滞血瘀の可能性。
重舌、舌衄、舌癰、舌疔、舌瘡、舌菌
・重舌
腫脹などにより小舌が生じたように見えるもの。
小児などにみられ、心経化熱の上衝によったりする。
・舌衄
舌面からの出血で、血熱妄行や脾の不統血。
・舌癰
舌面の化膿症で大きく腫脹するのが”癰”
・舌疔
舌面の化膿症で紫色であったり小豆大であったりするのが”疔”
・舌瘡
舌面に生じるアフタ。
・舌菌
舌面から隆起する新生物。
【参考文献】
『中医臨床のための 舌診と脈診』医歯薬出版社
『新版 東洋医学概論』医道の日本社
夙川にて
図書館、公民館など、外で勉強する事が殆どです。
好きな場所で、夙川沿いの静かなところに”西宮市立中央図書館”があります。
休憩に川沿いで新鮮な空気を吸うのですが、ふと思い出した事がありましたので。
以前に、六甲山からの鉄砲水で犠牲者が出たことがありました。
その時に『山上が曇れば大蛇が通る』という伝承を知ります。
古人が鉄砲水を大蛇に例えて後世に伝えやすくしたのだと思います。
それをきっかけとして、スサノオノミコトがヤマタノオロチ退治を
”治水対策の比喩”であるとの仮説にも出会う事になりました。
クラスメイトが話の中で「東洋医学=スピリチュアル」との認識に違和感を覚えたのを覚えています。
東洋医学を学ぶという事は災害の地に建つ石碑のように、
古人が未来へ向けた思いに耳を傾ける事のように思います。
とか、思い出しながら国家試験に向けての勉強の年末です。
問診
問診情報こそ重要ー 自分でそうインプットした
のは何がきっかけになったか、思い返してみて
理由のひとつが案外浅いところに見つかる。
3年次に学校のある授業で、
はじめの問診でできるだけ疾患の特定までなされるべきと教えられた。
授業中は、その為の説明が訝しい内容に聞こえ、
かといって先生に何か質問をぶつけるとこもできず、
後味の悪い思いも残った。
なのに(だから?)拘っている。(おかしな話です)
でも1番は、他の診察で得る情報を整理できないからに他ならない。
それらをつなげていけるように。
溝か裂か
「舌正中溝のみに溝があるものは正常、舌正中溝以外の部位に溝や裂け目が見られる際に裂紋舌とする。」
と教科書にある。
では、正中上に一部分、ビリっと破けたような、正中溝より横幅が大きいものはどう見立てたらよいのだろうか。
教科書的には裂紋舌と呼ばないが、「溝」より「裂」の表現に近いと思う。
舌診の本では、裂紋舌の写真は、亀裂が無数に走る物が掲載されていることが多いが、そればかりではないのかもしれない。
■ 文献引用『新版 東洋医学概論』第6版 p.208,公益社団法人 東洋療法学校協会 編,教科書検討小委員会 著
備忘録(1)
アルバイトとして障害者の介助や老人の介護をおこなっておりますが、
今回は、とある方の入浴を介助いたします。
洗髪の際、
ゴシゴシ、ゴシゴシ、、
Aさん「もっと強くして下さい。」
稲垣 「大丈夫ですか?それでは。」
ゴシゴシ、ゴシゴシ、、(結構強くしてるけど大丈夫かな?)
Aさん「もっと強くして下さい。」
稲垣 「(゚д゚)!えっ(マジで!)。わかりました。」
ゴシゴシ、ゴシゴシ、、
Aさん「強くやり過ぎて、昔は血が出たことがあるんですが、それが良いんです。
HAHAHAHAHAHA。」
稲垣 「・・・。」
Aさん「でも、寝不足の時は強さに耐えれない時があるんです。」
★ ”養蔵”できない事での、”皮毛”への影響を思う。
腹をうかがうにあたって
腹診を学ぶにあたって理解があやふやな用語をまとめてみました。
心下痞(しんかひ)=心下痞満(しんかひまん)
心下とは胃脘部を指す。胃脘部に気機の阻滞によって痞えたような不快がある。患部に疼痛はなく押さえると軟らかい。
心下痞硬(しんかひこう)=心下痞鞭(しんかひこう)
硬と鞭は同意語。気機の阻滞により胃脘部に痞えたような不快感があり、患部を押さえると硬く抵抗感がある。また心下痞硬の一種として心下部が菱形状に抵抗が強い心下痞堅がある。
どうやら心下痞は自覚症状のみですが、痞硬の方は他覚的に抵抗があって場合によっては疼痛もある感じです。
心下支結(しんかしけつ)
胃脘部が詰まったような不快な煩悶感がある。
少腹急結(しょうふくきゅうけつ)
左の前上骨棘と臍を結んだちょうど真ん中あたりに索状物を触れ、押したり按じると響くように痛むもの。瘀血の症の一つ。
小腹腫痞(しょうふくしゅひ)
右の腰骨と臍を結んだ線の上から3分の1あたり、回腸部付近にしこりや圧痛があるもの。瘀血の症の一つ。
一語でわかる中医用語辞典(源草社)
はじめての漢方診療十五話(医学書院)
風寒邪の咳嗽から穴性を学ぶ③
前回の続きです。
中医鍼灸 臨床経穴学 P25
「風寒外束、肺失宣降(風寒の邪による宣降失調)
症状:喉が痒い、咳嗽、痰は稀薄である。鼻閉、鼻水。声が重い。または発熱、悪寒、頭痛。無汗。舌苔薄白、脈浮など。
処方:中府、風門、大椎(瀉)…疏風散寒、宣肺止咳。」
まずは中府について考えてみます。
中医鍼灸 臨床経穴学 P 24
「肺臓の病証では多くの場合、この募穴に圧痛または異常な反応が現れる。本穴は胸部、とりわけ肺部疾患を治療する常用穴とされている」
同書籍 P 25
「本穴には、清肺宣肺、肺気を調節する作用がある。また咳による胸痛があるもの、本穴の所属部位に圧痛のあるものなどを治療することができる」
穴性学ハンドブックp 31・152
中府(瀉)…宣肺理気
「肺は全身の気を主る。もし寒邪が外束したり 内熱が上を侵すと肺気は その宣降作用を失い 咳嗽し 喘息し 胸満して 脹痛する。
中府は 肺の募穴であり 手足の太陰の会で 穴は胸膺にあり よく上焦を宣発し 肺気を疏調する。 肺気が郁遏される毎に これを鍼し 気を行らし 血調えれば 痛み止まり 胸満感を消すことができる」
つまり、
中府が治すものは「肺が宣降失調を起こして起こす咳嗽」であり、
中府単独で用いても一時的に咳は楽になるかもしれませんが、風寒邪を取り払う事はできないと思いました。
中医鍼灸学の治法と処方 P132 を見ても
発表散寒法
「配穴処方:大椎・風門・風池・合谷・復溜
随症加減:咳嗽ー肺兪・膻中を追加。」
とありました。
肺兪と中府は腧穴・募穴の関係にあり、共通点も非常に多い経穴で、共に肺失宣降に用いられる様です。
この随症加減と同じで、風寒外束の表寒証であっても、肺失宣降が起きていなければ決して使う必要がないのではないかとも思いました。
また、風寒外束で肺失宣降が起きていれば
「中府を触ると痛い、もしくは異常な反応」
が起こりやすい事も分かりました。
鍼灸学 P230では
陽性反応穴「陽性穴は兪募原穴の部位に現れることが多い…陽性反応穴は、臓腑の経絡体表における反応である。この陽性の経穴を刺激すると、臓腑の機能を調整することができる」
との事なので同じ意味かなと感じました。
参考文献:
中医鍼灸臨床経穴学 東洋学術出版社 李世珍著
穴性学ハンドブック たにぐち書店 佐藤弘監修 伴尚志編著
中医鍼灸学の治法と処方 東洋学術出版社
鍼灸学 東洋学術出版社
六經病機(03)
太陽病病機
【03】邪入經輸
傷寒論
辯太陽病脉證并治上 第五
第十四条
太陽病、項背强几几、反汗出惡風者、桂枝加葛根湯主之。方三。
「太陽病、項・背が几几として強張り、反して汗が出 悪風なるもの、桂枝加葛根湯これを主る。」
辯太陽病脉證并治上 第六
第三十一条
太陽病、項背强几几、無汗、惡風、葛根湯主之。方一。
「太陽病、項・背が几几として強張り、汗が無く、悪風、葛根湯これを主る。」
太陽表邪が經に入れば、經に沿って輸ばれるので、經氣の通りが悪くなり、
筋脉に栄養が届かなくなり、項背部が強張るなどの症候が現われる。これが邪入經輸。
風邪が經に入って輸ばれれば、表が虚して自汗がでる。これが桂枝加葛根湯証である。
寒邪が經に入って輸ばれれば、表が実して無汗となる。これが葛根湯証である。
【参考文献】
『中医病因病機学』東洋医学出版社
『中医臨床のための方剤学』医歯薬出版株式会社
『傷寒雑病論』東洋学術出版社
シズル感
レストランのメニューなどで見かける美味しそうな写真、新鮮な肉や野菜の色をした写真を「シズル感」といいます。
以前の仕事では、「本物を観て美味しそうな色は記憶しておきなさい!」と教わり、何百枚もの写真を「シズル感」のある写真に仕上げてきました。
鍼灸学校に入ってしまってからそんなことすっかり忘れていました…
健全な舌は「淡紅色」という教科書的な表現も、共通言語的なものかもしれませんが、色名というのは国や人によって曖昧なものです。
以前、寺子屋メンバーで舌の色を話していた時に「好感度のある色」「好感度がない色」と表現していましたが、とても感覚的なものでした。
それって、「美味しそう」と「不味そう」に当てはまらないかなと思いました。
スーパーの生鮮コーナーでも「あ、これ買わんとこう…」って思う物って、青みがかっていたり、褪せていたり、黒ずんでいたり、くすんでいたり。
文字を追ってばかりだと忘れてしまいます。
澤田健先生も仰っておられました。
「書物は死物なり. 死物の古典を以て生ける人体を読むべし.」
日々の生活にヒントは沢山あるので、もう少しシンプルに、素直に物を捉えていかないとなぁ、といつも気付かされます。
引用 「鍼灸真髄」代田文誌 著
『舌鑑弁正 訳釈』より紅舌を学ぶ。
こんにちは稲垣です。
『舌鑑弁正 訳釈』の”紅舌総論”より学びます。
・・痩人多火、偏於実熱、医者拘於外貌、輒指為虛、
誤服温補、灼傷真陰、域誤服滋補
(名為滋陰降火、実則膩渋酸歛膠粘、実熱、引入陰分)、
漸耗真陰、亦成絳舌、而為陰虛難療矣
(其初必有黄苔、医者不知、久之内傷己甚、不能顕苔、而変絳色矣。
凡陰虛火旺之病、自生者極少、多由医家誤用補薬逼成也)。
不論病状如何、見絳舌則不吉。・・
(引用:『舌鑑弁正 訳釈』P221~222)
・・痩せた人は火が多く、実熱に偏る、医者は外見にとらわれ、痩せていれば虛とする、
誤って温補を服用し、心陰を焼き傷る、誤って慈補を服用
(滋陰降火という、実すれば則ち膩渋酸歛膠粘、実熱、陰分に引き入れる)
真陰が次第に消耗、また絳舌となる、陰虚が治り難くなる
(初めは必ず黄苔、医者は知らず、時と共に内傷が甚だしくなり、苔が目立たぬまま、絳色となる。
陰虚火旺の病、自らそうなるものは極めて少なし、多くは医家の補薬の誤用によるもの)。
病状がどうあれ、絳舌は則ち吉ならず。・・
実際の臨床に立たせて頂いて、感じることの一つに
下焦の邪が強い患者さんが少なからず居られ、
その下焦をいかにクリーニング出来るかが重要に思えるケース。
補瀉の取り扱いは極めて慎重であるべきだと思いました。
鍼灸学校においては腎に実証はないと教育されますが。。
経験を積み考察を深めたいと思います。
今回は黄苔の存否などは分かりやすいと思えました。
【参考文献】
『舌鑑弁正 訳釈』たにぐち書店