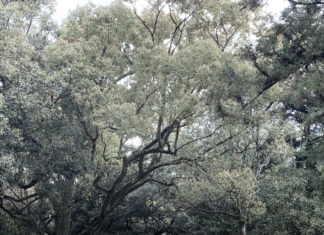観察の記録
===========================
2021/10/02 『観察の記録』
ある方の体を診せてもらった、その際の記録として。
母趾の足背に向けたキツい反り方が、やや和らいで見えた。肝気の亢進は見られず比較的精神的に穏やかに映る。
神道 ーその上下はまったく沈黙している。その点だけにはっとするような顕著な反応。刺す様に入ってくる感覚に当てるべき表現が分からないので、受け取った感覚のまま記録する。
===========================
2021/10/04 『エラー』
駅までの道。公園を自転車で通り抜ける途中、歩道のコーナーで思わずハンドルを切ってさけたのは芋虫がいたから。
自分より前を行く誰かが誤ってタイヤで轢いてしまったのだろう。地面につぶされた体の後方は動かない。代わりに動ける前方を動かしてもがいている姿が視界に飛び込んできた。
恐らく1秒に満たないわずかな時間。視野全体からするとほんの一片。エラーの情報は流れ込んでくるようになっているのかもしれない。
===========================
2021/10/05 『朝と夜』
朝焼けの薄明かりは光量も質も変化する。夕焼けの変化はそこに引いていく性質を伴う?
意識の変わり目は、やはり、同時にからだの変わり目でもあるはず。同じ性質の中で続く様に見える真昼間と比べて、からだが、意識が、より大きく動いているようにと思う。
鍼治療を受ける時、独特の時間の感覚を伴う事がある。普段の、眠っているときとも、覚醒しているときも異なる。そんな所に一度入ったあと、戻る。これにおいては昼間でも夜間でも起こる。頭の処理より上位にある経験であるのは明らかだけど、いつも何かしら新しい。
===========================
2021/10/06 『客観性』
ある日、継続的に診せてもらっている患者さんの体で、切経においてほとんど情報が拾えないことがあった。現場ではその理由は不明だった。
振り返ってみてー
脈状、舌、腹診いやそれより前に、患者を前にしてひと目で入ってきた情報、具体的には、目の周りの落ち込みや痩せ方など、急激な変化にうろたえたことに一因があるらしい。
合算するより前に、望診で得られた情報を真ん中に置き、その理由や原因を探して思考し、それに引っ張られていたからかも知れない。
===========================
2021/10/08 『心と脳』
奇恒之腑に分類される脳。
五臓のひとつ心が神を蔵す、として意識や思考活動は心の統制のもとなされる。
小学校何年の頃か、多分そのくらいに教わってそのままとり入れた考え方ー脳がコントロールセンターという立場で聞く「心」についての教科書の解説は、教科書的な読み物として流し読むに留まり、学生時代には検討すること自体すすめられずにいた。今なら読み取れることが少しずつでも出てくるはず。検討を再開する。
===========================
2021/10/9 『脈の変化』
診せてもらった患者の脈の変化について。
脈状は洪脈に分類できるものだと思う。やや浮位に偏る状態が処置後に、沈位まで行き渡る。(そうすると?)ピタリと一致してバラつき(と感じられていたもの)がなくなる。
一見、幅が広くなったようで、実際はまとまって雑さが消えて細くなった印象。
何度か経験して、この方において、調子が上向くときの徴の様に考えるようになった。
勝負
「患者さんが鍼灸院に入った時からが勝負です!」と下野先生からの一言。
一挙手一投足、速度、歩き方、手つき、表情、声色、姿勢、皮膚の色、身なり、体型…
私は舌や脈に固執していた事に気付きました。
院内はもちろんのこと、街でも、学校でも。
意識して目を養うこと、記録すること、真似ること、毎日が勝負です。
心がけていきます!
側頭部痛 2
(前回の続き)
側頭部痛(表面的な痛み)
を引き起こしている機序が何かー
その場では
結局見立ては固めることができず、
ただ、どうしても足部とくに三陰交付近に
深く引き込まれる感覚と
舌、顔の気色に熱の所見が認められる
ことなどから、三陰交に取穴した。
処置後、
体がやや熱くなっているとのことだった。
停滞していたものが動いたひとつの徴としてよいのか。
下焦の瘀血が気滞を生じさせ疎通を阻んでいたのか。(それならば瘀血の素因を何とみるのか)
「温か」ではなく「熱い」というのはどうなのか。
流れ
堰き止められた川が開放されるような感覚は初めてでした。
とてもシンプルなことなんだなぁ…
と治療を受けた後はいつも思うのに、本を読んでいる時は一言一句に目が止まって、中々前に進めない。
わざわざ自分でダムを作っているんだなと思う。
夢魇
知人が金縛りになったきっかけで昨年から金縛りについて調べています。
不眠の類と考えましたが、病因病機が見つけられず、ようやく金縛りについて書かれた書籍を見つけました。
「夢魇」とは、悪夢のこと。
例えば何かに押し潰されるなどして、驚いて目が醒めることが多い。
いわゆる金縛り状態になることもある。
心火熾盛を原因とすることが多い。
(針灸二穴の効能 呂景山著)
心火熾盛とは、心神が内擾すると心神不寧となる。
心は舌に開竅し心火上炎だと口舌に瘡が生じる。
(中医針灸学の治法と処方 : 弁証と論治をつなぐ邱茂良, 孔昭遐, 邱仙霊 編著 p.225)
「夢魇」というキーワードを見つけたものの、書籍を見つけられずネット検索してみました。
中医认为梦魇发生是患者体质虚弱、贫血,疲劳过度、及抑郁、生气、发怒等情志因素导致气血不和,神明失调所致。
(中医では、夢魇は患者の虚弱体質、貧血、過度な疲労、抑鬱、怒り、怒りなどの情緒的な要因が、気血不和、神明失調によるものだと考えている。)
【弁証】
肝胆鬱熱、肝胆上亢、心肝血虚、心虚胆怯、痰熱内擾、気血凝滞
(鬼压床的中医辨证及临床验方より 李士懋氏による臨床験治から抜粋)
ちなみに、「夢魇」は中国の俗語では「鬼圧床」ともいうそうです。
先日、知人を診せていただきました。
【現病歴】
長年不眠。2年前にインフルエンザに罹患して以来、間欠的に金縛りの症状が出現した。
強いストレスや過労の後は頻繁に起こる。
睡眠薬を服用しないと眠れない。
【問診】
考えて思い悩むことが多い、情志抑鬱、繰り返す悪夢、入眠困難、眠りが浅い、心悸、耳鳴、頭痛、咽頭痛、のぼせ、頸部の脹痛、倦怠無力、手汗、勝手に手を握る、歯を食い縛る、視力減退
【切経】
褪紅舌 歯痕舌 黄膩苔
舌裏は細脈が多く舌下静脈怒張 脈 細 数?
心窩部の詰まり
太渓穴の左右差、左霊道穴上方1寸に虚、合谷穴と太衝穴の圧痛、神道穴の詰まり、膈兪穴の隆起
顔色不華、頬紅潮、上肢の熱感、掌は汗をかくが冷たい、爪甲不栄、仰臥位で下肢の外転が強く小指がつく
収集がつかなくなってきたので、書籍から幾つかのヒントを得ました。
不寐証は病であるが一様ではない。ただ邪生の二字で知りつくすことができる。(中略)不寐の病は主として気血や臓腑失調のものである。(中略)気血を調和させ臓腑の機能を正常にさせることが主な原則となる。
長期に渡って鎮静安眠薬を服用している患者は、薬の関係で精神不振、倦怠、無力感(中略)といった虚に類似した証候が出現する場合がある。弁証を行う場合には、こういった証候を弁証ほ根拠とすべきではない。
(中医鍼灸臨床発揮 李世珍...
最近わかってきたこと。
毎週、先生方々から治療を受けるのですが、
どういう手順で治療を行っていくのかが少しずつわかってきました。
脈や舌、腹を見て人の状態を知り、そしてその人の身体の状態を理解する。
そして、弁証を立てる。しかし、弁証を立てるだけでは終わらない。
その病機の原因を探す。
表面上の治療で終わらせてはいけない。根本的な原因を見つける。
ここが肝であり、難しいところ。
これは下野先生がよくおっしゃってくださります。
これができるかできないかで治療のレベルが大きく。変わるような気がします。
林先生が言う「美しく治す」の一つの要素だと思います。
この病機の真意を理解するのは、合理、論理力と直感力の賜であるような気がします。
本に書いてある机上論だけでは培われない。
臨床の技術だけでは培われない。
直感だけでは、確信することができない。
これら全てが培われて、臨床で発揮できる感じがします。
まだまだひよっこですが、今のうちから意識し、臨床に立って本当の治療ができるよう励みます。
春になると・・・
私はいつも春先になると不調がでることが多く、
今までは梅核気や左中指に見に覚えのない腫れ(今でも原因わからず、1ヶ月位腫れていた)
今年は生理不順に胃の不調と、気分も落ち込みやすくなったりするので
春がくるのが待ち遠しい反面、不調がくることに怯え毎年身構えてしまいます。。。
でも。もう私も3年生になりますし、下野先生の施術も受けつつ、
せっかくなので自分でも鍼してみようとあれこれ原因を考えてみました。
生理不順については、最近は17日くらいの短い間隔で生理がはじまっておりそのせいで貧血気味で
胃の調子も悪いので脾の弱りが原因?年齢的に腎も原因かも?いつも春先に不調でるし肝の気があがっていることも考えないといけないのか?思いつく限りいろいろ自分の身体に鍼をして変化を観察しようと思います。
寺子屋でも先生方に、脈の変化を観察する方法や毎日自分に鍼してみたら?とアドバイスをいただいたので
さっそく実践してみます!
やっと暖かくなってウキウキする季節を心も身体も元気に過ごしていきたいです。
突発性難聴
突発性難聴の方に柴苓湯が使われていたので調べてみます。
柴苓湯 (中医臨床のための方剤学/東洋医学出版社 P.106より抜粋)
組成:小柴胡湯合五苓散
効能:和解半表半裏(通調少陽枢機)・利水
主治:半表半裏証あるいは少陽枢機不利で、浮腫、水様便などの水湿停滞が顕著なもの。
淡滲利水の五苓散を合方し、水湿の除去をつよめる。
少陽枢機不利とは何なのか?
枢機:肝心かなめの大切なところ。
枢⇒戸の開閉装置のくるる 機⇒石弓の引き金
扉の開閉がうまくいかず水が停滞している状態のことかな?と考えました。
ただ、2週間程度服用していたが症状改善には至っていない様子なので、
漢方変更するなら何になるのか、引き続き考えてみます。
参考文献
中医臨床のための方剤学/東洋医学出版社
頭痛と舌の記録
少し前になりますが、頭痛が一週間ほど続いた後、38度発熱しました。
PCR検査を受けたところ陰性で、胃腸炎と診断を受けました。
頭痛は日を追うことに痛みが悪化し、拍動性と動作時痛みが側頭部から後頭部にかけてあり、片頭痛とばかり思っていましたが、激しい痛みで立てなくなった後、発熱しました。
頭痛が起きる数日前は急に気温が下がり風がとても強かったです。
下肢に熱を持ち転筋、易怒、焦燥感、耳鳴り、更に光が眩しく感じられるようになり、発熱と共に目が抉られるように痛み立てなくなりました。
肝火からくる頭痛と考えました。
それと共に悪心、食欲不振、便秘、歩くと身体の中が痛いという症状も現れました。
肝気が鬱結して疏泄失調を起こしていた時に、脂っこい物を食べて肝胃不和の状態を起こしていました。
当時は何が起きていたか全く考えられず、舌の写真を記録しました。
発熱と共に苔が一斉に広がり、黄膩苔、裂紋が長くなり舌体が紅く膨張しました。
舌の状態が刻々と変わることに驚きました。
体が重い
先週から体調が変化してなかなか身体が重くてしんどい。
舌をみると真っ白な豆腐の粕の様なもので覆われており、脾募を労宮で触ると掌から抜けていく感じがし、指腹で触るとゆるゆるになっていて、両手が重い。
お風呂で温もると脾募が赤くなっていました。
数日前は入浴時、肺経が赤くなっていました。
関係あるかわかりませんが、最初に感じた身体の変化は1ヶ月くらい前で、胸のあたりに肌荒れが起こっていて、それが段々下に降りてきていた。
今は荒れが治ってきて少し脱皮し始めた。
調べると膜原に問題がある可能性もあるかも知れないと思った。
<中医臨床のための温病学入門> P136
「呉有可が「膜原は、外は肌肉に通じ、内は胃腑に近く、すなわち三焦の門戸、実に一身の半表半裏なり、邪は上より受け、直ちに中道に趨く、故に病は多くは膜原に帰す。」と述べるように、湿熱濁邪は膜原に鬱伏して、本証を発病しやすい。」
しかしこの邪が潜伏と言うけどもいつから潜伏しているかなど書いていないので気になる。
背中を診てもらっているとき膈のあたりがと言われた事があるが繋がっていないのか。
臓腑の働きが良くなると伏せていたものが浮き出てきたりすることはないのか。
気になるのでしばらく追ってみようと思います。
参考文献
中医臨床のための温病学入門 東洋学術出版社 神戸中医学研究会編著