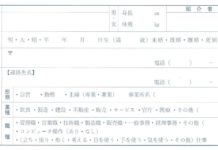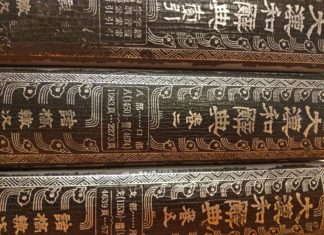針先、切経、治療報告
切経
経まずは形を追ってみた。
その後、手を当てる時にしっかり当たれば深さと方向が感じられた様な気がする。
また、その他の関連部位と反応を繋げても勉強になりました。
みるときの心の状態、大切だなと感じました。
変な緊張感は不要。
自分を作らない。
また、日常の訓練として、全てにおいて距離感を大切にしたい。
鍼先
学校で鍼を受けました。
よくあるパターンだったのでそこからどう動くのかは経験済みだったので自分でリカバリーできるか試してみた。
ただ自分のリカバリーする為の治療でも失敗を沢山しているので同じ穴でもやり方は変えてみた。
針先から伝わる感覚がいつもと違い、以前失敗した時と脈の前後の反応も違うのでここからどう動くか。
処置が今日なので明日以降どう変化するか楽しみです。
日曜鍼を受けて
結論から書いていくと翌日以降は調子が良くなって施術を受けさせてもらって良かったなと思いました。
お腹が弱ると自身の体感として猫背気味になるのでそのへんもピンとしましたし、翌日のある変化が起こったあとは脈も均等でした。
学校の授業での鍼などもあり、純粋な前後の状態を確認してもらえなかったのが残念なくらいです。
前後変化としては、その日はとても口が渇き、冷たいものを飲みたくなる現象と睡眠が浅いと言った状態になりました。
翌日、倦怠感があり何となく湯船に浸かったら変わるかなと思って入浴しました。
しばらく浸かっていると急にお腹が膨れて汗がひき、一瞬の不安感、吐き気が出た後、排便したくなり急いでトイレに駆け込むと排便と共に状態が良くなると言った経過でした。
その後の反応や施術後の変化を見ると選穴は合っていたはず。
後の反応は必ず起こり得るものなのか、もしくはコントロールできるものなのか。
自分が治療する時のために頭の隅に置いておこう。
色々
ブログ
自分のこと長い!
めんどくさいので頭を使いながらシンプルにやることをやれ!!
以上!!!!!!!!
そんなんばっかしてたら卑屈になるぞ!!
鳥山明さん
ドラゴンボールも連載のとき、連載が辛いので終わった時大喜びしていたそう。
元々小さい頃から絵を描くのが好きで、就職先も絵が描けない仕事場に回されると退職するほどだったけどそうなるんだな。
仕事は楽しいだけじゃできない。
人にうまく会話を返せる人
会話をしていて面白い人は自分で喋るのが上手い。
色んな話を出来るから、相手が話を振ってきても喋れる。
元々が受け身ではない。
でも合わせる。
男坂
自分に足りないものを求めてネカフェへ。
そこで出会った本。
「男坂」
漫画の冒頭での挨拶も面白い。
いい本でした。
舞台など
舞台
主役をどこに置くか。
そこが以前からずっと課題として残っている。
受付でもこのシーンはこの人にやってもらった方がいいかな?と考えたりもするが黒子になる意識が薄い。
これはチームで行っている事。
受付時、一緒に働いている方々にやって頂いている事を思い返す。
上手い人達はサラッとして作意がないが、落としたところを助けて頂いている。
そうなる為にまずは太極的に、先の動きも考える。
感じられるところまでいければいいが、まずは考えてみる。
考えた上で考える事が違っていれば考えを捨てる。
自分の場合、内省して答えを出すというより、他からヒントをもらって練度を上げていきたい。
外を見る目を養う為にも意識を変えなきゃいけないな。
やり方は色々試していきます。
舌の考察①
色:淡紅
形:軽く歯痕舌、軽く胖大
その他:斜舌
裏は出すのに苦労している様子も窺える。
正気が無くて出せないというより、緊張して舌を操作出来ていない印象。
口の開け方、舌下静脈は偏る
脾気虚。
口の開け方や斜舌など偏りを感じる。
気の偏りがあるかもしれない。
また、舌下を見せるのに歯が見えるまで出すところに真面目で気逆を起こしやすい要素があると思われる。
舌の考察②
前回よりも舌下静脈付近の細絡が目立つ。
これも瘀血の症候としてみれそうか。
以前として強い歯痕舌が見られ、気虚の程度が強い。
考察③
暗紅色、裏に熱がこもり、瘀血。
自身の体なので他の情報と一致させられるが、舌先右の赤みは右の上焦の停滞と一致させられるかもしれない。
西葫芦(ズッキーニ)
数か月前から外食が多くなったせいか、身体の不調が5月から改善しないので、薬膳を取り入れて少しでも食生活を改善してみようと思いました。
ズッキーニとウインナーのカレーマヨ炒め 【料理家ぐっち夫婦のRECIPE BOOK】参照
材料 2人分
ズッキーニ 1本
ウインナー 5本
オリーブオイル 小さじ2
【A】
マヨネーズ 大さじ1
カレー粉 小さじ1/2
にんにく(すりおろし) 少々
①ズッキーニはヘタを落とし、縦半分に切り、1cm幅の半月切りにする。ソーセージは斜め半分に切る。パセリは細かく刻む。Aはあらかじめ混ぜておく。
②フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、ズッキーニを両面焼く。ズッキーニに焼き色がついたら、ソーセージを加えて炒める。
③【A】を入れて炒め合わせる。
④全体に味がなじんだら皿に盛り、完成。
水の巡りを担う「脾と腎」に働くズッキーニ
性味:甘/寒
帰経:脾腎
効能:清熱、生津、通淋 現代の食卓に生かす「食物性味表」参照
転職してから仕事で夜遅くになることか増えて、外食で済ましてしまうことが多くなりました。そうなると油物に偏りがちだったり、コッテリ系の味になりがちで、普段の食事量より必然的にご飯の量が多くなり、かと言って残すのももったいないので、無理に食べすぎて自分の容量をオーバーしてしまう。駄目なスパイラルにハマっています。
初めは強い胃もたれの症状だったのが、鍼治療のおかげもあって最近は胃もたれは強くないのですが、下焦にきたのか尿の出が悪くなったなと思っていたら、股関節や膝関節が痛くなって治らないです。今では陽明と少陽ラインが、更に厥陰、太陰の内側も痛いんじゃなかろうかという状態です。
きっと季節的にも湿邪が絡んでるに違いないと、ズッキーニを食べてみました。
カレー粉も入れて鬱金の効果もプラスして気血の流れも良くなりますように。
先ずは基礎から
ほぼ10年ぶりに東洋医学の基礎理論の本を開いてみました。
結構忘れています。
東洋医学、特に中医学の言い回しって独特ですよね。元々が中国語の表現からの解釈になるせいもあるんだと思いますが、それが余計に理解するのを困難にさせます。
例えば
肝についての記載
陰を体とし、陽を用とす (基礎中医学 神戸中医学研究会 p45参照)
なんのこっちゃです。抽象的すぎて困ります。もっとハッキリ具体的に書いて欲しいものです(笑)
柔肝という文字もよく見ます。
肝の陰血を補うことで、肝陽を調整する治法
肝の陰血をもとに陽気が作動(陰を体とし、陽を用とす)し、肝陰の柔潤によって肝陽の剛強を抑制し、和らげている。 (基礎中医学 神戸中医学研究会 p46参照)
肝陰がなくなると柔→剛強に変貌するとあります。何だか物騒なことになりそうです。
そういえばC型肝炎の治療にインターフェロン療法が行われますが、昔に医療の現場で聞いたことがあります。治療を受けている患者さんの性格がだんだん変貌するそうです。怒りっぽくなったり、抑鬱症状が出たり、そうなると家族は大変なようで、そういう症状が強いと治療を一旦中断することも多いそうです。もしかしたら東洋医学的に考えてみると、インターフェロンによって肝陰が傷つけられてしまうのかもしれません。
ミート、霊道、名前
ミート
体の使い方の件で、なぜそうするかのイメージが繋がって発見がありました。
要領はサッカーのキックと共通する部分も多いにあると感じて発見がありました。
ただ、その前段階で患者との信頼関係が出来上がっていないと相手も反応してくれないと思うので
色々感じ取りながら、向き合いながら相手を主体にやっていこうと思います。
霊道
患者さんの状態を観察させて頂いきました。
成因についても教えていただき、またそれがなぜ起こるか。
穴から背景が見える現象が勉強になりました。
その時の患者さんの様子も覚えておこうと思います。
名前
その場所にいる時はどういった自分でありたいのか。
自分のスタンスを表す名前にしたい。
一つは「貞」を盛り込みたいと思います。
意味は二つの意味で一つは自分のためで、もう一つは医療人としての意味を込めました。
自分のための意味としては
貞には「定」という意味があり、精神が安定して惑わされないという意味もある。
頑固になる訳ではなく、一つ自分の核を持って物事に向き合いたいと思います。
堅物になりたい訳ではありませんが、奥底にはいるべきものを納めて浮つかないようにしたい。
医療人としての意味は易学の乾元亨利貞から取りました。
この意味を表す前置きとして、
「尚書」の「天一生水、地二生火」
の言葉があり、
万物発生論としてまず水が生まれたとの考え方が私は好きだからです。
菅子でも
「人は水である。男女の精気が合し、形となったものである」とあり、水に人間を例えています。
水は坎水なので、坎を探ると陰の画象、陽の画象、陰の画象で出来上がっている様に中に陽を宿す。
その水が生まれる前段階として
乾(純陽)と坤(純陰)が交わりがあり、
坤(陰)の中に陽(陽)が入ることで水が生まれた。
昔、大変自分に影響を与えた本で火神派ではなく火神派的な医案解説集という本があり、そこには
生命現象とは「無形の陽気」が「有形の陰気(肉体)に宿っている状態」といった内容が書かれていました。
ここで患者さんの生命現象の本質を水の中に宿る陽で見てみた時、
乾の特性である「元亨利貞」は
訓読みで
「元まり亨り利しく貞し(はじまりとおりよろしくただし)」
易経講話
「天の大元気の働きによって、万物は始まり生まれるのである。それが元であり、始まるのである。
それが始まり生まれると、だんだん盛んになり、十分に伸びていくのである。
それが亨であり、通るのである。
盛んになり十分に伸びていくと、それぞれの物が各々そのよろしきを得、その便利とするところを得るのである。
大きくなるべきものは大きくなり、小さくあるべき物は小さくできあがり、太いものは太く、細いものは細く、各々そのよろしきところを得、各々その利とするところを得るのである。
それが利であり、よろしきである。
各々そのよろしきところを得ると、その正しきところを堅固に守って完全に出来上がるのである。
それが貞であり、正しきである。」
これが私には良い状態の人間の一生の様にも感じられ、貞は完成形なので、患者さんの最大限のパフォーマンスを最大限発揮できる貞の状態に持っていきたい。
との意味から貞を選びました。
一文字でいくか、他の文字も入れるか考えてみます。
参考資料
易経講話(1) 公田連太郎 明徳出版社 P141〜146
火神派ではなく火神派的な医案解説集 小金井信宏著 星雲社P26〜35、P108
中国の水の思想 法蔵館 蜂屋邦夫 P148、149
心血虚証
心の血不足によって血脈が空虚になり、身体を滋養することができなくなる。
心血が不足すれば「神」にも影響が出る。
思慮過多、心労過多、目の使い過ぎ、血の生成不足(脾胃の失調からくる)などが原因。
心悸、怔忡、胸悶、眩暈、健忘、不眠多夢、顔面蒼白などの症状が現れる。
心血虚が痩せやすいのは、脾胃からの影響を受けて血の生成不足が起こり、
身体が栄養を吸収できないため。(舌もやせてくる)
心血が不足し、神を滋養できなくなると落ち着かなくなり、不安になる、心悸怔忡がおこる。
(眩暈や健忘が現れるのは血が少なくなり、髄海を養えないため)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
舌の考察 2023/12/20
先日、職場の薬局での出来事。
窓口でのやり取りの際、「処方箋に頼んでたお薬が記載されていない。先生が書き忘れている」と、患者様が言われました。
そのお薬の名前を尋ねると、「レイボー」だと言われるが、全く初めて聞く名前だったので、なかなか聴き取れませんでした。
当然薬局の在庫にはないお薬なので、処方医に問い合わせて追加処方してもらい取り寄せという形になりましたが、後で調べたところレイボーなるお薬は偏頭痛のお薬でした。2022年6月8日発売されたばかりの新しいタイプのようです。
今までのトリプタン系の偏頭痛薬とは異なった作用機序で、セロトニン1F受容体に結合して脳の神経に働き痛みを起こす物質の放出を抑えるとありました。
果たしてこの患者さんに効果があるのか。
もうすでに飲んでおられる様で、1錠では効かなかったとのこと。今回からは1回に2錠に増量してみるようです。
結局のところ、偏頭痛の原因や作用機序はまだはっきりわかっていないのが現状なので、あくまでもセロトニン仮説もその一つの考えであるため、その患者さんにフィットするかは未知数なのは必至でしょう。
偏頭痛もなかなか難しい症状です。それでいて結構多くの人が悩まされている頭痛の一つです。
そんな偏頭痛に対して鍼灸はかなり効果があることで知られていますが、実際受ける人はまだまだ少ないのかもしれません。
今週の舌です。
今週もお疲れの様子です。
色味も薄くて気血が足りてない感じです。気の不足により停滞感が見られ、むくんでいます。
脈は浮大滑 やや中空
苔はしっかりついていますが、通常に比べてば、まだまだ薄い方です。写真の写り方にもよりますが、色味はいつもより淡い様に見えます。生理後でやや淡白なのか。
そういえば最近は目が乾燥して疲れやすいです。スマホを見ると悪化します。
客氣の”客”
景岳全書 伝忠録
夏月伏陰續論
『主氣と異なるものとして、客氣がある。天は五氣を周らし、地は六氣を備えている。・・
・・この客氣は冬であろうと夏であろうと、その季節とは異なる氣を引き起こして、人々を病気にさせる氣である。・・』
『夏期になると陰気は伏して内にある。これは本来、天地の間における陰陽消長の理である。・・』
の冒頭から始まるこの篇ですが、
朱丹溪との陰陽の考え方の違いを解説し、張景岳の持論を展開している章になります。
この章を咀嚼した内容は別の機会に上げさせて頂くとして、
ときおり出てくる”客”が気になりましたので、調べてみる事としました。
【客氣(かくき)】
1⃣一時のから元気。血氣の勇。假(仮)勇。
2⃣其の歳の運を動かす外部から來る運気。主気に對(対)していふ。
客
①よせる。よる。身を寄せる。
②まらうど(客人)。主の對。
③上客。一座の尊敬する人。
④かかり人。
⑤外來人。
⑥あひて。
⑦たびびと。
⑧たび。
⑨居處(いどころ)の定まらない者。
⑩人。士。
⑪とくい。得意。顧客。
⑫來しかた(過ぎ去った時)。過去
⑬姓。
この夏月伏陰續論の客氣に関していえば、主たる氣とは別の
「病をもたらす得体の知れない氣」といったところでしょうか。
景岳全書の後の章、「命門余義」の中には
『・・三焦の客熱として邪火がある場合も火が原因となっているのであり、・・』
とあります。この客熱もまた、主体の火化とは異質の火に感じられます。
經穴では、
小陽胆経の經穴で上関穴を別名:客主人といいますが、この場合は
「頬骨弓を挟んだ、下関穴の相手方」という意味として、鍼灸学校で教えて頂きました。
その意味合いだけなのかどうか、今後の新たな発見を目指したいと思います。
【参考文献】
『大漢和辞典』大修館書店
『新版 経絡経穴概論』医道の日本社
『現代語訳 景岳全書 伝忠録』たにぐち書店
張景岳曰、
明清時代、痰に関する研究は日増しに整備されていった。
張景岳は「痰には虚と実とがあり、・・・最良の治療は、痰を発生させない事である。これが天を補うということである。」
と述べている。(『中医病因病機学』第20章 痰飲病機)
気になりましたので備忘録として置いておきたいと思います。
先生方で『景岳全書』を購入するなら、”この出版社がおススメ”などあればご教授頂ければありがたく思います。
【参考文献】
『中医病因病機学』東洋学術出版社